日本婚姻史概説
日本婚姻史概説
ヒトのはじまり
ヒトと類人猿の祖先に「ダーウィニウス」と呼ばれる化石動物があります。四千七百万年前に棲息していたとされていて、この頃から既に親指と他の指が対置するようになっているといいます。つまり、その時点でモノを掴んだり、摘んだりすることができていたのです。なのにどうして人類に至るまで道具を発明できなかったのでしょうね? よく直立二足歩行によって手が自由になり、自由になった手を活用するために道具を産みだしたと説明されますが、常時フリーというだけでどうして道具の発明に繋がるのでしょう。学者は時々意味不明なことを平然と言いますね。
今から六百十万年前から五百八十万年前に棲息していたとされるオロリン・トゥゲネンシスは、木には登れたけども腕渡りはできなかったと見られており、直立二足歩行をしていたと考えられています。また、今から四百四十万年前に棲息していたとされるアルディピテクス・ラミドゥスは、足の指が手の指の様に物を掴める構造になっているにも関わらず、直立二足歩行をしていたことがわかっています。彼らはどのような生活を送っていたのでしょうか。直立二足歩行をしていたのだから道具を発明していたのでしょうか。ぜひそんな遺物が出てくるといいですね。学説を証明するチャンスですよ!学者のみなさん!
ところで、ヒトを特徴づけるものとして、大脳新皮質の大きさがあります。ヒトは他の動物と比べて突出して大きいのです。ここは、合理的で分析的な思考や、言語機能をつかさどるとされています。なぜこんなに大きいのでしょう。過程は不明であるものの、大脳新皮質がより大きい種が自然淘汰を克服して生き残ったのですが、大脳新皮質が大きいことにどんなメリットがあったのでしょうか。
チンパンジーと共通の祖先からヒトが分かれたのは、五百万年前頃、あるいは五百万年前から八百万年前のどこかと言われています。チンパンジーの大脳新皮質はかなりに大きいもののヒトに比べられるものではありません。明らかにその後の進化で手に入れた機能であることがわかります。ラマルクの用不用説の立場を採るにしてもダーウィンの自然選択説を採るにしても、大脳新皮質の大きさがより大きくなる方へ進化してきたことは事実です。それが有利になる環境を考えてみましょう。
ヒトが地上へ降り立った時、アフリカは乾燥化が進み、サバナが形成されたと考えられています。そのため、広葉樹が激減し、ヒトは足の指が対向しておらず、木から木へ木渡りができません。そのため、地上におりてエサを探す必要に迫られたのが始まりです。森林の中にいては危険な肉食動物が跋扈していますし、エサもないので必然的にサバナ森林の外へ進出することになります。この時のヒトの体はチンパンジーとさして変わらない体躯をしていたと思われます。しかし、森の中にいてもエサがない脆弱で襲いやすいエサであるヒトが地上に降り立てば、それを狙う肉食動物もサバナに出てきました地上に降りてきましたから、安全性という意味ではあまり変わりがありませんでした。唯一直立していたので、ある程度の見通しができたことは確かですが、肉食動物に近づかれていればそれも無駄です。現代人もそうですが、肉食動物に捕捉されれば、ヒトの足ではまず逃げ切れません。あるいは、ヒトが恐怖でパニックに陥ったり、あるいは体が動かなくなったりするのは、群の一部を天敵に食わせることで、残りが生き残る戦術だったのかも知れません。いずれにせよ、ヒトの恐怖はここから始まるのです。
木から降りたばかりのヒトは、直立二足歩行ができるという以外、石器もなく、当然火もなく、身を守る術を持ちませんでした。肉体が進化によって改造されるのを待っていては絶滅してしまいます。森の中で培われてきた本能は何の役にも立ちません。それでも死ぬのがいやですから、頭を振り絞るしかなかったと思われます。どうすれば外敵から身を守れるか、どうすればエサが手に入るか。現代を生きる我々にはその切実さがピンと来ませんが、当時の環境ではこれは不可能課題です。決して答えが出る問いではありません。しかし、答えを出さねば絶滅です。実際、そうやって絶滅していった集団がいくつもいくつもあったでしょう。
ヒトの思考は大脳新皮質によって支えられています。それは本能では解決できない課題を克服するために、視覚や聴覚といった五感から情報を収集し、これを総合して新たな方法を見いだすのに不可欠なものでした。より大きい大脳新皮質を持った種が淘汰圧力を跳ね返し生き延びることができたことは想像に難くありません。何よりその結果が現代の私たちです。より大きな大脳新皮質はより柔軟で新しい思考を可能としたでしょう。わずかな大脳新皮質しか持たない種は環境の変化に耐えられず絶滅してしまったと言えます。
しかし一方で、脳は大喰らいの内臓器官です。ほんの少し酸素の供給が断たれただけでも広範囲に壊死が発生します。栄養も潤沢に供給されなくてはなりません。そのくせ疲労がたまると活動がにぶくなり、睡眠が必要になってきます。ヒトやヒトに飼われている動物以外は、睡眠を取るといっても、まるで仮眠しているようです。少しうとうとしては目を覚まします。ヒトも最初はそうだったでしょう。しかし大脳新皮質が拡大するにつれ、それではとても間に合わなくなってきます。つまり長時間じっとして意識を失う睡眠を取る必要がでてきたのです。大きな大脳新皮質を手に入れた代償でした。こうしてますます外敵からの自己保存に神経を尖らせなくてはならなくなったのです。
ヒトのそのような脆弱性に目をつけ、始原のヒトは夜行性だったのではないかという人がいます。もちろんそんなことはありません。夜は肉食動物の支配する世界です。そんなところをうろついていたら真っ先にターゲットにされてしまいます。また、ヒトの視覚は昼間目を使うことに最適化されており、夜目が利きません。最初のヒトが夜行性なら夜に最適化された目を持つ種が生き延びたでしょうから、そのような考え方は否定されます。ヒトは夜が明けると共に目を覚まし、昼間活動し、夜は、例えば岩陰や洞窟など比較的安全を確保できるような場所で眠ったと考えられます。眠る時はひざをかかえて体を丸めて眠ったでしょう。この姿勢は外敵に襲われた時に致命的な傷をなるだけ受けない姿勢であり、また後に葬送儀礼が発達した時に屈葬で葬られていることからも、まず間違いないと断定できます。
その頃のヒトは何を食べていたのでしょう。おそらく何でも食べたと思われます。木登りができなくなったわけではありませんので、木の実はもとより、肉食動物の食べ残し=すじ肉や骨髄、鳥の卵、海や川があれば海藻、魚、貝、なまこの類い。骨髄や貝の堅い殻を割るために、石を使ったのが最初の道具かもしれません。ヒトはアミノ酸のすべてを合成できず、必須アミノ酸を食事で摂取しなくてはならない上、その中には植物にはあまり含まれていないものもあるため、肉食動物の食べ残しを漁っていたことは確実です。
この時ヒトはどのような社会を作っていたのでしょう。チンパンジーと共通の祖先から分化したのですから、血縁の集団で行動していたことは間違いないでしょう。ヒトの集団には、意思決定において最終決裁権を持つリーダーが必ず存在します。チンパンジーにはリーダーがいるのかいないのかよくわかりません。これは不可能課題を抱えたヒトの集団が、最も優れた=最も安全でかつエサを入手できる場所を探って移動先を決めることができる個体に決定権をゆだねたことに端を発するのではないでしょうか。不可能課題は誰にとっても解決不可能な課題です。もちろん全員頭を振り絞って考えたかも知れません。過去の経験からどうすれば、肉食動物の魔の手を掻い潜り、エサを手にすることができるか。しかし、不可能課題であるがゆえに絶対に答えは出ません。出ませんけど出さないと絶滅です。その中でこっちだ!と誰かが指し示せばそれに従うしかないでしょう。
一度それがうまくいけば、次も期待が集まるのは当然です。その期待に応えて再び道を指し示すことになったでしょう。時には間違い、肉食動物の犠牲になった仲間が出てかもしれません。あるいは期待していたエサがなかったかもしれません。しかし元々不可能な課題であることは全員承知しているのです。余りにも間違うのであれば、誰も従わなくなったでしょうが、そうでない限りはその者—もうリーダーと言っても差し支えないと思います—に従ったでしょう。こうしてリーダーが指導し、集団のメンバーがそれに従うという社会規範が形作られていったと思われます。
リーダーは何をどう考えてメンバーを導いたのでしょうか。もちろん、過去の経験から肉食動物がいなさそうなところ、睡眠を取っても安全そうなところ、エサのあるところを推測したでしょう。しかし一度エサを取ったら、例えばそれが植物の果実であれば、次にまたエサが取れるのはしばらく先になります。一度は安全だったからといって次も肉食動物がいないとは限りません。メンバーも必死ですからああすればどうか、こうすればどうかと考えるでしょうが、しかし決定はリーダーが下さなくてはなりません。この懊悩は計り知れない重圧となってリーダーの肩にかかってきたでしょう。おそらくですが、ヒトという種自体が短命である中で、リーダーはストレスでさらに短命であったに違いありません。逆にリーダーにストレスを集中することで、ヒトという種が生き残る戦略を採ったとも言えます。
これは現代の組織に繋がる普遍原理であるとも言えます。あるいは、統率された行動を取るヒトの集団には、リーダーが不可欠ですが、これはなぜかと問い直してもよいでしょう。この時代、エサを探す、天敵から逃げるという基本行動自体が不可能課題であるということは、全員でこの課題を担ってしまえば種として生き残れなかったことを意味します。現代でも不可能課題を与えて逃げ道を塞ぎ、達成を強く促せば、ヒトは見る見るうちに病み、あるいは自殺してしまいます。これはヒトに限りません。不可能課題に直面した動物はひたすら逃げます。逃げおおせなかった場合は死が待っています。原始のヒトも同様ですが、エサを探す時点でそれが不可能課題になってしまっていては、その課題から逃げることはできません。それもまた死が待っているからです。この八方塞がりの課題圧をリーダーに集中することで、種あるいは群としてのヒトが滅ぶことを避けたと考えるべきでしょう。リーダーが一人そのストレスから死を迎えても次のリーダーを出せばよく、群そのものは存続していくことができます。リーダーの意思が群の意思となり、リーダーに権力が集中することは、そうすることでリーダーを使い捨てていき、群自体の滅亡を避ける原始的な知恵であるがゆえに、人類の歴史を貫く普遍原理たりえたのでしょう。
以上のような状況にあったことを年頭において、あらゆる風俗の根本にある性風俗=婚姻の歴史をこれから見ていきたいと思います。
え、何で性なの? とお考えの方もいらっしゃるでしょうが、よくお考えください。性交は有性生物に普遍的な課題です。時には雌を巡って雄同士が争い、あるいは雌を引きつけるために懸命に誘い、動物の特徴的な行動様式の基本には必ず性が存在します。ライオンのプライドやゴリラの群れなどのように、生殖、繁殖様式がそのまま社会様式になっている動物は数知れません。つまり、ヒトの歴史を考える上で、その生殖様式や繁殖様式を規定する性規範、婚姻の問題は避けて通れない課題なのです。ところがどういう訳かこれを研究している学者は少ない。まるで歴史に性は関係ないかのような態度を取っているかのようです。まあここは、余りにも基本的な命題であるがゆえに、手を出しづらいのだと好意的に解釈しておきましょう。それでも、この課題に果敢に取り組み、成果をあげておられる方もいらっしゃいます。この稿は、基本的に、高群逸枝氏の『日本婚姻史』至文堂、昭和38年5月30日初版、を参照しつつ、それを補う形で論を進めます。もちろん、これを読んでいない方にも理解の妨げとなるような書き方はしませんので、予めご承知おき下さい。
族長婚
「婚姻制度の歴史を考える – ①婚姻の始まり」と内容が重複する部分も多いのですが、しばらくおつきあい下さい。
ヒトの始原において、リーダーは不可能課題に取り組まねばならなかったことを先に書きました。答えを出さなくてはならないのにそれが不可能なこともまたわかっているという状態は、過大なストレスを心身にかけます。どちらへ行けば外敵の目に留まらないか。どこへ行けばエサにありつけるか。嵐にでくわしたりした時、どうすればこれをやり過ごすことができるのか。「はじめに」で挙げた「オロリン・トゥゲネンシス」は身長がチンパンジーほどしかありませんでした。チンパンジーが決して大人しいばかりの凶暴性を持たない類人猿だとは言いませんが、大型肉食獣やいきなりの自然災害には全く無力です。始原のヒトもやはり同じように全く無力だったでしょう。ヒトの直接の祖先につながることが明確である、アウストラロピテクス・アファレンシスの代表としていつも取りざたされるルーシーは、身長が1.1mしかありません。仮に性的二形が大きかったとしても、脆弱といってよいサイズです。
ヒトの群れを考える前提として、性的二形を考慮してみましょう。性的二形が大きかった場合、一頭の雄が複数の雌を従える群れを作った可能性が大きくなります。そうではなく、性的二形が比較的小さい場合、雄雌が混在した群れを作っていたことが考えられます。現代人類の性的二形による体格差は10%程度です。決して小さい値ではありませんが、ゴリラのように大きいわけでもありません。悩ましいですね。ですが、ここはヒトの雌雄の体格差は、外敵闘争への最適化による体格差だと見て、生殖上は概ね対等だったと考えましょう。
とすると、雄雌が混在した群れを作っていたことになるのですが、どのように生殖を行っていたのでしょうか。ヒトの生殖負担が他の哺乳動物と比べても極端に重いことは有名です。出産、育児において現代でも女性の負担が重すぎて、社会問題にもなっているように、始原のヒトにおいては、食料の採取もままならないほどの負担になったと考えられます。ここで雌の取る戦略は雄に一定期間、つまり出産、育児の間保護してもらう方向へ舵を切ります。当然ですね。
さて一方雄の方はというと(雌もですが)、不可能課題がリーダーに丸投げされているわけで、他の雄はそれに従うことが求められます。でないと集団が行動できないのだから当然ですね。それは他の雄を軽んじるとか無視するということではありません。しかしお互いの顔を見あっても答えは出てこず、それゆえリーダーに解決が委ねられるのですから、当然の帰結です。さてそのリーダーの懊悩はいかばかりだったでしょうか。集団の期待を一身に浴びて逃げ出すこともできず狂おしいほどに悩みに悩み抜いたと考えられます。太古、歴史時代に入っても、栄養状態のよくない時代のリーダーは——その頃は「王」と呼ばれていましたが——多くの人が短命です。あまりに過大なストレスがかかるため、寿命を全うできないのです。集団にはリーダーが不可欠ですし、優秀なリーダーともなればなおさらです。農耕が始まり、食料摂取に大きな不安が恒常的に存在したわけでもない時代の「王」でも短命なのです。始原のヒトのリーダーはまさしく燃え尽きるように死んでいったでしょう。折角リーダーを選んだのに、瞬く間に死なれては集団が困ります。あるいは、死なないまでも「燃え尽きて」しまってリーダーの職務を全うできなくなっても同じです。となると、何らかの形でその重圧を開放してやらなくてはならないのです。
人間の二大本能欲とは、食欲と性欲です(睡眠欲を入れて三大欲求ということもありますが)。性欲と性の快感を強化することで、一時的にせよ、重圧の開放としたことは進化の結果、つまり現在のヒトを見ればわかります。常時発情しているのは、常時発散ができることを意味します。プレッシャーに潰されそうになった時、いつでも性交による快感を得てプレッシャーを一時的に回避して潰れてしまうことを避けたのでしょう。同時に雌の性欲も強化されています。常時発情もそうですが、雌が性交から非常に強い快感を得るのは、他の動物ではあまり見られません。これは雌の性欲求を強化し、リーダーを挑発して性交させることで、重圧を回避させたと考えることが理にかなっています。同時に、集団の維持がリーダーの双肩にかかっているとなれば、生殖の保護をリーダーに求めるのもまた必然でしょう。
つまり結果的に、リーダーにすべての雌が集中する婚姻形態が存在したことになります。これを表す適切な言葉がないので今ここで『族長婚』と名付けましょう。最も近縁のチンパンジーが二十から百頭程度の群れを作って生活しているので、ヒトの血縁集団も二十人前後から最大でも百人だったと思われます。これは子供も含んだ数ですから、生殖適齢期のメスはそんなにたくさんはいなかったことがわかります。リーダーに雌が集中してもリーダーが十分対応できる数でもあります。性欲の強化がリーダーにかかる重圧の開放にあったとしたら、性はリーダーにのみ開放されて、他の雄は封鎖されることになります。もちろんつまみ食いをする雌がいなかったはずはないのですが、基本的に他の雄は、一人寂しくマスターベーションだったのです。マスターベーションの歴史は古く、エジプト神話に既に記述があることから、歴史時代以前から行為としてあったことは断言できます。他の種と違い、性欲が極度に強化されているので、雌に相手にされなくてもどうにかして性欲を発散しないと集団の行動に支障を来すことから、ヒトの始まりとほぼ同じくらいの歴史があると私は考えています。ヒトはその始まりから「モテない奴はマスかいて寝ろ」を実践していたわけですね。
リーダー以外のメンバー、特に若い雄にとって、性が封鎖されることは辛いことです。しかし、リーダーになればそれが開放されるわけですから、若い雄が切磋琢磨して次のリーダーになろうとする強力な動機付けにもなります。おそらくリーダーはあまりの重圧に短命だったでしょうから、群れは常にリーダー予備軍を抱えている必要があったでしょう。その意味でも性が強化されていることは都合が良かったのです。
ところで、メンバーは彼が答えを指し示すことを期待していますが、リーダー自身、誰かが答えを指示してくれることを切実に望んだでしょう。もちろん、そんな人は存在しません。いや、かつてはいたのです。リーダー自身が子供のころはやはり集団を導いたリーダーがいたわけですから、その人が死んだ後も自分たちに道を指し示してくれることを期待し、何とかそれを見いだそうとしたと思われます。死が特別であることはその頃も理解されていたでしょうが、メンバーの期待に応え、集団を導いた偉大な先達に、つまり血縁集団で前のリーダーということは自分のオヤに、今のリーダーが期待をかけるのも当然です。しかし、死んでしまって目には見えません。目には見えないけど期待には応えてくれるという確信からひたすらそれを見てとろうと苦悩を続けたことは想像に難くありません。あるいは狂乱といった態でその方法を探し、答えを求めたのではないでしょうか。仲間に自分の希望を伝えるのは、顔を見て身振り手振りとわずかな声で十分だったでしょう。実際、チンパンジーはそうしてコミュニケーションしています。ところがこの場合、相手の顔は見えません。相手から自分が見えているかもわかりません。そこで、目には見えない相手に特別な方法で期待の内容を伝えることが必要だったのです。こうして言葉が生まれました。目に見えない、顔が見えない相手とコミュニケーションを取るために言葉という媒介物を発明したのです。
今でも本名を他人に教えることをタブーとする部族が世界にはいるそうですが、これは日本でも昔はそうでした。女性が本名を告げることは結婚の承諾になった時代もあったのです。現代は同族間のコミュニケーションツールとしか見なされない言語ですが、かつては祖霊に働きかけ、その結果精霊が動いて意図を実現してくれる、つまり言葉に超自然的な力があると思われた時代が永くあったのです。未開を脱した日本でも『言霊』信仰として永く残りました。現代に残る忌み言葉もその名残です。また、『言霊』信仰は洋の東西を問いません。旧約聖書でも神の言葉によって光が生まれています。
現代でもシャーマニズムにおけるシャーマンの踊りは、一面、狂乱と言って良いほどの激しさを持つものが多いのですが、始原のヒトのリーダーも狂乱に近い状態で先達に言葉で問いを発し、それに対して示される御徴を見て取ろうとしたでしょう。現代の企業代表という人たちの中にも占いや手相見に凝る人が少なくないそうです。それは未来を予測するということがいかに困難な課題であるかを示しています。始原のヒトのリーダーも言葉で自分たちの期待や希望をオヤに訴え、それに答えてくれることを期待し、様々な兆候からそれを読み取ろうとしたでしょう。あるいはトランス状態の中でひらめくものを教えられた答えだと見なしたかも知れません。当たり前ですが、それで安全な、あるいはエサのある場所にたどり着けたら、そのような期待は信仰へと昇華します。最も原始的な宗教は、オヤを崇めることから始まったでしょう。それが累代続けば、祖霊に対する信仰へと進みます。そして、オヤが道を示してくれるのは誰に聞いたのだろうか、あるいは災難から逃げられるようにしてくれたのは、何に働き掛けてくれたのだろうかという思考から、祖霊が働き掛ける対象としての自然精霊を措定したでしょう。すべての民族がアニミズムを経るのは、こういう理由があるのです。また性交が出産の原因となる因果を理解していなくても、女性が子供を産む性であることは一目瞭然ですから、祖霊と自分たちを繋ぐものとしてまた女性、母を崇めたかも知れません。血のつながりが祖霊の保護を受ける所以であったのですから、母性を崇めるのはむしろ自然であったとも言えます。
また、言葉を生み出したことによって別の効果が生まれました。それは、論理的な思考が初めて可能になったことです。論理は言葉に支えられています。言葉なくして論理的合理的な思考はできません。そして言葉を持った結果、何かをした時に結果がどうなるかを予測することが可能になったのです。それは決して現代的な意味での論理性や合理性を持ちませんが、予測とその説明が可能になったことで、人類の知的レベルは爆発的に向上したでしょう。それを端的に示すのが道具の発明です。道具は作り方もさることながら、どう使ってどのような効果が期待できるかを予測しないと作成することができません。カラスは堅い木の実を車にふませることで殻を割りますが、カラスが車を発明することはできません。道具を使用することと発明することは天と地ほどの差があるのです。道具に限らず、人類が駆使するあらゆる概念は、言語なしには成立しません。まず始めに「言葉ありき」なのです。
人類の歴史のうち、一体どれだけの期間、ヒトはそうやって過ごしてきたのでしょう。少なくとも五百万年は下らないと思われます。気が狂いそうな苦悩と懊悩の果てに、言葉を見いだし、祖霊を見いだし、道具を見いだした末に、遂には火を御すまでになりました。今から五十万年前(最近の説では七十八万年前)と考えられている北京原人の化石に伴い、火を使った炉の跡が出土しています。火を利用することはあるいはかなり早い段階から可能だったのかも知れません。しかし、火種を保存したり、新たに火種を起こす方法を発明するには、とてつもない時間がかかったのではないでしょうか。そもそも、ヒトはどうやって火を起こすことを覚えたのでしょう。現在に伝わる発火法は観察で得られるものがありません。不思議なものです。しかし、火に精霊を見ていたのなら、祖霊に願い、恩恵が与えられることを期待したでしょう。肉食動物に限らず、動物が火を恐れて近づかないことはわかっています。火は熱く猛々しく容易く死をもたらします。でも、火を味方につければ、外敵の恐怖がひとつ消えるのです。岩陰や洞窟といった特別な場所を探して眠ることもありません。火をたいておけば動物は近寄ってこないので、どこでも眠れるようになるのです。おそらく火を手に入れたことで本格的な人類の拡散が始まったものと思われます。
さて、このように俯瞰したとき、人類は言葉を発明し、これを駆使することで生き延びたことは容易に理解できると思います。大脳新皮質が小さい種と大きい種では、大きい種の方がより複雑な言葉を操り、より複雑な概念を理解する余地が大きいので、後者の方が生き延びて子孫を残すことになります。発情期が他の動物同様決まっていた種よりも、常時発情してリーダーに発散の機会をより多く提供する種の方が、リーダーに対する負荷を相対的に軽くするのでやはり生き残る可能性が高くなります。結果的に高度な思考を操りながらも常時発情し性での発散を指向するという、ある意味珍妙な、しかし極めて合理的な種が現在まで生き残ったわけです。
この「族長婚」において、集団は結果的にすべて近親になることは自明のことです。集団の外からメンバーを受け入れることがなかったとは言いませんが、サルとは異なり、共通の祖霊への信仰を持つ集団に定期的にハグレザルならぬハグレヒトがやってきていたと考えるのは非常に困難です。祖霊の指示に従ってリーダーが集団をまとめ、移動する習慣と信仰を持つ族のメンバーにとって、祖霊の庇護を受けないということは、死を意味します。そんな状態で群を離れて一人さ迷うなど狂気の沙汰です。これは、オキシトニンというホルモンの作用でも裏付けられます。家族や恋人、友人との抱擁、触れあいを通じてオキシトニンというホルモンが分泌され、愛着や信頼を強化します。このホルモンは同時に「人見知り」にも作用し、見知らぬ人間を怪しみ警戒する作用を及ぼします。ホルモンメカニズムに組み込まれているということは、器質的な問題なので、本能的に見知らぬ集団を避け、自分の属する集団に愛着を持つということになります。ハグレヒトなどいなかったのです。従って人類は、近親婚を繰り返して発展してきたと考えざるを得ません。尤も、集団の規範を破るような者が現れた場合は別です。おそらくごく稀ではあったでしょうが、罪を得るものが全くいなかったと考えるのは不合理です。その場合集団はどのような罰を与えたでしょうか。留置や財物による賠償は、私有制度が確立して初めて意味を持つ罰です。この頃に存在したとは考えられません。となるとひとつは殺してしまうこと。もうひとつは集団を追放すること。この二つのいずれかになります。いずれを罰とするかは、やはりリーダーが祖霊にお伺いを立てたでしょう。集団に生存を依存しているこの時代、集団を追放されることは死と同義です。が、自ら手を下すことと追放に処することは罰を下す側としてはやはり大きな差があったと思いたいものです。
この時期の祖霊信仰とはどのようなものだったのでしょうか。元々はオヤである先のリーダーとの対話欲求から産み出されたものですから、もちろん「父」が崇拝の対象となったのは自明のことです。しかし、その「父」と自分たちを繋ぐものは「母」による血のつながりが不可欠でした。性と出産が明確に関連付けられていたとは考えにくく、「父」が自分たちを保護する理由に「母」たちの息子、娘であるという繋がりを想定せざるを得なかったのではないでしょうか。予断なく見てみれば、妊娠、出産というプロセスは非常に神秘的です。なぜ何もなかったはずの女性の腹に命が宿り、それが育って子が産まれてくるのかという疑問は、全く謎めいているものの、自分たちがまさしくそのようにして産み出されたのだという事実から否定などしようもなく、無からヒトを産む女性に崇敬の念を持ったとしても不思議はありません。後に地母神信仰として確立する、大地を母性に託して信仰する宗教の根源は、この頃既に芽生えていたと言ってもよいでしょう。
しかしながら、ヒトはいつまでも同じところで足踏みをしていません。自然もいつまでも同じというわけではありません。気候が変化し食料の入手が困難になった場合、ヒトはどんな手段を講じたでしょうか。
私有婚
ヒトが生きてきた時代には、鮮新世、更新世が含まれ、その間に何度も氷期が訪れています。食料となる動植物を追い移動を繰り返していたヒトの集団も遂には身動きが取れなくなってしまうことがあったと思われます。気候の変動はゆっくりと推移する場合もあれば、急速に変化する場合もあり、かつての変化がどのようなものであったかは推測の域を出ませんが、食料を入手できなくなり絶滅してしまった集団も少なくなかったでしょう。
しかし時代を経て、人口が多くなり、人口密度が上がって集団と集団の距離が比較的近くなっていればどうでしょう。自分たちは食料がないかも知れませんが、他の集団はわかりません。このままじっとしていると絶滅が回避できないとなれば、他所から奪ってくるしかありません。即ち、掠奪です。掠奪を行う際、失敗すれば下手をすると全滅ですが、成功すれば、食いつなぐことができます。リスクの高い賭ですが、当然この賭に勝って生き延びた集団もありました。そのことは集団にどのような変化をもたらしたでしょうか。以下「婚姻制度の歴史を考える—②私有婚と私有制度・身分制度」でも触れた点がありますが、再度確認してみようと思います。
元のメンバーは血縁であり、同じ祖霊を信仰する同士でもあります。掠奪した食料は全員で公平に分配しないと不平が起きますので、これを占有したりできません。残るのは掠奪に負けた族です。当初は信仰も異なる族などうち捨てていたでしょう。奪える食料は全部奪うので、その後のことなど考えなかったに違いありません。しかし、ある集団が掠奪に踏み切るということは、気候を同じくする地域に住んでいる別の集団も掠奪に踏み切るであろう事は容易に想像が付きます。今度は自分たちが掠奪される側に回るかも知れないのです。そうして闘争が繰り返されると、戦いには数がものをいいますので、敗北した側を族に組み入れ、支配下に置く集団が出てきます。支配の方法ですが、一番ありえるのは、祖霊を奪い、それを掠奪した側の族の祖霊に奉仕する霊に位置づけ直すことで信仰を支配したことでしょう。
もちろんそれだけに止まりません。掠奪において戦働きの優れた者には何らかの形で報償を出さねばなりません。食料は族が生き残るために絶対に必要ですし、仮にたくさん分配されたとしても一人で食べきれる以上のものを貰ってもどうようもありません。食欲に報いることができなければ、性欲に報いるというのは的外れな推論でしょうか。いえ、まさに掠奪にあたって女も掠奪の対象とし、これを宛がうことで報償としたことは充分に考えられます。同じ族の女と違い、掠奪の報償として与えられた族外の女はその男の占有対象であり、他の男が手を付けることは許されません。でなければ報償にならないからです。これを『私有婚』と呼びましょう。分捕ってきて占有するのですから、私有以外の何ものでもありません。「掠奪婚」と言っても良いですね。というか通常はそう呼びます。現代、一夫一婦の家父長制を経験してきた民族のほとんどは、その歴史の過程で必ずこの「略奪婚」を経験しています。一夫一婦や一夫多妻といった『私有婚』の最も古い形態が「略奪婚」なのです。日本も例外ではありません。なので、原始、それまで族長にならなければ宛がわれなかった女が、掠奪闘争の報償とされたことはまず間違いないと断言してよいでしょう。
全ての『私有婚』の根源が「掠奪婚」であるということの証左は枚挙にいとまがありません。日本の例で言うと、歴史的にはごく最近の例として「昭和34年(西暦1959年)6月19日の鹿児島地裁判決」に見ることができます。この事件は鹿児島のある村の青年が16歳の女性に結婚を申し込んで拒絶されたけども、諦め切れず、従兄と叔父とで謀議した結果、女性を誘拐して、結婚を承諾させることにしたというものです。そして、通学中の女性を計画通り拉致し、従兄と叔父も加わって三人で馬小屋において無理やり姦淫に及びました。それを知った青年の両親は、青年と一緒になって喜んだといいます。当然、青年は警察に逮捕され誘拐と強姦の罪で裁判にかけられたのですが、弁護人はこの地方には婚姻に同意しない婦女を承諾させるため、その婦女を強いて姦淫する「おっとい嫁じょ」と呼ばれる慣習があり、被告人はこの慣習に従って行為に及んだもので、違法性の認識を欠き故意がないと、無罪を主張したのです。また、村も全村民の署名を集め彼の無罪を嘆願したのです。ちなみに、青年の母親もまた家族と食事中に青年の父親に拉致され強姦されそのまま結婚したと伝えています。歴史上で言えば有名な御成敗式目に次のような条項があります。「一、密懷他人妻罪科事。右不論強姧和姧懷抱人妻之輩被召所領半分可被罷出仕無所帶者可處遠流也女之所領同可被召之無所領者又可被配流之也次於道路辻捕女事於御家人者百箇日之間可止出仕至郞從以下者任右大將家御時之例可剃除片方鬢髮也但於法師罪科者當于其時可被斟酌」「一、他人の妻を密懐(=密通)する罪科の事。右、強姦和姦を論ぜず人妻を懐抱(くわいはう=性交)するの輩、所領半分を召され、出仕を罷めらるべし。所帯なき者は遠流に処すべきなり。女の所領同じくこれを召さるべし。所領なくばまた配流せらるべきなり。次に道路の辻に於て女を捕ふる事(誘拐、掠奪)、御家人に於ては百箇日の間出仕を止むべし。郎従以下に至つては、右大将家の御時の例に任せ、片方の鬢髮(びんぱつ=頭髪)を剃り除く(=丸坊主にする)べきなり。ただし、法師(=坊主)の罪科に於ては、その時に当りて斟酌せらるべし」とあって、式目に載せて成敗しなくてはならなかったほど、御家人から坊主に至るまで拐かしを行う者が多かったことがわかります。ヨーロッパでは、ローマ建国神話に「サビニの女たちの略奪」という有名な集団掠奪婚があります。また、ギリシャ神話でゼウスが乙女たちを誘惑するという下りは、誘惑ではなくまさしく掠奪で、こちらも起源に「掠奪婚」を持つことが語られています。この他にもありますが、余りに多いので後はご自分でお探し下さい。
さてそうすると、元から族にいた女たちと新たに掠奪されてきた女は同列に扱われたでしょうか。片や祖霊を同じくする同族の女性、片や掠奪されてきた私有存在=奴隷的存在である女性。同じであるはずがありません。元々崇める祖霊が異なるのです。元から族にいた女たちの腹から生まれる子は、族長になることも、また族長が妻とすることもできます。これは変わりません。一方で、掠奪してきた女の腹から生まれる子は、族長にもなれなかったでしょうし、族長の妻となることもできなかったでしょう。こうして血筋による身分の差が同じ族の中でできるのです。この差は「母系」で区別されますから、母系制による身分制度と言ってよいでしょう。この血筋が氏族となって、王の妻となる女を出すことのできる氏族(つまり王を出せる氏族)と、王に妻を娶せることはできないまでも高い身分を保持した氏族=貴族、闘争に敗北し支配下に置かれて従属した部族の中の数々の氏族=平民という身分です。中国では「商(殷)」の頃までこうした身分制度が続いたと思われます。今でも故事成語として残っている「牝鶏晨す」は『書経』の牧誓に出てくる言葉で、周の武王が「古来、雌鶏が時を告げるのは家が滅びるときだ。殷の紂王は雌鶏(妲己のこと)に血迷って暴政をしている」と殷を批判しています。これは血の継承が母系を基本にしていたため、女性の地位が相対的に高く、また王の妃は巫の頂点にあったためその占いを以て国政の指針としていたことを暗示しています。婦好の墓が殷墟で発掘され、実際に女性の地位が高かったこと、甲骨文などでも祭祀を担当しており、妃(この場合は婦好)が巫の頂点にあったことが確認されています。日本だと平安時代まででしょうか。日本の場合、大化の改新までは天皇の后を出せる豪族は大臣や大連などのカバネを持つ豪族だけと決まっていました。それ以降も天皇の妻は皇族から迎えられ、臣下の娘が妃に迎えられたのは、文武天皇に至ってからです。聖武天皇の妃も臣下の娘ですが、これらは皆藤原不比等の娘で、それ以外は内親王を娶っていました。これは天武天皇が伊勢神宮へ斎宮を派遣したことで、祭祀王でもあったキサキの職能が伊勢の斎宮へ移されてしまい、その結果、天皇の妃が跡継ぎを残すという役割に堕してしまい、それなら臣下の娘でもよい、ということになったのが大きな原因であるとされています。それでも目立つのは藤原氏であとは皇別氏族出身だったり、内親王であったりします。
一方でリーダーは雄ですから、王も雄が継承します。当初は、王の妻となる女を出すことのできる氏族(つまり王を出せる氏族)の間で優れた指導者を選んでいたのでしょうが、血筋がだんだんと重視されるようになり(それで身分、位階差をつけていたので当然ですが)、遂にはリーダー「王」も血筋で選ばれるようになったのでしょう。つまり、王の息子であることが次代の王の条件となっていったのです。しかし、母族の力が全く及ばないようになったかというとそうではありません。殷の例でいうと、有力な氏族に産まれた王子たちは兄弟相続で王位を履んでいるのに対し、勢力の弱い族に産まれた王子が王位に就いた場合、そのような例がありません。日本では平安時代に至っても同じ天皇の子供のうち、母族の力が強力で有力な後ろ盾となった皇子を皇太子に選んでいますし、親王宣下を受けたのもそういう皇子です。後ろ盾の貧弱な皇子は、源姓や平姓を与えられ、臣籍に降下しました。閑話休題。
掠奪による『私有婚』と「母系氏族」による身分差は、生産手段が農耕に移っても変わりはありません。掠奪の対象が直接的な食料からその食料を生産する土地に変わりますが、農耕によって余剰な食料が手に入ったとしても、農業には豊凶がありますから、その時に備えて蓄えておかなくてはなりません。つまり、余剰生産物から私有制度が始まることは決してないのです。では私有制度はどのようにして始まったのでしょう。ここで重要なのが「母系」という血筋です。掠奪を繰り返す度集団が大きくなっていったのは自明のことです。肥大した集団を統率するには、リーダーひとりの指導力ではいかに優れていても不可能な局面が必ず来ます。そうなった時、血筋を元にして集団を分け、中間に管理職を置いて末端を統率させると同時に、その行動にある程度フリーハンドを与えるのは当然のこととなります。そうすると、それら小集団単位で農耕や掠奪を営むことが基本になり、集団全体からの恩恵を直接受けることはなくなります。もちろん、もとの集団全体が不測の事態に対応するために必要な食料、財物は納めさせたでしょうが、後は各個独自に行動することになります。第一、そうなった時点で集団と言っても広範囲に散らばっているのですから、現状を追認したという方が妥当でしょうか。それぞれが農耕、掠奪したものは、上納物以外はそれぞれに処分権が下されます。この排他的な処分権が「私有権」の起こりです。それは女を掠奪して占有する『私有婚』が先に有り、「私有」とはどういうものか実例があったので、その排他的な占有権、処分権を生産物や略奪品にも拡大するだけで一般にも理解されたでしょう。古代の私有制度は「氏族制」に基づいていました。ここから更に細分された「家」が誕生し、家父長権をへて、近代の個人主義に基づく、というより個人主義が基づいている「個人私有」に至るには長い歴史があるのですが、それはまた後に語ることにしましょう。
生産手段が農耕に移ると、まるで風物詩のように戦争が起きるようになります。耕作に適した土地は限られていますから、奪い合いになったのです。戦争が激化すればするほど、個人の戦働きが重要になっていき、報償としての女は重要になっていきます。しかし、末端の兵にまで無制限に女の掠奪を許せば、養いきれないほどの数を抱えてしまうことになりかねません。そのため、一夫一婦という原則が立てられたのでしょう。これが末端を制御するための制度であることは、王即ちリーダーや貴族、豪族にはこの制度が適用されず、事実上の一夫多妻であったことからも明らかです。血筋の重視はやがて「家」を産み出しますが、最初は貴族、豪族層から「家」が現れ、闘争の激化とともに、闘争において主権を握る男による父権が拡大していき、家父長制へと至ります。そこでも貴族、豪族においては婚姻は「家」を存続させることが第一義であり、確実に跡継ぎを得るために、複数の妻を持つことが要請されており、庶民の富裕化とその勢力が無視できなくなるまで、一夫一婦制へ移行することはありませんでした。また、仮に庶民の力が強くなっても、「家」制度が重視される場合には、事実上の一夫多妻が維持されました。日本でも、明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)では妻と妾を同等の二等親とすると定められています。後に民法が制定されて、この法律は無効になりましたが、妾が公然と存在する状態は変わりませんでした。
ところで、『私有婚』に転換した集団の信仰はどんなものだったのでしょう。母系が血筋の証となったので、母が信仰の対象となったでしょう。一方で集団を率いる有能なリーダーを欠いては掠奪闘争に勝ち抜けませんから、やはり父も信仰の対象となったでしょう。祖霊といっても、父だけ、母だけでなく、その両方が信仰の対象になったと考えられます。しかし、闘争が激化してくると母系よりもリーダーである父に信仰の比重が傾いていきます。それは現実の闘争において男性の戦闘力が生き残りに極めて重要な要素になっていくからであり、戦闘を指揮するリーダーの能力に勝敗が帰せられるため、その現実が信仰に反映していくからです。そして究極には女性性が否定され、男系のみが信仰されるに至ったと考えられます。恒常的な暴力にさらされる族では女性は庇護される存在であって、族を保護する力がないものとされたと考えられるからです。中国の例では、「商(殷)」は、父母(王と后)とそれに連なる(王と后の)祖霊を敬いましたが、本質的に農耕集団であり、より激烈な闘争を経験していた「周」は、完全な父系制になっていました。敬う祖霊は「父」とそれに連なる男系の祖霊であり、女性は排除されていたのです。激烈な民族闘争を経て誕生した古代ユダヤ教や、その戒律復興を目指したイエスが改革したユダヤ教であった始原キリスト教、砂漠の民の族滅を伴う争いの中で成立したイスラム教、皆唯一神は男性的であり、民族の系譜も男系のみが伝えられています。男系を敬うことは男系を至上のものとする「私権闘争」に付き物の観念であるとも言えます。
一方、原始のヒト集団が、縄文時代の日本のような、外敵が少なく(深い森の中でなければ肉食獣としては狼がいるくらい)、食料が豊富な地域にたどり着いた場合、リーダーに対する不可能課題として主要な「外敵からの安全」と「食の確保」という命題が解除されます。これはどういう変化をヒトにもたらしたでしょうか。
群婚(族内婚)
『群婚』(族内婚)についても、既に「婚姻制度の歴史を考える—③群婚」で取り上げていますが、改めてここでまとめてみましょう。先の項では扱わなかった点についても考えてみたいと思います。
まず第一に、不可能課題の解除に伴い、性をリーダーに固有のものとしていた規範が緩みます。とはいえ、縄文草創期の日本は、まだ生存環境が厳しく、常に移動しながら狩猟や採集を続けなければ食を確保できませんでした。安定的に食を確保できるようになったと目されるのは、竪穴式住居が普及し、定住生活を営んでいたと考えられる縄文早期からです。温暖化が進み、漁業や外洋航行も始まり、明らかにそれまでと異なった氏族の統合の結果と見られる行動が覗えるようになります。この時期の文化圏は、全部で九つとされています。以下、ウィキペディアから引用します。
石狩低地以東の北海道
エゾマツやトドマツといった針葉樹が優勢な地域。トチノキやクリが分布していない点も他地域との大きな違いである。トド、アザラシ、オットセイという寒流系の海獣が豊富であり、それらを捕獲する為の回転式離頭銛が発達した。
北海道西南部および東北北部
石狩低地以東と異なり、植生が落葉樹林帯である。ミズナラ、コナラ、クルミ、クリ、トチノキといった堅果類の採集が盛んに行われた。回転式離頭銛による海獣捕獲も行われたが、カモシカやイノシシなどの陸上のほ乳類の狩猟も行った点に、石狩以東との違いがある。
東北南部
動物性の食料としては陸上のニホンジカ、イノシシ、海からはカツオ、マグロ、サメ、イルカを主に利用した。前2者とは異なり、この文化圏の沖合は暖流が優越する為、寒流系の海獣狩猟は行われなかった。
関東
照葉樹林帯の植物性食料と内湾性の漁労がこの文化圏の特徴で、特に貝塚については日本列島全体の貝塚のうちおよそ6割がこの文化圏のものである。陸上の動物性食料としてはシカとイノシシが中心。海からはハマグリ、アサリを採取した他、スズキやクロダイも多く食した。これらの海産物は内湾で捕獲されるものであり、土器を錘とした網による漁業を行っていた。
北陸
シカ、イノシシ、ツキノワグマが主な狩猟対象であった。植生は落葉広葉樹(トチノキ、ナラ)で、豪雪地帯である為に家屋は大型化した。
東海・甲信
狩猟対象はシカとイノシシで、植生は落葉広葉樹であるが、ヤマノイモやユリの根なども食用とした。打製石斧の使用も特徴の一つである。
北陸・近畿・伊勢湾沿岸・中国・四国・豊前・豊後
狩猟対象はシカとイノシシで、植生は落葉広葉樹に照葉樹(シイ、カシ)も加わる。漁業面では切目石錘(石を加工して作った網用の錘)の使用が特徴であるが、これは関東の土器片による錘の技術が伝播して出現したと考えられている。
九州(豊前・豊後を除く)
狩猟対象はシカとイノシシ。植生は照葉樹林帯。最大の特徴は九州島と朝鮮半島の間に広がる多島海を舞台とした外洋性の漁労活動で、西北九州型結合釣り針や石鋸が特徴的な漁具である。結合釣り針とは複数の部材を縛り合わせた大型の釣り針で、同じ発想のものは古代ポリネシアでも用いられていたが、この文化圏のそれは朝鮮半島東岸のオサンリ型結合釣り針と一部分布域が重なっている。九州南部は縄文早期末に鬼界カルデラの大噴火があり、ほぼ全滅と考えられる壊滅的な被害を受けた。
トカラ列島以南
植生は照葉樹林帯である。動物性タンパク質としてはウミガメやジュゴンを食用とする。珊瑚礁内での漁労も特徴であり、漁具としてはシャコガイやタカラガイなどの貝殻を網漁の錘に用いた。九州文化圏との交流もあった。
縄文時代後期に入ると、これら9つの文化圏のうち、「北海道西南部および東北北部」「東北南部」「関東」「北陸」「東海・甲信」の5つがまとまって単一の文化圏(照葉樹林文化論における「ナラ林文化」)を構成するようになり、また「北陸・近畿・伊勢湾沿岸・中国・四国・豊前・豊後」「九州(豊前・豊後を除く)」がまとまって単一の文化圏(照葉樹林文化論における照葉樹林文化)を構成するようになる。その結果、縄文時代後期・晩期には文化圏の数は4つに減少する。
ウィキペディア『縄文時代』「縄文時代の文化圏」より
「石狩低地以東の北海道」では、植物からの採取が望めず、もっぱら海獣や海洋性の植物(海草)を食べていたと思われます。いずれの海獣も繁殖期にはハーレムを形成するものが多く、その時期の狩りは単独ではなく、集団で実行したと考えられます。それ以外は単独あるいはごく小数で一頭ずつ仕留める狩りを行っていたのかも知れません。
「北海道西南部および東北北部」は堅果類の採取が可能になる植生であり、また陸上哺乳類の狩りも可能な文化圏です。植物は移動しませんので縄張り内部の堅果類の採取は女性や子供、年寄りが担い、狩猟を男性が行っていたでしょう。陸上動物の狩猟は、集団で行い、リーダーの的確な指示とメンバーの機敏な対応が猟の結果に影響しました。植物と動物の死と再生を目の当たりにした人々は、あるいは大地母神を敬うようになっていたかも知れません。
「東北南部」の漁労が、海岸縁では捕獲することができない、カツオやマグロなどに及んでいることに注意して下さい。特にマグロは、数百㎏に達するものも少なくなく、中型から大型の船舶でないと、釣り上げる際に船そのものが転覆してしまいます。また、これらの魚類は黒潮に乗って三陸沖にまで北上してくるので、船をそこまで出さなくてはなりません。従って外洋を航行できる強度を備えていることが必須となります。もちろんそのように大きな船は個人が作るものではなく、集団が総力を集めて建造し、運用していたものでしょう。
「関東」は貝塚が有名です。というと貝ばかり食べていたようなイメージがありますが、そんなはずはなく、貝のむき身を加工して運搬しやすくかつ保存しやすくして交易に用いたのだと考えられます。縄文時代中期には新潟県糸魚川産のヒスイ製勾玉が遠く北海道にまで流通していたことから、非常に広範な交易ネットワークがあったと考えざるを得ず、同時にそれは集団が氏族として組織化されていたことも示します。交易があったということは、言葉が通じたということで、現代の我々からすると何を当たり前なと考えがちですが、江戸時代の侍言葉が方言の違いを吸収するために産まれたものであることからもわかるように、離れた地域の言葉は通じないのが当たり前でした。ましてこの時期、集団の組織化の必要から族の結束を固めていたと考えられますから、ごく近隣にいる自分たちと最近別れた氏族ならともかく、山をひとつふたつ越えた先の集団とは意思疎通が困難なほど言葉が異なっていたとしても不思議ではなく、むしろ当然です。それを媒介し、通訳するものとして、どんな人々が活躍したのでしょうか。また、交易の主体となる集団がばらばらでてんで勝手に交易を行ったとすることは考えにくく、氏族という最小単位の血族集団を統率する部族が産まれ、その指導の下、各地の部族と交易を行ったと考えなければ、広範囲にネットワークが広がりません。そして、その部族内、あるいは場合によっては部族外の者も参加する場として「市」が立てられたでしょう。それは互いの族の祖霊が見守る共通の場でもあり、元来は神の許しを得て物品を交換する神聖な場でもあったと考えられます。
「北陸」の特徴は大型家屋です。これは豪雪地帯なので雪の重みに絶えられる建造物を模索すると必然的にそうなります。また、冬の間は雪のため身動きできませんので、食料の保存技術が発達したでしょう。「東海・甲信」は雪がないため家屋の発達はないものの、植生が「北陸」と似通っており、狩りも同じように行ったと思われます。
「北陸・近畿・伊勢湾沿岸・中国・四国・豊前・豊後」は植生に照葉樹林が混じり、内湾製の漁が盛んに行われました。関東と関西の情報交換が存在したと言うことは、物品の交換も存在したと言うことであり、ここにも交易ネットワークの存在を見ることができます。
「九州」は西北九州型結合釣り針や石鋸が朝鮮半島東岸の釣り針と分布域が一部重なっているという点に注目しなくてはなりません。部族は元より民族も異なるものが同じ道具を使うはずがなく、この重なっている部分は部族が混交している地域と見なせます。後の「倭人」は朝鮮半島南岸にも居住していたことを示す物証と言えましょう。九州南部は縄文早期末に鬼界カルデラの噴火で全滅しますが、そのため、卑彌呼の時代に至ってもさしたる勢力が存在しなかったのです。
「トカラ列島以南」はがらりと様相が変わっているのにお気づきでしょう。もちろん九州と文化圏を接しているわけですから、互いに交流が存在したことは間違いありません。このジュゴンを食べるという話は、後の『梁書』諸夷伝倭國条に「又西南萬里有海人身黑眼白裸而醜其肉美行者或射而食之」「また西南に一万里のところに海人がいる。体は黒く、目が白い。裸でいて容姿は醜いがその肉は旨いという。行く者があればこれを射て食べる」とある言葉を彷彿とさせます。
一方で縄文後期にはこれらの文化圏が四つに収束するというのは、活発な交流が前提にないと考えられません。「北海道西南部および東北北部」「東北南部」「関東」「北陸」「東海・甲信」がまとまったということは、交易ネットワークがこの全体に広がり、人的な交流を含めて相互に影響し合った結果でしょう。部族による氏族の統合と部族間のネットワークが強固になり、あるいは言葉の共通化が進んだかも知れません。「北陸・伊勢湾沿岸・中国・四国」「九州」がまとまってひとつの文化圏になったということも、同じ事が言えます。
ここで着目すべきはその文化圏ごとの独自性もさることながら、集団ごとに狩猟採集を維持していながら定住が行われたことです。その狩猟も集団で行う性質であることは既に述べました。不可能課題を解除された集団において、性をリーダーに独占させる意味はもはやありません。しかし、性欲は男女とも強化されていますので、放置すると無放縦な乱交が始まってしまいます。事実、始まっていたのでしょう。性が個々人の好みのままに営まれるのであれば、族員の間に女を巡って対立が発生することも考えられます。いや確実に発生していたでしょう。これらの問題を解決し、しかも集団=族を強固にまとめなければなりません。狩猟の成果は族の結束にかかっているからです。ところで、この時代の住居の特徴は、中央に広場を置いてその周りを住居が取り囲む形で建造されていることであり、その広場では夜ごと火をたいて祭りを行ったと考えられることです。性を解放しなければならないのであれば、それを以て集団を律するのは必然です。野放図な野合を禁じ、祖霊の祝福がある場と時間に、祖霊の決めた相手と性交することが決められれば、族員も不満は言えなかったでしょう。これを『群婚』といいます。男にとって集団内のすべての女性が伴侶であり、同時に女にとって集団内すべての男性が伴侶です。同時進行の多夫多妻であり、『群婚』と称する所以です。あるいは族の内部で婚姻が完結していることから「族内婚」ともいいます。これを乱婚と呼びあたかも乱交であるかのように言う人がいますが、乱婚と群婚は全く異なるものです。乱婚は無規律、無秩序ですが、群婚は相手が恒常的に定まらないだけであり、集団内の秩序と規律に従って営まれたものだからです。
さて、狩猟で得た獲物が主要なタンパク源であり、場合によってはすべての栄養源であったことから、狩猟におけるリーダーの役割が依然として重視されるものの、族員の果たす役割が飛躍的に増大し、その発言力を無視することは却って集団を破壊しかねない状態に移行していました。族員の要望に応え、神=祖霊のお告げとして皆で性交するようにという指示がリーダーから出されたのは明白です。もちろん族員もそれを喜んで受け入れたでしょう。性交=婚姻の場は、広場での夜の祭りの時だけとは限りません。「歌垣」が入会地や市で行われたように、時には他の氏族や部族の者を交え、祖霊の指示に従って『群婚』が営まれたでしょう。性による交歓は、充足感とともに、族の一員たる自覚を高め、集団が氏族としてまとまっていくのに大きな力があったと思われます。
この「歌垣」が最初『群婚』の儀式であったことは、万葉集にある「鷲の住む、筑波の山の、もはきつの、その津の上に、おどもひて、をとめをとこの、行き集ひ、かがふかがひに、人妻に、我も交はらむ、我が妻に、人も言とへ、この山を、うしはく神の、昔より、いさめぬわざぞ、今日のみは、めぐしもな見そ、事もとがむな」という歌によって窺い知ることができます。この歌の意味は、「筑波山にある裳羽服津の嬥歌う歌垣に、娘と男が集い、歌い踊る。人妻に我も交わろう、我が妻も人と交われ、この山にいます神が古より許す神事ぞ。今日のみは見るのが辛いことも目をつぶれ、何をしても咎めたてなどしてはいかんぞ」ということです。『群婚』が神前集団婚であったこと、その遺風が万葉の時代にあったことがよくわかります。また高群逸枝氏は著書『日本婚姻史』において、
郡内共婚の遺習は、後代では村内共婚としてみられると思う。この種の俗はひじょうに多いが、若干例をあげれば、美濃国郡上郡東村大字祖師野の氏神の秋祭りでは、村じゅうの老若男女が夕刻から神殿にあつまり、太鼓にあわせて輪をつくって乱舞した。それがすむと、人妻と処女の別なく、入り乱れて共婚神事をいとなんだというが、伝統の古さがうかがわれる。
『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第一章 原始時代」「一 族内婚というもの」15頁より
と、『群婚』遺風が伝えられている例を挙げておられます。また、上記の「歌垣」歌を紹介した後、
トツギ祭りというのがある。その多くは大漁とか、豊年とかを祈って行う共婚神事であって、これにはザコネ式や闇まつり式などあり、個別的な好き嫌いをゆるさない共婚性を示しているが、帰着するところは、食と性にたいする共産共有の意識を象徴した原始共同体的な祭りの一種であろうことは疑いない。
大和国磯城郡纒向というところでは、毎年旧正月一〇日に、綱掛神事というのが行われた。田一反分の藁で男根をつくり(これをスサノオ神という)、おなじ分量で女根をつくり(これを稲田姫神という)、神官氏子が立ち合って、トツギ神事を執行したというが、もとは氏子同士がいとなんだものを、男女の性神に委託して象徴化したものであろう。
『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第一章 原始時代」「一 族内婚というもの」15頁〜16頁より
と、若干弱いながらも「群婚」の遺風らしき祭りについて述べらておられます。ただしこれらがいつのことか記されていないのが(纒向の例は執筆当時であろうが)惜しまれます。あるいは、すべて執筆当時のことなのでしょうか。
この『群婚』遺風は、もちろん万葉の時代で途切れてしまったわけではなく、延々と続いて戦後まであったことがわかっています。赤松啓介氏も_『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版_、「Ⅱ 非常民の性民族(ムラとマチ)」「19 泉州機業地の実態」328頁から342頁で触れている通り、盆踊りの後は総出でお楽しみでした。まあ別段赤松氏を担ぎ出さなくてもウィキペディアにだってそれくらいのことは書いてありますね。
ところが、縄文時代の住居跡から出土した人骨の状況などから、当時一夫一婦またはそれに近い生活実態があり、『群婚』はなかったとする説が考古学では流行しているようです。嗚呼、なんと想像力が貧困な人たちなんでしょう。例えば、岩手県二戸市・上里遺跡の例で言うと、男の骨が一体と女性の骨が二体に、子供の骨が一体、縄文時代の住居跡から出土しています。このうち、女性の一体と男性は歯冠測定法を用いた結果、血縁関係があることがわかりました。この二者は、兄妹または姉弟であると見られるので、他の女性と男性が夫婦で子供を産んだのであり、つまり、一夫一婦制だと断定するのです。馬鹿馬鹿しいほど論拠が脆弱な主張で、住居に男女とその子供と思われる骨が出土するのは、住居が子を扶養する目的があり、あるいは男女の性交の場にもなったことまでは言えても、それをもって「家族」と断定するほど固定的な関係であったとは証明できない点を突けばこの論は崩れるのです。もっと言えば、縄文時代のこの時期に「家族」という単位集団が存在したことを証明しないと「家族」などという用語を使用することはできません。しかしながら、彼らは予断を以て「家族」と決めつけるのです。しかも、血縁があるから妻ではないという理由は一体何でしょうか。歴史上、日本人が異母であれば兄弟姉妹であっても結婚したことやオジ・メイでも結婚したことは厳然たる事実です。血縁が近いから婚姻しないという規範は、日本の歴史の中でも室町時代以降、ほんのわずか六百年ほどのことでしかないのです。そんなことも考えられないほど考古学者や歴史学者に頭が悪い人が多いという事実に愕然とします。なぜ我々はこんな知的怠慢を繰り返す学者気取りの衒学者を税金で養わなくてはならないのでしょう。
近親であっても夫婦でないとは言えない。という言い方に引っかかる片がいるかも知れません。『族長婚』では「族長」=リーダーが族内のすべての女と性交しました。その結果、産まれてくる子供は全部同母あるいは異母の兄弟姉妹です。その世代からリーダーが出て、また性を独占するわけですから、人類は近親相姦で増えてきたことになります。本能的忌避感? そんなのあるはずないじゃないですか。これだけ近親の禁婚観が強い現代でも近親相姦に走る者が絶えないことを見れば、本能にそんなものが設定されていないことは容易に分かります。これが『群婚』(族内婚)に移行すると、近親同士で性交しあうんですから、やはり近親相姦です。現代的な意味の夫婦ではありませんが、近親だからこそ夫婦であるとすら言えます。この時期、近親相姦を避けるために男が集団を抜けて他の集団へ参加していく風習があったとする説があるようですが、噴飯物です。豊かだったと言われている縄文時代にあっても、祖霊の祝福と集団の結束なくしては個の生存が保証されない厳しい生存環境下で恒常的にメンバーを集団が放出したと考えることはできません。それは集団の自殺行為です。また、メンバーにおいても祖霊に祝福されない一人旅など死にに行くようなもので、狂気の沙汰です。第一、縄文時代草創期や早期において、他の集団と言葉が通じたとする根拠がありません。むしろ意思疎通に問題があるほど言葉が異なっていたと考えるのが自然です。信仰も違う、言葉も違う、にも関わらず恒常的に男はハグレザルならぬハグレヒトになってさ迷う? ありえません。おそらくサルの行動様式から類推したのでしょうが、サルの行動様式をヒトに当てはめようとすること自体が間違っています。
近親相姦の弊害として、劣性遺伝子の発現が挙げられます。この劣性遺伝子には致死遺伝子も含まれており、また様々な遺伝子由来の疾病もここに隠れています。運悪くそのような致命的な欠陥が子供に現れた族は淘汰され、滅んでいったでしょう。また、外部の血が全く集団に入らなかったかというとそんなことも考えられません。偶にある意味無鉄砲な、別の言い方をすれば好奇心旺盛な若い男が集団を飛び出すことはあったでしょう。そのような男の中で独力で生き抜くことに成功し、別の集団に迎えられた者もあったはずです。当時、ただ一人で生き残り、旅を続けてきたことはそれだけで英雄的行動です。古来、非常に稀であるが遠方から旅を続けてきたお客さん、つまり客人(まろうど)を神聖な者とし、女性を侍らすのはその強い血を取り込むためです。それは縄文時代から続いた風習ではないかと思います。ただし、客人とはまた稀人である通り、そんな男は滅多にいませんでした。
ところでもちろん、『族長婚』から『群婚』へ一時に移行したはずはありません。最も大きな契機は「定住」であったことは想像に難くありませんが、リーダーが族をまとめきれず分裂してしまった族もあれば、内訌が起きて分裂した族もあるでしょう。中には滅んだ族もあると思います。しかし、歴史が途切れることなく続いていることを考えれば、多くは首尾良くこの移行を果たしたのです。縄文時代草創期末から早期にかけてこの移行は行われたでしょう。その遺風は長く、本当に長く、一万年に渡って残り続けました。私は『群婚』を以て日本人の原風景の一つと断定してよいと考えます。それほどの長きにわたる残照でした。
『族長婚』にせよ『群婚』(族内婚)にせよ「血筋」が問題になることはありません。なぜなら、生活を共にする集団の構成員全員が同じ血筋を持っているからです。従って身分差や貧富の差などできようはずもなく、人々は比較的穏やかに暮らしていたのではないでしょうか(平和にと言わないところがポイントです(笑))。しかしそのような時間は瞬く間に過ぎていきます。『群婚』によって集団の結束を固めていた縄文人にも新たな時代の波が押し寄せていくのです。それは人口の増加による人口密度の向上と、それによって族の縄張りが互いに接するようになってくることから生じる緊張です。それを縄文人はどのように解決したのでしょう。
族外婚は?
ここで少し脱線します。日本で縄文時代に見られた『群婚』を『族内婚』ともいうと述べました。ということは『族外婚』というものもあることになります。『族外婚』は、集団の男性の妻を別の特定の他集団に求める婚姻で、その集団の女性全員が妻になります。これは逆も同じで、集団の女性たちは他集団から男たちを夫として受け入れます。多夫多妻であり、それも同時的に行われることから、やはりこれも『群婚』です。ただし、他集団といっても全く関係のない族と婚姻通交するという話ではなくて、多数の氏族からなる「部族」内の協調と調和をはかるために、氏族と氏族の間で取り決められる相対集団婚です。言ってみれば、「○○家」の本家と分家の間で婚姻するようなもので、世間から見たら「○○家」とひとくくりにされるような集団の内部で、多数の分家や別家があってその分家や別家同士で婚姻するようなイメージでしょうか。そういう意味では「部族内婚」であり、全く無関係な外部の族との婚姻があったわけではありません。これは逆にそういった氏族を統率する部族や宗族といった大きな単位組織が成立することが前提になっています。日本ではこの例が見られないのですが、外国にはその例があります。
中国最古の辞書である「爾雅」には釈親の項に、昭穆という基準があり、古来これは難解とされてきました。高群逸枝氏は著書『日本婚姻史』至文堂、昭和38年5月30日初版「第一章 原始時代」「二 族外婚というもの」30頁〜34頁においてこれを論じられており、上古、周の昭族と穆族で行われた「族外婚」の結果、生じる縁戚関係を説明したものと解かれました。けだし卓見というべきでしょう。中国父系主義の源流となった周の族もさらに遡れば「族外婚」を行っていた時期があったのです。春秋時代、葬儀の喪主は死者の孫が勤めると決まっていました。これも父と子が異族であった頃の名残でしょう。
家族史、婚姻史といえば必ず名前が挙がる「モルガン」の『古代社会』では、婚姻の歴史を、乱婚→血族婚→プナルア婚→対偶婚、としています。乱婚は即ち『群婚』ですが、血族婚は同じ血族の中で同世代の兄弟姉妹を含む男女が婚姻を結ぶ(世代の異なる血族は婚姻しない)ことを指します。プナルア婚とは、血族婚に加えて兄弟姉妹での婚姻を禁じたものを指します(本概説でいう『族外婚』に近いがやはり異世代間の婚姻は禁止)。対偶婚は、一対一の男女関係を基本にしつつも性的関係を他と結ぶことを排除しない婚姻です。もちろん彼はこれを机上で創造したわけではなく、世界各地の親族名称から分析したのですが、今でもこれが通用していることに驚きます。血族婚にせよ、プナルア婚にせよ、形態が『群婚』であることが今では明らかになっており、本来ならまったく制約がなかった『群婚』からこのような制約を伴った婚姻制度が生まれた原因を探求し発表して貰いたいものですが…仮にそういうことをした人がいたとしても一般的ではないようです。結局、「モルガン」の説は様々な変遷の後、現在は否定されています。しかし、『群婚』から対偶婚へ移行した族がいないという意味での否定ではなく、「モルガン」の提示した婚姻の進化形態が否定されたのでした。彼の進歩史観もまたいわれなき白人優位を自明に考えており、人類社会の発展を「野蛮」「未開」「文明」に三分できるという粗雑な説であり、しかも彼が依拠したインディアン社会のことなど彼が全く理解していなかったことが明らかになっており、今でも彼の説に依拠して婚姻史を説明しようとする人がいるのが不思議なくらいです。
『女性史研究 第4集』家族史研究会、1977年5月25日発行、の2頁から26頁において、石原通子氏は「族内婚と族外婚 —高群逸枝氏の場合—」と題する論文を発表し、高群逸枝氏の「族内婚」と「族外婚」の取り扱い方を「モルガン」の『古代社会』を引きながら批判されているのですが、惜しいかな、『族外婚』自体が日本に見られないとする本質的な批判に至っていません。「モルガン」の『古代社会』のへの批判は最近のことで当時はなかったのでしょうか。そんなことはありません。既に20世紀冒頭の段階で「モルガン」の説は徹底的な批判にさらされていたのです。不思議ですね。
高群逸枝氏も最初は「モルガン」に準拠して婚姻史を想定していましたが、おそらく「モルガン」に対する批判を知ったのでしょう。『日本婚姻史』ではまったく触れなくなっています。ところでその高群逸枝氏ですが、クナドの神を引き合いに出して「族外婚」の典拠とする苦しい説を展開しています。
まず、氏は以下のように指摘した後、
昭和三〇年に発掘された横浜市鶴見川流域の南堀貝塚(縄文前期)の住居跡をみると。この住居跡は、谷にかこまれた約五,〇〇〇平方メートルの台地の上に南西に馬テイ形にひろがっていたが、貝層は台地の北側急斜面にあり、だから貝のゴミ捨て場を一所につくっていたことがわかった。これらの事実から、これは統制された一集団(平均一〇戸ほどの竪穴住居からなる)の跡であろうと推定されたが、とくに私には、台地の中央に大きな石皿をかまえた広場があり、それに接近して直系二メートルもある「非たき場」と、さらにそれをめぐってセンベイをふみつぶしたように一面に散乱した土器のカケラがあったことが興味ふかく、そこで私は、これは族内婚から族外婚への過渡期にある群の跡で、火たき場のあたりは共食の場、広場は婚姻と舞踊の場所ではないかと想像した。
『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第一章 原始時代」「一 族内婚というもの」17頁より
次のように説明しています。
ところが日本では、二群単位とはかぎらず、二群でも三群でもが集落をなし、その中央に祭祀施設のあるヒロバをもち、そこをクナド(神前の公開婚所)とし、集落の全男女が相あつまって共婚行事をもつことによって、族外婚段階を経過したと考えられる(「日本歴史」一(昭和三七年)坪井清足「縄文文化論」によると、長野県与助尾根遺跡は東西二群に分かれた興味ふかい集落構成のようである)。
縄文中期以後の集落遺跡が環状型や馬テイ型をなし、中央にヒロバをもつことを特徴としているという最近の研究結果は、右の婚姻制を裏書きするものと思う。そのヒロバには祭壇の設けがあり、母性土偶とともに石棒がみられる点は、クナドの神といわれる能登の道祖神につながるものと考えるときに興味ふかいものがある。 『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第一章 原始時代」「二 族外婚というもの」21頁より_
また、
これらを考えると、クナドの神なるものは、数カ所村共有のヒロバや、入会山や、交通の要衝(いわゆるヤチマタや物々交換の市場)や、村の入り口に祭ってある石神であるが、その性格は一面が交通の神、他面が性の神という複雑さを持っている。
交通の神が性の神でもあるというのは、族外婚段階のヒロバのクナドを考えればわかろう。クナドは文字通り神前共婚の場所であるが、またそのことによって他群と交通し、結びつくことになる場所でもある。原始時代では性交は同族化を意味する。排他的な異族の間では性の交歓だけが(ときには性器のみせあいだけでも)和平への道であり、理解への道であり、村つくり、国つくりの道でもあった。大国主神の国つくり神話が、同時に妻問い神話になっているのも、この理由にほかならない。
『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第一章 原始時代」「二 族外婚というもの」22頁より
これらの論考は結局、氏が「モルガン」の、婚姻は血族婚から徐々に遠ざかるという婚姻史観を脱しきれなかったことを表し、日本の婚姻史に画期をもたらしながら、ついに前時代的な措定に留まざるを得なかった限界を表したものであると考えます。なぜならそのような「ヒロバ」の存在はそこを『族内婚』の場としてもまったく矛盾なく説明できるばかりでなく、他族との交渉、和平的な共存は、『妻問婚』でも可能だからです。特定の他族との集団婚を経なければならない理由が日本にはありません。さらに、
猿田彦神話では、国境のヤチマタに、異国人の猿田彦が立ちはだかっていると、ウズメという女神が乳房と陰部を露出してこれに立ち向かい、両者唱和して交通がひらけたとある。だから猿田彦は交通の神でも性の神でもあることになり、ウズメは雄取式舞踊(カグラ踊り)の祖神ということになった。
『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第一章 原始時代」「二 族外婚というもの」23頁より
とあるに至っては、この説話のどこに『族外婚』が成立する余地があるのか、氏は説明していません。これも、族長同士の『妻問婚』でも説明できる説話なのです。
日本に『族外婚』がなかったことは、またその遺制がどこにも存在しないことによって裏付けられます。『族外婚』は必然的に「族内」での禁婚を伴います。結婚相手は他所にいるのですから当然ですね。ところが日本にはそのような制度があったことを窺わせる遺制も説話すらも存在しないのです。婚姻史的には、その前段階とされる『族内婚』の遺制は現代まで生き残っていたことは既に述べましたが、『族外婚』が日本にあったとすれば、これもまた残っていなくてはおかしいのですが、欠片もそれを窺わせる事実が残っていません。日本は『族外婚』を経ず、一足飛びに次の段階へ移ってしまったのです。
妻問婚
気候が温暖化し、植生が豊かになり、また海産物や狩りをする対象(シカ、イノシシ)に困らないとなれば、人々が流入してくるばかりでなく、出生して死なずに生き残る子供も増え、自然、人口も増えます。同じ祖の血を分け持つ氏族が部族として統合されていく中で、族と族の縄張りの境界が接して、だんだん過密状態になっていきます。自然、他の族と交渉を持たねばならない場面が登場し、言葉の問題が解決していきます。もちろん対立もあったでしょうが、それで戦争にはならなかったのでしょう。縄文時代の人骨には戦闘でついたと見られる傷がありません。緊張を保ちながら、共存を選択した賢明な祖先に敬意を表しようではありませんか。
ところで、日本人の特性として「和を以て尊しとなす」「ねばり強い」「上の言うことに唯々諾々として従う」「世間を過剰に気にする」といった内容が挙げられ、農耕を基盤としたムラ社会の伝統によるものだなどとまことしやかに嘘を吐く言論人がいますが、これら日本人の特性と言われている項目はすべて狩猟採集民族に強く見られる特徴なのです。日本で言うと縄文人です。農耕民族はそこまでお人好しではありません。むしろ過剰なくらい好戦的です。中国で殷周革命と称する、農耕民族である周が、商(殷)を滅ぼした行為を、周は天命による革命と盛んに自己宣伝しましたが、逆に言うと派手な自己宣伝が必要なほど強引に商(殷)の天下を簒奪したのです。商(殷)の紂王は敗れましたが、周はその子、武庚禄父を諸侯に封じたり、武庚禄父が背いたらこれを討ってかわりにやはり紂王の異母兄である微子を宋に封じたりしています。商(殷)の氏族を完全に滅ぼすことは、実力的にもできなかったし、またそれを諸侯が許さなかったのでしょう。実際、革命が非常に強引であったがゆえに西周時代はゴタゴタ続きであり、終に周は自滅してしまいます。このあたりの顛末は、司馬遷の『史記』周本紀に詳しく書かれています。また、農民が好戦的という事例は日本でも顕著に見られます。赤松啓介氏が自身で経験した旱魃における水騒動を『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』で詳しく説明されています。
この「水騒動」の実戦部隊の主力となるのが、すなわち「若衆組」なのだ。用水源を防衛したり、あわよくば他のムラの用水であろうと掠奪して、一合の水でも欲しい。血の一滴よりも、水の一滴が役に立つ。したがって水騒動、水喧嘩の乱闘では負傷者も出るし、ときには死者もあって、それほど激烈な抗争になる。いわば戦争状態であるから、なかなか他所者は立ち寄れない。スパイなどに疑われると、袋だたきにされる。
『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』赤松啓介、明石書店、1986年7月20日初版 「Ⅱ 非常民の民俗文化」「10 炊き出し作業の機構」134頁より
いずれにせよ、農耕民族は極めて好戦的なのであり、日本人の特性と言われているものは、農耕が入ってくる前の縄文時代に培われたものだということをおわかり頂けたでしょうか。閑話休題。
さて、この時期に『妻問婚』が始まったとする根拠は以下の通りです。
- 既に大規模集落が営まれており、集団が大規模化していたこと。
- 勾玉の交易から明らかなように他集団との交流が活発であったこと。
- (同一血族を示すと思われる)抜歯の風習が始まったこと
族の大規模化は縄張りの拡張が不可欠で、これを以て近隣の族と縄張りが接するようになったと考えられます。平和的な交渉で縄張りが決まった例もあれば、対立関係に陥った例もあったでしょう。対立は集団に緊張をもたらします。互いに侵略するわけではありませんが、ことは「食」に関わることなので、一度対立が発生するとその緊張はなかなか解除されません。また、交易ネットワークが発達するには、これを仲介する場が必要です。それが「市」なのですが、当然祖霊の加護を受けていない地においそれと人を派遣することはできません。まずは道を清め。祖霊を祭り、以て祖霊の加護と監視があるようにしたのではないでしょうか。抜歯の理由については様々な説が横行していますが、これといって決定打はありません。が、健康な歯を抜いてその欠けているところを見て所属の族を示したのではないでしょうか。
族と族の緊張がいつまでも続くのは外交上問題です。そこで性を使ってこれを解決しようとする動きが出てきます。それが『妻問婚』です。縄文時代中期になると交易ネットワークが形成されるのですが、これを為す原動力として、婚姻の力があったと考えています。ここで「族外婚」に移行しなかったのは、対象集団が一意に定められなかったこと、つまり、縄張りを接するのは一集団ではなく、多数の集団しかも部族も異なる集団が含まれているためだったと考えられ、外交上どこかを特別扱いするのは得策ではなったからではないかと思います。また、交易のためには「市」を設け、あるいは他族の設けた「市」に出向かねばなりませんが、全員で「市」にかかりきりになることはまずありえず、誰かが代表として十数人くらいを伴って出かけたでしょう。そしてそのままその地で婚姻してくれれば、通交範囲が広がり、それだけ周囲との緊張が和らぐかもしれません。さらに境を接する族にしても、実際にその族の者と接するのは、狩猟のために出かけていく男たちです。その男たちが狩猟地からさらに侵入して婚姻してくれれば、族と族の間の緊張も和らいだことでしょう。
『妻問婚』は「婚姻制度の歴史を考える—④妻問婚」および「婚姻制度の歴史を考える—⑤妻問婚補記」でも記述したように、女の元に他族の男が夜ごと通ってセックスをし、子供をもうける婚姻形態です。子供は母の族で育てられ、男の族はその養育に一切関知しません。その始まりも、男が女性に求婚し、それを女性が承諾すれば即結婚です。結婚式などという仰々しいものはありません。子供が母親の族で育てられることから、母系制がここでも始まったと考えられます。当初、子は母の族で産まれ、母の族に育ち、母の族で生活し、母の族で死んでいったでしょう。つまり、完全な母系制社会が現れたと考えています。
少し脇道にそれますが、血筋や資産の継承が母系制で始まったことについて詳しく考えてみます。実は人類が継承制度を初めて打ち立てたとき、母系制であったか父系制であったか、また母権制であったか父権制であったか、確定した学説はありません。それを証明する決定的な遺物がないからです。しかし、少なくともかなり早い時期に母系制を経ていることは、各地の神話に地母神の信仰が見られることから推測できます。例えば最古の文明と言われるメソポタミアのシュメール神話におけるナンム、イナンナ/イシュタル、それを引き継いだアッカド文明におけるバビロニア神話のティアマトも母なる神です。中国の神話に登場する女媧も人類を生み出した母なる女神です。元々苗族が信仰していたこの女神を後に伏羲とのペアに改変したものが今に伝わっている伝説らしいと言われています。かつてユダヤ人が侵入してくるまでカナンで信仰されていたのもアシュトレト、フェニキアのアスタルテも地母神です。ギリシャ神話にもガイアという地母神が登場します。あるいは北欧においても同様で、インドでも初期のヴェーダ文化から地母神への信仰が存在すると考えれています。ケルト神話でもダヌという古い女神が存在します。詳しく知りたい方は、ウィキペディアををご覧下さい。日本においても皇室の祖先とされているのは天照大神という女神です。(天照大神は元々男神だったのが古事記編纂段階で女神へと改変されたという説があります。確かに太陽神信仰において太陽は男神に仮託されることが多いのです。また、天の岩戸に隠れた天照大神の気を引くためにアメノウズメがストリップをして他の神々と騒いだというのも男神でなければ意味が通りません。しかしこれが正しいとしたら、にも関わらず、男神から女神へと改変されたという事実こそが問題となります。元々天照大神を信仰していた集団を別の集団が取り込んだ際に自分たちの母神信仰に適合させるために改変が行われたという推測が一応は可能ですが、祖が母神でなくてはならない理由とは何だったのでしょう)
『族外婚は?』でも触れた「爾雅」の釈親条にある昭穆関係は、子が母族で扶養されていたことを表していることも明らかになっています。周は商(殷)を倒した王朝ですが、その商(殷)は、王位が男性に伝えられたのは間違いないものの、亀甲獣骨文字の解読から、世襲はしないのが基本で、実子相続が行われた場合もある、といった王制であったことが判明しています。商(殷)は氏族共同体の連合体であり、商(殷)王室には少なくとも二つ以上の王族(氏族)が存在していました。松丸道雄氏の仮説によると、商(殷)王室は十の王族(「甲」~「癸」は王族名と解釈)からなり、不規則ではありますが、原則として「甲」「乙」「丙」「丁」の四つの氏族の間で、定期的に王を交替していたとしています(「丙」は早い時期に消滅している)。それ以外の「戊」「己」「庚」「辛」「壬」「癸」は臨時の中継ぎの王を出す王族で、王妃も出していたとされています。あるいは、商(殷)の王族は自分たちを太陽の末裔と信じており、『山海経』の伝える十個の太陽の神話は、商(殷)王朝が十の王族の間で王位を交替する制度を表していて、羿(げい)により九個の太陽が射落されるのは、一つの氏族に権力が集中し強大化したことを反映したものとする解釈もあります。それはさておき、商(殷)の王族はその地位や財産を母系継承で伝えていたのであり、周の武王が「牝鶏(ひんけい)晨(あした)す」と言って非難したのは、商(殷)では女性の地位が高く、その卜占を支配していたことを示すもので、まさしく父権母系制であったと考えられるのです。
原始、ヒトが性交と出産の関係を理解するまで、親といえば母親を意味したのは当然ですが、日本ではこれが長く続いたと考えられます。『万葉集』で父を単独で歌ったものはわずか一首(巻二十4341「橘の美袁利の里に父を置きて道の長道は行きかてのかも」)に過ぎません。ところが母を単独で歌った歌はたくさんあるのです。これはつまり、かつて父が親の範疇になかったことを表しています。このことはまた国語学的にも確認されています。古代日本ではそもそも、子供が兄弟姉妹を指していう言葉(イロセ・イモセ)と実母を指して言う言葉(イモセ)はあっても実父を指す言葉がなかったのです。言葉がないのは実父というものが認識されていなかったからで、これも母系を支持する有力な根拠となります。加えて、古代日本独特の禁婚観念があります。日本では実母子および同母の兄弟姉妹の婚姻が禁止されていただけで、他に禁婚とするものはありませんでした。これは父系が同族、今日で言う親戚という感覚がなく、他人同然であったことを示しています。そのような婚姻感を支えうる制度は、やはり母系制以外考えられません。
話を『妻問婚』に戻します。おそらく『群婚』から『妻問婚』へ変化する流れは、縄文時代中期からゆっくりと始まったでしょう。族と族の緊張を緩和し、時には族長自身が妻問いを行うことで、族に平穏をもたらしたでしょう。「市」には多くの族が出入りするので「歌垣」が設けられたのは必然です。族と族が接する入会山などでも「歌垣」は行われました。いずれも祖霊が見守る中で行われた神事であり、最初は、相手の部族を招いて共に『群婚』を営んだのでしょうが、そもそも招かれる方、あるいは招く方は「市」なり「交渉」などでやってきた男を見初めて招き招かれるのであって、やがて女性の側から不満が起きたと思われます。つまり、あの人がいい!って言ってるのに、ちっとも当たらないじゃない!ということです。狩猟採集社会では女性はただ庇護されている脆弱な存在ではありません。食の大半を賄っているのは彼女たちなのです。しかも性を支配していますから発言力は並ではありません。故に「歌垣」においても対偶が基本になっていったのでしょう。性の交歓が『群婚』では族の一体感を高めるのに役立たされたのと同じく、『妻問婚』で通ってくる男も族と族の紐帯を固める役割を担ったでしょう。
『妻問婚』は、「歌垣」で女性に求婚し、それを女性が承諾すれば、女性の元に通っていって性交=婚姻するのが、元来は正式な形でした。「歌垣」で審判を下すのは互いの族の祖霊であり、神々です。『日本書紀』の武烈天皇紀に、皇太子時代の武烈天皇が物部麁鹿火(もののべのあらかい)の娘、影姫を見初めたところ、海石榴市の歌垣で求婚して欲しいと影姫が答え、その歌垣で平群鮪(へぐりのしび)と闘歌で競っている間に、影姫と鮪が既にただならぬ関係にあることを歌から悟り、激怒して兵に鮪を追わせて誅殺してしまう話があります。この海石榴市の歌垣で求婚して欲しいという要望は、それが正式の求婚であったからであり、闘歌の審判は神の裁きでもあったからです。
しかし時代が下ると、後にヨバヒと言って、夜忍んでいって女性に声をかける、求婚歌を謡う、文を届けると様々に便宜な方法へ移行していきました。これは『群婚』が神前集団婚であり、婚主が「祖霊=神」であったのに対して、族の外交や交易の都合から、族の意思、あるいは方便が神意より優先されるようになった結果、神前での婚約という形で祖霊の加護を期待しながらも、婚主が集団の長(オヤ)へと移行したことによります。それは事後的承認であったとしても婚姻が人の手に移った確かな証であり、また当事者の意思が優先されたことは、充分に共同体的な措置であったと思います。
ところで繰り返しになりますが、この時、通ってくる男の身分証明となったのが、「抜歯」ではないでしょうか。というのも、九州には入れ墨をする部族がいましたが、抜歯をしていた形跡がないのです。これは入れ墨の形が属する族を表していたので、ことさら歯を抜く必要を感じなかったからでしょう。実際、九州で抜歯のあとがある人骨は少ないことが報告されています。尤も抜歯が所属する族を表すというのは異論も多く、確定した説ではありません。いずれにせよ、どこの誰かがわからないと婚姻を族長層(オヤ)に報告できないのですから、何らかの手段で相手の所属する族を知ったものと思われます。これは同時に、集団内に他集団の男が入ってくることになりますから、族としてもどこの何者であるかは是非とも明らかにしておかなくてはならない点だったでしょう。この時、この通いの男は、妻方の族からはどのように見られていたのでしょうか。完全な同族ではない。それは食を共にしていないからです。しかし完全に他人でもない。なぜなら自族の娘と性交しているからです。身内と他人の中間という、何とも曖昧なところにいたものと思われます。
女の元に男が通うと言うことは、日ごとに通う先を変えることができるということにもなります。つまり、一夫多妻の男も少なくなかったでしょう。尤も、多くは一夫一婦だったと思われます。ツマドイモノといって婿が妻の家に行くときに手土産を持参する習慣があったのですが、あっちもこっちもとなると中々手が回りません。それにこの時期はまだ『群婚』が併存していたと考えられます。『群婚』において「あぶれる」男は存在し得ません。必ず誰かにあたるのが『群婚』です。これに対して「対偶婚」である『妻問婚』は、相手の女性の承諾が必要です。現代でも恋愛下手が多数派であるように、当時も女性をその気にさせることは一般の男性にはなかなか難しかったのではないでしょうか。しかし一夫一婦であるからといって今日的な制度を想定すると誤りを犯します。『妻問婚』は自由意思に基づく結びつきであり、「床去り(とこさり)」「夜離れ(よがれ)」といっていつとはなしに男が通ってこなくなって、自然、離婚していたというひどく曖昧な婚姻形態でもあります。もちろん女の方から来た男を返す(入れない)ことによって離婚が示されることもありました。そう言う意味ではチャンスはいつでも誰にでもある婚姻形態でもあります。
この時期の日本は『漢書』にちらりと出てきます。地理志燕地条にある「樂浪海中有倭人分爲百餘國以歳時來獻見云」という下りです。多数の氏族を統合する部族が成立し、それらが共存している姿が見えます。「以歳時來獻見云」とあるのですから、力のある部族あるいは、いくつかの部族が連合して周あるいは燕に毎年朝貢していたのです。海の彼方に大国の周があり、天子が治めているという事実は、商(殷)の遺民が伝えたのでしょうか。何を期待して周に朝貢したのでしょう。あるいは渡来人自らが代表して朝貢し、冊封を受けることで自族の地盤を固めたとも考えられます。いずれにせよ、日本に住む人々の目がようやく海外へ向き始めたことを示す貴重な資料です。
禁婚観はどうだったでしょうか。明確な身分制度も私有財産制度もなく、『群婚』も併存している以上、強いて禁婚というほどのものはなかったと考えられます。あるいは、場合によっては『妻問婚』により母系の血筋が明確になるため、実母子の禁婚が成立したかも知れません。しかし、それ以上は決してなかったと断言できます。『群婚』で近親との性交を禁止してしまったら相手がいなくなります。ただ、妻問いは通常他所に出向いてするものと観念されてはいたはずです。でないと意味がないですから。族内で妻問いはしないという意味では『妻問婚』においては禁婚になりますが、『群婚』が続く限り、禁婚観念として意味のある観念ではなかったでしょう。
さて、農耕と共に戦争が日本へ入ってきます。戦死と思しき人骨も発掘されています。時代は縄文時代晩期から弥生時代にかけて。戦争と暴力の風がとうとう日本に届いたのです。これは婚姻風俗に影響を与えたでしょうか。結論から言うと、「妻問い」の風は変わりませんでした。戦争の時代とは言っても戦闘しているばかりではありません。当然利害を共にする部族同士が同盟を組んで後顧の憂いをなからしめたり、戦闘へ至らずに妥結できないか交渉を繰り返したりしたでしょう。特に同盟では部族長の婚姻が積極的に利用されたでしょう。身内ではないけど他人でもないという立ち位置は、同盟に大変都合の良いポジションです。完全な身内であれば後から状況が変化しても離れることができません。完全な他人でしたら、そもそも同盟の意味がありません。そして、「妻問い」は戦争で敗北した族を支配する際にも行われたでしょう。祖霊は奪われ、戦争に勝利した部族の祖霊=神に従属、奉仕する神へ作り替えられ、部族長に連なる娘と婚姻を結ぶことを通じて、その支配を正当化したでしょう。子が産まれれば、当然その子を負けた部族の長に推したに相違ありません。和平と交易が産みだした『妻問婚』は、戦争の時代にも有効でした。
しかし、すべての部族が『妻問婚』に留まったのでしょうか。縄文時代から弥生時代にかけて、渡来人の大量移入の波が何度もあったことが考えられます。
紀元前一二世紀頃?
商(殷)の高宗武丁王が江南を侵略し、支配下に置いています。これを避けて日本に逃げ延びた人々がいたと考えられます。その中にはミャオ族の人々がいたかも知れません。
紀元前1067年
商(殷)が滅び、周が王朝を開きました。商(殷)と誼を通じていた部族には、日本へ逃げた部族があったでしょう。この時、商(殷)の習俗、卜占などが持ち込まれたと思われます。
紀元前473年
越が呉を滅ぼしました。後に「倭國」の中核をなすと思われる呉の部族が脱出し、日本を目指しました。
紀元前334年
楚が越を滅ぼしました。鯨面文身の習俗を持った越の部族が日本へ脱出したと思われます。
紀元前221年
楚が滅び、燕が滅び、斉が滅んで、秦により中国は統一されました。
紀元前206年〜202年
西暦8年〜25年
西暦184年〜
黄巾の乱が起こり、乱が終結した後は群雄割拠の状態で、間もなく三国志の時代に突入します。
これらの渡来人は当然自族の風俗を日本へ伝えたでしょう。骨卜(こつぼく、獣の肩甲骨や大腿骨などを焼いて生じるひび割れで吉凶を占う方法。極めて古い、原始的な卜占の方法)、盟神探湯(くがたち、相争う二者を神前で対決させ、沸騰した湯の中に手を入れて何ともなければ正、手が爛れれば邪とした判定法。実際は神前で自分が正しいことを誓う時に、神を恐れた不正な者は手を入れるまでもなく白状した)など、極めて古い中国の習俗が日本に伝わり、後代まで保存されています。そうであるならばまた、彼らが定着した地域に他の風俗も持ち込まれたと考えられます。では、婚姻はどうでしょうか。最も基本的な風俗であり、その意味では変わりにくいのが婚姻風俗です。この時期、婚姻風俗が大きく変わったことを示す考古学上あるいは歴史学上の証拠は発見されていません。つまり、婚姻風俗を変えてしまうほどの人口移入ではなかったことがわかります。しかし、中国の家父長制に基づく嫁取婚が族とともに持ち込まれなかったはずはありません。しかし婚姻は相手があることですから、婚姻先が承知しない婚姻形式は残りません。あるいは後の「倭」國を形作ることになる部族の支配階級は、その風習を伝えたかも知れません。しかし、それを全土、全階層に波及させることはできなかったと断定できます。
農耕が持ち込んだのは戦争だけではありませんでした。人民支配を正当化する「身分」というものも持ち込んだのです。戦争とはつまるところ、大規模な掠奪です。農耕が始まると、持ち歩くことができずしかし生産には不可欠の「土地」を巡り、またその土地に供給する「水」を巡り、争いが起こるのは必然です。奪われれば明日からの活計がなくなるので、守る方も必死です。奪う方は土地がないと食料を生産できないのですからこちらも必死です。平和的な解決の余地はなかなかなく、暴力が暴力を呼ぶ時代に突入し、人々は自分たちの安全と土地の庇護を一生懸命祖霊や他の霊に祈ったでしょう。形や規模の大小がどうあれ掠奪が起きれば、それに付随する現象がすべて起きるのは自明の理です。『私有婚』で説明した現象が、縄文時代晩期から弥生時代にかけて日本でも起きたことは間違いありません。「身分」が生じた結果と説明される「墳丘墓」が弥生時代から建造されるようになっていきます。もちろん、何もかにもが一時に起きたわけでなく、少しずつ「国家」を目指して闘争が繰り広げられた時代だったのです。
争い続けていればいずれ勝者が決定されます。負けた部族は勝った部族に従属し、広い領域を支配する国家が誕生したでしょう。そしてその事実は(書かれたのは200年以上経ってからですが)『後漢書』東夷傳にある倭國条で知ることができます。「建武中元二年倭奴國奉貢朝賀使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬安帝永初元年倭國王帥升等獻生口百六十人願請見」「建武中元二年(西暦57年)、倭奴国が貢ぎ物を奉り、朝賀に来た。遣使は大夫を自称した。(倭奴国は)倭国の最南端にある。光武帝は印を授けさせた。安帝永初元年(西暦107年)、倭国の王たち帥升その他がやって来て、生口(奴隷)160人を献上の上、お目見えすることを願った」。光武帝が下賜した印が志賀島から出土した金印、漢委奴国王印であることは大変有名で、歴史にあまり詳しくない人でも知っているでしょう。このことから、一世紀には国と呼びうる形が出来上がっていたことがわかります。後漢建国から三十二年も経ってから「倭奴國」が朝貢したのは、その頃建国されたからだと考えるしかありません。前漢の滅亡から後漢建国まで戦乱が続いた中国から、かなり大勢の渡来人が日本にやってきたのだと思われます。部族組織が「国」へと成長したのはその人たちの関わりなしにはありえなかったのではないでしょうか。
ところで、これに呼応するかの如く、瀬戸内海や大阪湾岸に高地性集落が見られるようになります。これは紀元一世紀から二世紀にかけてのことで、三世紀に入ると高地性集落は近畿とその周辺部に限られるようになります。この高地性集落の分布は何を表しているのでしょうか。集落遺跡の多くは平地や海を広く展望できる高い位置にあり西方からの進入に備えたものであり、焼け土を伴うことが多いことから、のろしの跡と推定されています。つまり、西方、九州北部から中部にかけて「倭」國が成立したのと期を合わせるように出現していることを考えれば、高地性集落が「倭」國への警戒であることがわかります。なので、北九州にはあまり見られないのです。一世紀から二世紀の間に瀬戸内も平定されて、「倭」国の勢力が及んだのかも知れません。あるいは後に見られる「吉備政権」が瀬戸内をまとめたのかも知れません。この勢力はじりじりと西進し、遂には播磨国まで到達したと思われます。ただ、部族の安全のために戦争になる前に敢えて強大な部族に降り、服属したところもあったでしょうし、強大で勝っているからといって自族の男がすり切れるまで戦い続けるのも問題です。全部が全部、戦闘の結果というほど古代の人々が頑迷であったとは思えません。
一方で、国家を樹立したとはいえ、九州も決して安定したわけではありませんでした。その様子を、大変有名な『魏志倭人伝』で知ることができます。「倭人在帶方東南大海之中依山島爲國邑舊百餘國漢時有朝見者今使譯所通三十國」「倭人が帯方郡の東南の海の中にある地にいて、山や島を領地として国を建てている。旧の百余国(『漢書』地理志燕地条の文を指している)で漢(後漢)の時朝見する国があった。今使者や通訳が往来する国は三十国である」「其國本亦以男子為王住七八十年倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子為王名曰卑彌呼」「倭の国は、もとは男性を王としていて、七、八十年は続いたが、その後倭国に内乱が相次ぎ、互いの攻伐が何年も続くに及んで一人の女性を王として共立した。名を卑彌呼(ひみか)という」いったんトップが決まっても次に誰がなるか揉めに揉めたのでしょう。「暦年」の「歴」は次々と巡り歩くが本義ですから、この場合「暦年」は「何年も何年も」と非常に長い期間「倭國亂相攻伐」する状態が続いたことを示します。
この『魏志倭人伝』に婚姻を示唆する重要な語句が登場します。「有屋室父母兄弟臥息異處」「立派なお屋敷があり、父母と(成人した)息子兄弟は別々のところで寝る」とある文です。この時、倭の国は「嫁取り」だったのでしょうか「婿入り」だったのでしょうか。私は何も書いていないことからそのどちらでもない、つまり『妻問婚』だったと考えています。『妻問婚』は多妻を否定しませんから、「其俗國大人皆四五婦下戸或二三婦婦人不淫不妒忌」「その風俗では、国の高貴な者は皆、四、五人の妻を持ち、下戸(庶民)にも二、三人の妻を持つ者がいる。婦人は浮気をせず、嫉妬をしない」も尤もな記述なのです。
『妻問婚』があったとされる時代の考古学的な証拠としては、住居址があります。古墳時代前後には大小の規模を持った竪穴群として特徴的に見られるようになると言います。高群逸枝氏は『日本婚姻史』で次のように考察しています。
大小規模の竪穴群については、私はこれを大屋妻屋式集落とよび、また当時の古語によってヤカラ共同体とみて、典型的な妻問婚の場に比定する。
大屋は母屋とも中つ屋ともいい、トジ・トネおよび長老たち(これらをオヤといった)の詰所であり、同時に共同祭祀や会食等の場所でもあったろう。トジ・トネは夫婦ではなく、沖縄祭治村でのネーガン(根神)とネンチュー(根人)のように、姉と弟であるのを原則とした複式族長であった。この大屋をとりまいて、ヘヤ、クルワ、マキなどとよばれる類の妻屋群があったわけで、これらのなかには、倉庫、産屋、カマ屋、若者小屋等もあったろうが、なんといっても娘や母たちの婚姻用や育児用の小屋が妻屋としては代表的であったろう。「万葉」の人麻呂の歌に「枕づく嬬屋(つまや)」とみえ、高橋朝臣が亡妻を悲傷した歌に、「吾妹子とさ寝し妻屋に」とあるのがそれである。ついでに妻屋のツマは、妻戸のツマ、妻折れ笠のツマのように端という意味、だから妻屋は大屋をめぐる端の小屋の義である。
『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 「第二章 大和時代」「一 妻問婚というもの」38頁〜40頁より
おそらく中国の人々にとってはあまりにも当たり前だったので記述されなかったこととして、子の姓を男女どちらにつけるかという問題があったはずです。縄文の頃は母系に付けていたのでしょうが、農耕が導入され、身分が生じると、この身分がどのように継承されるかで子をどちらに付けるかが決まります。有り体に言うと、氏族の長、部族の長は男性がなりましたから、男子の姓は男系につけた方が有利になったでしょう。そのため、弥生時代からは、姓は男系で継承されることが多かったと考えられます。こうして双系と言われる継承制度、姓と地位は男系で継承し、財産は女系で継承する制度が確立しました。ただしこれは、飛鳥時代になっても、例えば「物部弓削守屋連」のように、父の姓である物部氏と母の姓である弓削氏を併称していたように、どちらも継承していたものが、律令制の施行とともに父の姓だけを称するようになったのかも知れません。記録類はすべてと言ってよいくらい律令施行以降に成立していますから、現代の我々が知りうるのは特別な場合を除いて父系の氏姓のみだというだけのことなのかも知れません。そうだとすると、父母両方の系から継承していたことになり、女系でも男系でもない双系だったということになります。
それに関連して、この時期の禁婚観がどうであったかも考察してみましょう。男が妻を他族に求めるのですから、同族の女との婚姻は禁止されたでしょうか。答えはいいえです。同族=同姓の男女が結婚した事例はたくさんあります。また、群婚遺制を考えても、同族の女と婚姻を許さない風俗があったとは考えられません。すると焦点は私有制度や身分制度が導入された事による変化です。子が母から財産を継承する母系継承を取っている以上、それを混乱させる婚姻、つまり実母と子の婚姻が明確に禁止されたと考えられます。同母の兄弟姉妹も継承が曖昧になるので禁婚対象です。では異母の兄弟姉妹、あるいは父方のオジ・オバ、甥・姪である場合は、たとえ父が同じであっても氏族が異なりますので、禁婚の対象になりません。この禁婚観は非常に強く定着し、「木梨軽皇子と同母妹の軽大娘皇女」が禁を破って私に婚姻したことを『古事記』は「国人皆これを憎み、木梨軽皇子は皇太子を廃され、伊予に流された。軽大娘皇女は後を追い、二人して伊予で死んだ」と書き、『日本書紀』は「夏の盛りに羹(あつもの、熱い汁物)が凍るという奇怪な出来事を占ったことから二人の密通が発覚し、軽大娘皇女が伊予に流された」としているように非常に忌むべきものとされていました。
宗教はどのように移行したでしょうか。『魏志倭人伝』によると卑彌呼(ひみか)は「事鬼道能惑衆」「鬼道に従いよく民衆を惑わした」=「(初期の)神道に仕えて民衆はそのお告げによく従った」とありますから、三世紀には氏族や部族の枠を越えた宗教が萌芽していたことが見て取れます。それは多くの部族に共通する伝統を汲みながらも新しい教義と神託によって瞬く間に信徒を獲得したのでしょう。この頃の王制は祭祀王と政治王を並立する複式統治で、祭祀王が優越していたと考えられ、故に卑彌呼が擁立されるまでなかなか王が定まらなかった所以でもあるでしょう。部族を背景にした宗教ではどうしても特定の部族への偏りが出てきます。男王がこの問題を解決できず、その不満が遂に爆発したため、「倭國亂相攻伐歴年」「倭國は内乱となり、何年も何年も互いに征伐し合った」という状況に陥ったのだと考えられます。そこに部族にとらわれない新しい教義をひっさげて卑彌呼が登場したのでしょう。恐らく戦乱の中にあってこの初期神道と呼ぶべき宗教は発展を続け、古墳時代の祭祀に影響を与えつつ飛鳥時代を迎えたものと思われます。ところが、その飛鳥時代に、大陸から仏教が伝来しました。この仏教を崇拝するかどうかで蘇我氏と物部氏が対立し、ついには戦争にまでなったことはご存じの方が多いでしょう。聖徳太子も篤く仏教に帰依しています(とはいうものの、『日本書紀』のこのあたりの記述はひどくうさんくさいと筆者は考えているのですが)。仏教はインドから中国を経て日本に至ったことでも明らかなように汎世界的な教義を持っています。古来より大陸と交流があったとは言え、豪族たちの目を改めて大陸に向ける契機となったでしょう。とはいえ仏教は知識人の、つまりは豪族や皇族の間で広まったに過ぎませんでした。これは続く奈良時代、平安時代も同じです。
なお、妻問婚の遺風は幕末まで残っていたようで、高群逸枝氏は『日本婚姻史』で次のような事例を紹介がしています。
わが国でも、幕末ごろまでは、各地に妻問婚も婿取婚(姉家督)ものこっていた。「風俗画報」(明治二七年)に、嘉永六年のこととして、土佐国高岡郡津野山郷の大古味部落のことが、つぎのようにみえている。
「女は終身生れたる家に居住し、男は夜々其女房と定たる女の家に行き、朝疾く帰りて世業を別にす。若し子を揚るときは、皆女の家にて養育する者とす」。
『『日本婚姻史』高群逸枝、至文堂、昭和38年5月30日初版 『「第二章 大和時代」「三 妻問婚の諸問題」56頁〜57頁より
空白の四世紀をはさんで、五世紀に入ると歴史は「記紀」の記述範囲に入ってきます。また『万葉集』も古代の婚姻を知る重要な手がかりを授けてくれます。それらによれば、飛鳥時代もまた『妻問婚』であったことがわかります。しかし、奈良時代に入ってしばらくするとこの状況に変化が起こります。それまで通いであった婿を自族に取り込もうとする動きが出てくるのです。
婿取婚
奈良時代はそれまで地方支配の中枢であった国造系豪族に対して土豪とでも呼ぶべき在地勢力が頭をもたげてきます。彼らは勢力拡大のため田畑の開墾を盛んに行いました。これを国家が法で保証したのが「墾田永年私財法」です。開発はかなり熱心に行われそのため男手はどこでもあるだけ欲しいという状況でした。地方の土豪が自分の勢力圏に通ってくる婿連中を労働力として組織化したいと考えても何ら不思議はありません。そのためには、婿が通うのではなく、はっきりと同族として遇し、以降妻と同居する風俗を確立する必要がありました。そうなると婿取られた方は労働力が減少しますから、やはり婿取りに走り、こうやって『婿取婚』は徐々に『妻問婚』に取って代わっていったのだと考えられます。尤も、労働する必要のない貴族階級はその必要が薄く奈良時代から平安時代初期まで『妻問婚』で推移し、世間の大勢が決定してから『婿取婚』へ移行しています。伝統墨守の貴族階級らしい特徴といえましょう。
「壬申の乱」以降、豪族制=氏族制には解体を促す打撃が加えられていきます。とはいえ、長く続いた社会の基本制度が一片の勅語で変わるものではありません。変化はゆっくり進みます。一方地方では先にも述べたとおり、新興豪族が成長してきます。彼らは周囲の農民を組織して墾田の開発に勤しんでいたでしょうから、自然、氏族を無視しこれを解体する方向へ突き進んだでしょう。そうなると、従来の氏族は必ずしも長の目が隅々まで行き届くようなものでなくなっていきます。そうなれば、婚姻の主体、婚主も氏族の長から、直接のオヤ、つまり両親に下降することになります。それを前提として、『婿取婚』がどのように行われたのか見てみましょう。
- まず男が女にヨバヒする、文を届けるなどして、求婚するのが始まりです。貴族に限らず数回文の応酬がある場合もあれば、すんなり承諾を得られる場合もあり、もちろんすげなく断られる場合もあります。
- 『妻問婚』以来、性を支配しているのは女性でした。従って娘の婚姻に承諾を与えるのは、母親の役目になっていました。とはいえ、本人が乗り気であれば強いて拒絶するようなこともありませんでした。
- 承諾を得たら、夜こっそり忍んでいって逢瀬を楽しむ=性交するのも『妻問婚』と変わりません。
- 初夜が明けて自家に戻ると、婿は「後朝(きぬぎぬ)」の使いを出して文を持たせます。
- 何度か通っていると、ある日妻方の両親や親族が寝所に現れて、婿を押さえつけ餅を食わせる「露顕(ところあらはし)」という儀式を行います。
- 「露顕(ところあらはし)」がすむと、婿は忍び通いをやめ、大手を振って通ったり、住み着いたりします。
「露顕(ところあらはし)」は後に、婿が通い始めて大体三日目くらいにするようになったので「三日餅(みかのもちひ)」ともいうようになりました。現在も様相が随分変わったとは言え、宮中の婚姻儀式に含まれていますね。それはともかく、この餅を食わせる意味ですが、もとは原始の共食共性における「ヘグヒ」つまり同じ鍋の食事から来ていて、食事を同じくすることで同族に擬制する意味があります。最近まで「同じ釜の飯を食う」という言葉がよく使われていたことからもわかるように、それは特別な意味を持っていたのです。
『妻問婚』の婚主は氏族のオヤから徐々に母親へ変わっていきましたが、『婿取婚』の頃からは父親も婚主のひとりとして婚姻に関わるようになっていきます。平安時代になると、住居も、都市部の貴族や地方の長者と呼ばれる土豪、有力農民は「寝殿造」に変わります。そうなると婚姻の手順も少し変わります。
- 女性の父親がそれとなく男性に結婚を打診する。これを「けしきばみ」と言います。
- 男性側に異存がないと、形式的に求婚の文を使者に届けさせます。これを「文使」「書使」「消息使」といいます
- 女性側ではその使者を饗応します。古式を尊ぶ家では返事の文を持たせたりしますが、大抵は省かれました。
- 夜を待って、自家で設けた出立所から婿が松明の火を先頭にした行列を組んで出立します。
- 婿行列が妻方に到着すると、妻側の近親の若者が出迎え、脂燭に婿行列の松明の火を移します。その火を廓、帳側、塗籠などの灯爐に点ぜられ、三日間消さずにいます。また大盤所や進物所等にも送って炭火にもうつし、三日後大炊殿等のカマドの火に混ぜます。これを「火合」と言います。
- 婿が新婦と顔合わせに行くと、上がり口で脱いだ沓を新婦の父母が抱いて寝ます。おそらく、婿が他家に行かず、自家に落ち着いてくれますようにという呪法だと思われます。三日後もしくは露顕日になると、婿はもう永久に新婦方の族員と見なされるのでこれを行わなくなります。
- 婿は寝殿に入って新婦が待っている帳中に入ると、服を脱ぐ。これに衾覆人が衾をかける。衾覆人は原則新婦の母で、三日間同宿する。要は経験者の介添えですな。
- 一夜明けると婿はいったん自家へ帰り、新婦へ後朝使を送る。
- こうしてさらに三夜通うと露顕(ところあらはし)の儀式を行う。後には即日行ったり、任意の吉日を選ぶようになった。
- 三日目には「三日餅(みかのもちひ)」を婿に食べさせるのだが、これも後に露顕(ところあらはし)に併せて行うようになった。
- 夫婦を同籍にして、支障がなかったならなぜ同籍の方針が貫徹されなかったか。
- 口分田の班給・田租の徴収・庸・調の頭税を課すための台帳の記述方式が一定していないことになつて不公正となる。
- 妻子の二重登録(両貫)を生ずるおそれもあり、これを防ぐには、別居・同居のいかんにかかわらず妻子を夫家もしぐは婦家のいづれか一方の籍に附すべきであるが、それでは班田と徴収の公正は期せられない。(中略)高群氏の言われるように、婿入婚的夫婦同居までを、あたかも嫁入婚的夫婦同居であるかのように転籍するという風なことが、果してあり得たであろうか。かうまで言ってはあまりにも恣意的解釈であるとせざるを得ない。このように、奈良時代における差別的夫婦同居制(あるいは差別的夫婦別居制)を否定し、大化以後、平安中期までを過渡的前婿取婚期とする高群氏の考え方は、とうてい成立しがたい構想であることが明かになったと思う。
- 籍帳は貴重な史料であるが、単独では各種各様の説がたてられうる。すなわち、これだけをもってしては、こんにち決定的なことはほとんどいえない。(中略)要するに洞氏と私との見方のちがいは、視角のちがいであって、この厄介な籍帳談義に関するかぎり、どちらがどちらともいえないとおもう。
- 奈良期ではツマドヒの語が代表語として継続しているように、通い(別居)が原則的で、住み(同居)は一時的滞在か寄合が多い。これが平安期に入ると前にみたような婿取儀式による正式の同居も漸次にあらわれる、この正式な婿取婚に比べると寄合同居は恣意的・例外的同居であって、単婚式である。(中略)こういう大家族のほかに、同種の小家族もあり、そうかとおもうと、前代的な妻問別居式も多い、いったい各時代の婚制や族制は、支配層において典型的・公式的に顕現するもので、被支配層になると前代からの遅延形態等がはじまり、雑多な家族状態が形づくられる。最下層の奴隷制—直接生産者層等になると、生涯妻問式のみの例も多い。このことが理解されないと、各時代の村落事情等にたいしても、単純な機械論的 推理などがなされやすい。
- 奈良以後鎌倉頃までのこの種の集落なり、集落内の個々の家族態なりは、大小にかかわらず結合の規範が族長的であって、家父長的でないことである。(中略)妻の奴隷化を固定づける嫁取式による夫婦家族などは、もちろん一例もみられず各夫婦は無儀式の妻問で寄合ったり、婿取儀式後に移住したものである。この集落の子弟で、市中へ婿通いや婿住みをしている者も多い。これらの家族態を統卒する方式としては族長式一世帯主式のほかにはありえない。(中略)招婿婚にかわって、嫁取婚が出現する室町以後になって、はじめて東北各地等にいまも遺存しているような名子式父系大家族等も顕現するのである。
- 右の期間中外見上は、嫁取式にあやまられるような形をもった例外婚としては寄合の外にも、スエ・召上・進上・掠奪等、女の奴隷化を伴う型もあり、時代が進むにつれて増加し、これらが室町以後の嫁取式へと影響することは疑わないし、またそれと同時に、前家父長型の家族型も増加するが、しかし原則的・原理的には、あくまで例外の域を出ず、招婿婚を族長家族のみが支配的であることが理解されねばならず、原則と現象は厳密に区別されねばならない、いわゆる「質と量の法則」のように、質的転化をとげないかぎり、どんなに現象が多量でも原則は厳存するのである。
- 日本の女性は処女の純潔を重んじない。それを欠いても栄誉も結婚する資格も失わない。
- 日本では男性は望みのままに何人でも離別する。離別されても栄誉も結婚する資格も失わない。
- 日本ではしばしば妻たちが夫を離別する。
- 日本では娘や妻が、両親や夫の許可なく、自由に行きたいところへ行く。
- 日本では親族の女が誘拐されようとしても、父母兄弟が見て見ぬふりをしてすごす。親戚同士の情愛がうすく、たがいに見知らぬもの同士のようにふるまう。
- 日本では夫婦のおのおのが自分のわけまえや財産を所有しており、ときには妻が夫に高利で貸しつける。
- ヨーロッパでは女性が文字を書く心得は普及していないが、日本の貴婦人はその心得がなければ格は下がるものとされる。
- 女性の飲酒は頻繁で祭礼にはたびたび酩酊するまでのむ。
- いともふつうに堕胎が行われ、二〇回も堕ろした女性がいる。
- 一. 百姓迯散時、稱逃毀令損亡事
- 右諸國住民迯脱之時其領主等稱迯毀抑留妻子奪取資財所行之企甚背仁政若被召決之處有年貢所當之未濟者可致其償不然者早可被糺返損物但於去留者宜任民意也
- 一. 百姓逃散の時、逃毀(とうき=犯罪者の財産没収)と称して損亡(そんまう=損害を与へる)せしむる事
- 右、諸国の住民逃脱の時、その領主ら逃毀と称して、妻子を抑留し資財を奪ひ取る、所行の企て甚だ仁政に背く。もし召し決(=百姓を連れ戻して事情を聞く)せられるゝのところ、年貢所当の未済有らば、その償ひを致す(=没収財産から)べし。然らざれば、早く損物を糺(ただ)し返さるべし。但し、去留(= 領地に留まるかどうか)に於ては宜しく民意(=百姓の判断)に任すべきなり。
-
と、農民の逃散の権利を認めている条があります。領主の横暴にただ屈するばかりでなく、集団で団結してこれに対抗していたことが窺えます。逃散ばかりでなく、一味神水や列参強訴も行われました。地頭も強権を以て対抗しようとしたのですが、荘園制度では自ずから限界があり、地頭も万能ではなかったのです。そこで「職」という形で定められた範囲をふみ越えて国人領主としての自立する方向へ向かいました。平たく言えば、とやかく言う連中は排除して全部俺様の物にする、ということです。その動きに伴い、鎌倉時代後半から室町時代にかけて、それまでの荘園公領制の基礎になっていた名田制が崩れだし、それまで分散して居住し、集団的な力を持たなかった農民が分散している必要がなくなり、集住して村落を作って自治意識と連帯意識に支えられた惣村を形成するようになっていきました。強権で対抗しようとしたら相手がますます手強くなってしまったのです。
武力を持っている相手に対抗しようというのですから、惣村はその団結力を強力にしなくてはなりません。一揆に立ち上がる時に備えて武装もします。村中のことはすべて寄合で諮られ、決定されました。ただし、土地は耕作するもののその所有権は領主にあります。有り体に言えば一般の農民には相続させるような財産など、わずかな家財を除けばないのと同じで、家父長権があったところで振るい先が子供の結婚くらいしかありませんでした。では、その子供の結婚も自由にできたかというと大いに疑問です。惣村は何も地頭とだけ対峙していたわけではありません。旱が続けば水争いが起こり、村と村が対決しました。昭和になっても水争いで死人が出たといいますから、当時も同様であったことは想像に難くありません。うかつなところから嫁を取ると村中から白い眼で見られたことは間違いなく、しかるべき媒人に頭を下げる必要があったでしょう。しかも室町時代ころから『群婚』の風が後退し、毎年の祭事のさいに限り営まれるようになるなど非日常化していく中で「夜這い」の風習が起こり、村の若衆などがこれを管理するようになったと思われます。つまり、性についても村の自治に委ねることになり、放っておくと息子や娘は結婚せずとも性生活を満喫できる状態にあったため、これもまた親が頭を下げて、しかるべき相手を世話してもらう必要がありました。何のことはない、家父長権など空証文でしかなかったのです。
では時代が進んで、戦国時代、江戸時代になるとどうでしょうか。室町時代から守護大名は一円知行に乗り出していました。これと地頭の動きが連動して荘園制が崩れたのです。戦国大名はその守護大名の守護代や、その配下が下克上で成り上がった者が多く(豊臣秀吉のように一介の足軽から成り上がったのは極めて稀なケース)、土豪の頭越しに直接領民を支配しようとしました。最も早くこれを試みたのが織田信長で、最も成功したのが徳川家康です。太閤検地も耕作者を直接把握することが目的の一つでした。戦国時代はその過渡期にあり、惣村をなだめるためにその自治には口出しせず、ただ必要な人数と兵糧を出させました。尤も秀吉の刀狩りに見られるように、武装を取り上げ、惣村から戦闘力を奪うことは忘れていません。戦国時代全般に渡って惣村の力は次第に削減されていき、江戸時代に入り、徳川家以下の支配が盤石になると、惣村は撫民の対象ではあっても支配の道具としては不要になります。それで惣村が解体されたわけではありませんが、支配はよりきめ細かくなり、惣村の中の耕作者を土地の所有者として認め、これを直接支配するようになります。もちろん、所有者として認められたからといって勝手に売買してよいわけではありません。江戸時代後半になると、耕作地を質に入れる百姓が多くなりますが(売買はだめでも質に入れて流すことは許された)、それは財産を作るためではなく、借金の返済のためでしたので、やはり多くの農民にとって財産の相続などは無縁のことでした。村と村の争いは江戸時代になってももちろん起きますし、「夜這い」は既に村の掟に組み込まれるようになっていました。とすると婚姻においてもやはり頭を下げるのは親ばかりと言うことで、姑と嫁の折り合いが悪かったりするとこれも頭を悩ますのは亭主の仕事で、『嫁取婚』から家父長制に移行したことは、庶民にとって何かいいことなどあったのかと思います。
ところで、赤松啓介氏の『夜這いの民俗学』筑摩書房、2004年6月9日初版でつとに有名な「夜這い」ですが、氏も著書で述べておられるように、惣村ごとに掟があり、全国画一な形態の「夜這い」なる性風俗があったわけではありません。何歳から「夜這い」の仲間に入れるか、誰を「夜這い」の仲間に含めるか(村の中でも上下に差別があったのです)、嫁に「夜這い」してもよいかどうか、組み合わせは総当たりかくじ引きか自由に決めてよいか、他村からの「夜這い」を認めるか認めないか、認めるとしたらどこの村ならよいか、などは村ごとに異なり、ひとつとして同じものはありません。そもそも「夜這い」ではなく『妻問婚』だった地域もあるくらいなので、画一的な「夜這い」の決まりや作法なるものがあるはずもありません。村によっては若衆がすべて管理し、結婚(つまり「夜這い」仲間から抜けることになる村もある)にも干渉したといいます。共通して言えるのは、惣村の総意で維持されていたことだけです。もちろん、「夜這い」のない村もあったかも知れません。
これが村の豪農や、町の大商人となると話が変わってきます。豪農は質流れの土地を買い集め、大地主として小作人を使役するようになりますし、大商人となると、莫大な財産があります。しかし彼らは彼らで自由ではありません。豪農は同じような豪農や名主や庄屋、郷士といった名家との婚姻を望みますし、実際、嫁を取るにしても婿を入れるにしても財産管理に無頓着な相手ではせっかくの資産を活かせないどころか、下手をすると食い潰されてしまうことになります。大商人も同じです。普段のつきあいや商売上の利得も考慮しなくてはなりません。政略結婚というと当事者の不自由性を問題にする人は多いのですが、婚主も同じように不自由な中から少しでもよい相手をと思って探すのですから、どちらもどちらです。その点、資産のない町人は気楽なものでした。気楽でしたが、そんな奴に縁づくような女性はそうはいません。世の中よくできています。俗に三行半といって線を三行と半分かけば亭主からいつでも無体に離縁ができたと言いますが、実際には、女房に愛想を尽かされる亭主もまた多く、嫌がる亭主に三行半を書けと町名主が命令したり、町中の女房連中が強談判して書かせた話も多くあります。亭主の横暴にじっと我慢して…という女性もいなかったわけではありませんが、もっと奔放で力強い女性の方が多かったのです。
江戸時代の武士ともなると、不自由さは最大になります。普段のつきあいはもとより、自家や相手の家格、当人の身分(嫡庶など)、履歴を調べて選ばなくてはなりません。しかも、その許可を主家に仰がなくてはならないのです。婚儀も家格によって決まっており、その式次第を守らなくてはなりません。嫁に出すのももらうのも大変な苦労です。うっかり同輩のところから嫁を取って実家が主家から咎めを受けた場合、下手を打つと連座させられる場合がありました。その心労たるや並大抵ではなかったでしょう。それでも江戸時代中頃までは働かずとも、知行があったり蔵米を貰って生活できたのですから当然かも知れませんが、江戸時代も後期になると知行や蔵米だけでは食べていけず内職に精を出さねばならない有様となります。借金を重ねた挙げ句破産する者も珍しくなくなります。そうなると、身分違いであっても富豪の娘を持参金付きで貰いたくなる気持ちもわからないでもありません。
では町人や武士は性をどうしていたのかと言うと、まず町人に関しては大人の場合、遊郭や岡場所があったので簡単でした。吉原のような遊郭で遊ぶには庶民では財政的に無理で、大抵、岡場所と言われる二流どころの売春窟を利用していました。一人前になるまではどうしていたかというと、例えば大商人の店に丁稚に出された場合、精通があったら先輩がしかるべき女中を宛がい手引きして「夜這い」をかけていました。もちろん男女間で取り決めがあり、奉公にあがりたての右も左もわからない新米の女中の場合は無理矢理してしまうこともあったと言いますが、概ね取り決めは守られたと聞いています。「夜這い」は何も農村だけのことではなかったのです。お堅い武家屋敷にだって下女目当てに「夜這い」に及ぶ男が後を絶たなかったといいますから、外は推して知るべしです。大人になって嫁にも飽きたなと思うが岡場所にすら行く金がない場合は、さらに安い夜鷹と呼ばれる街娼を相手にしました。見目のよい男の子の場合は近所のおばさんが放っておくはずもなく、虎視眈々と機会を狙って筆下ろしをしたそうな。
これが大店のおぼっちゃんだとそうはいきません。乳母に筆下ろしの相手を勤めさせたり、女中の中に信頼できる者がいれば任せたりする場合もあったといいますが、遊郭を利用することも多かったようです。一般に吉原などの遊郭というと、特に初期吉原の太夫が有名ですが、さすがに太夫相手に筆下ろしを頼んだら即行で帰られてしまったでしょう。粋も何もあったものではありません。事情のよくわかった格子、あるいは店に長くいてそこそこ信頼できる散茶相手だったと思われます。
少々脱線しますが、初期吉原の太夫といえば、舞などの芸が見事なのは無論で、書をよくし、漢詩や和歌を詠むなど教養豊かで、中には『源氏物語』や『古今和歌集』をそらんじる才女もいたそうですから、現代一般女性ではとてもかなうような相手ではありません。なおかつ房中術もしっかり仕込まれていますから、男が女に抱く理想を結集したような存在です。それだけに遊ぶには非常にお金がかかり、なまなかな商人では身代を潰してしまうほどでした。太夫と遊ぶには、まず「初会」といって顔合わせがあり、次に「裏」を返して、三度目を「馴染」といって初めて寝所を共にすることができます。一回当たり37匁(3.7両)かかったといい、しかもこれは太夫にだけかかるお金で、遣手や新造、禿へのご祝儀や小遣いはまた別です。しかも太夫は揚屋では客を取らず、必ず茶屋に呼ばねばなりませんでしたから、茶屋で遊ぶのもまた大金がかかります。このように会うだけでも散財で、その上物惜しみしないところを見せないといけませんから、いくらでもお金がかかります。半端な商人では身代が潰れたというのも当然でしょう。しかも太夫は金を出しても気のない相手は平気で振ります。振られたらそこでおしまいでお金も帰ってきません。遊ぶというのも太夫が芸をするのをただ眺めて楽しむだけでは無粋ということでやはり振られます。太夫の気を引き関心を持たせる教養と話術がないとまず楽しくなりません。なにせ太夫の方は客を楽しませる気がないからです。無論自分が気に入った客には愛想を振りまきますが、そこまで行くには客の方から本気で口説いて恋愛に持ち込む技量が必要です。そうです。太夫は惚れさせないと楽しくないのです。しかし相手も先輩から散々仕込まれていますからにわか仕込みの口説き方では通用しません。初期吉原の上客は大名や旗本などの武士階級だったのですが、彼らを以てしても口説き損ねる相手だったのです。これが格子になるとぐっと親しみやすくなります。が、いやな客はやっぱり振ります。となると散茶に行くしかなくて、散茶は振らないから散茶というの言葉通り、ちゃんと相手をしてくれます。江戸時代後期になると武士は財政難で大名といえど吉原で遊ぶ金はなくなります。すると自然、相手は商人や近在の豪農といった庶民相手になりますので教養もへったくれもなく、太夫、格子といった高級遊女は吉原からいなくなってしまいます。
この頃吉原などの遊女がどう思われていたかについて、慶応元年(西暦1865年)に来日したドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンは次のように書き残しています。
貧しい親が年端も行かぬ娘を何年か売春宿に売り渡すことは、法律で認められている。契約期間が切れたら取り戻すことができるし、さらに数年契約更新することも可能である。この売買契約にあたって、親たちは、ちょうどわれわれヨーロッパ人が娘を何年か良家に行儀見習いに出すときに感じる程度の傷み(いたみ)しか感じない。なぜなら売春婦は、日本では、社会的身分として必ずしも恥辱とか不名誉とかを伴うものではなく、他の職業とくらべてなんら見劣りすることのない、まっとうな生活手段としてみなされているからである。娼家を出て正妻の地位につくこともあれば、花魁あるいは芸者の年季を勤めあげたあと、生家に戻って結婚することも、ごく普通に行われる
安政六年(西暦1859年)に来日したイギリスの公使オールコックは、
彼女(遊女)たちは消すことのできぬ烙印が押されるようなこともなく、したがって結婚もできるし、そしてまた実際にしばしば結婚するらしい。夫の方では、このような婦人の方が教育があり芸のたしなみもあるというので、普通の婦人と結婚するよりも好ましいわけである
と言っていますし、慶応二年(西暦1866年)に来日したフランス海軍士官スエンソンは、
日本のゲーコは、ほかの国の娼婦とはちがい、自分が堕落しているという意識を持っていないのが長所である。日本人の概念からいえば、ゲーコの仕事はほかの人間と同じくパンを得るための一手段にすぎず、(西洋の)一部の著作家が主張するように尊敬されるべき仕事ではないにしろ、日本人の道徳、いや不道徳観念からいって、少なくとも軽視すべき仕事ではない。子供を養えない貧しい家庭は、金銭を受け取るのと引換に子供たちを茶屋の主人に預けても別に恥じ入ったりするようなことはないし、家にいるより子供たちがいいものを食べられ、いいものを着られると確信している
と書き残しています。
遊女って要するに売春婦でしょ、賤業ってイメージを払拭しようとして、印象操作してないか? と思われるかも知れませんが、事実なので仕方ありません。遊郭の遊女が身請けされたり、年季が明けたりした後は、相手がいれば普通に結婚してましたし、そのまま遊郭に残って遣手や新造になる者もいました。別に売春していたからと言って後ろめたく思う人もいませんでしたし、そんな文化は明治になるまでなかったのです。明治になって下級武士の禁欲的な価値観がそのまま刑法や民法として法律に制定され、学校教育が普及したことで、初めて賤業視が生まれたのです。だいたい「夜這い」があったのに、遊女だけ特別視するっておかしいでしょ? だからと言って、楽な商売だと思われても困ります。太夫、格子といった上妓はともかく、文字通り身体を使った商売ですので大変疲れますし、何より一日何人も客の対応をするだけでも神経を使います。妊娠だってしますし、過労で体調を崩し、病気にもなって死んだ者も多かったのです。三ノ輪の浄閑寺には現存するだけで数千人に及ぶ遊女の記録が残っており、それを辿ってみると死亡時の平均年齢は二十二歳前後となっています。また、岡場所の女郎や宿場町の飯盛女になると労働条件がより劣悪になりますから、年季が明けるまで身が持たず、若いうちに死んでいった者が数知れずいます。なお、折檻などの虐待で死ぬ遊女が多かったという人もいますが、それは半分正しく半分間違っています。遊女でなくても奉公人は折檻で死ぬ者が少なくなかったのです。閑話休題。
なお、江戸時代の町人の性風俗に関しては、永井義男氏の「大江戸八百八町の性生活」が大変面白うございます。ぜひご実見あらせられますよう。
では武士はどうしていたのかというと、将軍家の場合は、元服の際、信頼の置けるもしくは若君が指名する奥女中に筆下ろしをさせ、その後も相手を勤めさせたそうです。相手が懐妊してしまった場合、産ませることができない事情があると、旗本、御家人で独身の息子がいる訳の分かった家へお下しになるわけです。時代劇に御落胤ネタが多いのには理由があるんですね。大名の場合も似たり寄ったりです。ではもっと小身の旗本やお目見え以下の武士はどうしていたかというと、これがわかりません。遊郭を使ったんだろうなとは思うのですが、始終遊べる金があるわけでもなし、謎と言えば謎です。その上次男三男のいわゆる部屋住みともなると、そもそも嫁のきてがあるかどうかもわからないのですから、もう気の毒としか言いようがありません。いや待てよ。「衆道」というのがあったなと思い至りました。
武士と言えば、そもそもは戦闘集団でしたので、出兵中は女性を連れて行くことができません(秀吉の小田原征伐を除く)。そこで非常に早くから「衆道」が盛んでした。その起源はというと、日本で最初に男色があったのは神功皇后の頃だと『日本書紀』に書かれています。ほとんど神話に近い時代です。次いで『続日本紀』には、天武天皇の孫である道祖王が、聖武天皇の喪中に侍児と男色を行ったとして廃太子とされたとあります。奈良時代、平安時代になると、寺院で男色が流行しました。ほら、お坊さんって女性に接することが禁止されているから(除く浄土真宗)。お稚児さんを取り合うお坊さんの絵が残ってたりします。『万葉集』にも男性に宛てたと思われる和歌があったりします。大伴家持も読んでます。平安時代末期には男色の流行が公家にも広がります。これもう伝統と言ってよいでしょう。何が日本人をこれほどまでに男色へ惹きつけるのでしょうか。
室町時代になっても、北畠親房が『神皇正統記』で男色の流行に言及していたり、三代将軍・足利義満はまだ少年だった能役者の世阿弥を寵愛したりと全く勢いは衰えていません。能や狂言には男色がとても多く取り入れられています。戦国時代になると、戦国大名の間に戦場で美少年を「お小姓」としてそばに置いて愛でることが流行ります。織田信長と森蘭丸が有名ですね。1549年に来日したフランシスコ・ザビエルは日本人を賞賛しながらも、許すことができない罪悪として男色を挙げています。そしてザビエルを保護し布教を許した山口の大名大内義隆が数多の美少年を抱えていることに驚き嘆いています。世に武士道というものを知らしめたあの『葉隠』にもちゃんと衆道のたしなみについて書かれた箇所があります。曰く「互いに想う相手は一生にただひとりだけ」曰く「相手を何度も取り替えるなどは言語道断」曰く「そのためには5年は付き合ってみて、よく相手の人間性を見極めるべき」そして、相手が人間として信用できないような浮気者だったら、付き合う価値がないので断固として別れるべきだとし、怒鳴りつけてもまとわりついてくるようであれば「切り捨つべし」と断言しています。女性より大切にされていますなぁ。上杉謙信が生涯不犯の誓いを立てられたのは、衆道にのめり込んでいたからだという説がありますし、三代将軍徳川家光の衆道好みも有名です。室町時代には武士や僧侶の間で行われていただけのようですが、江戸時代になって「陰間茶屋」という少年を侍らせて男色を楽しむ専門の茶屋ができて庶民にも広がり、江戸時代前期に全盛を迎えます。若衆歌舞伎などもあって大変ヒットしたんですが、余りに人気が過熱して町奉行所から禁止されてしまうほどでした。どんだけ男の子好きやってん。
江戸時代中期になると、美少年を取り合って刃傷沙汰が起きるわ、恋愛至上主義を貫徹し、主君への忠義より美少年への愛に生きる侍が続出したりと事態を静観していられなくなったため、これを禁止する藩が増え、幕府も享保の改革や天保の改革で禁止が徹底させるなど衆道は衰退へ向かいます。とはいえ、なくなってしまったわけではなく、衆道を題材にした戯作も書かれていますし、浮世絵も残っています。明治維新の直前にも若衆を侍らせて船遊びをする侍がいたそうですから、隠すようなものではなかったのです。それにしても本当に日本って性に寛容というか奔放だったんですねえ。
そんな中、町人は「夜這い」を楽しみ、旦那は女遊びもしくは美少年遊びをしている中で、武家の女房は慎み深く貞操を守っていた…わけではなく、不義密通は割とよく起きていました。ほとんどの場合、体面に傷をつくことを考えた旦那が適当な理由をでっち上げて、女房を離縁して済ませたそうです。もちろん本当に「重ねておいて四つにする」を実行した例もあり、『よしの冊子』に載っています。世間の人は「珍しいこともあったもんだ」と評判を呼んだそうですから、本当に稀なできごとであったようです。
「武士は食はねど高楊枝」という言葉がありますが、下級武士などは金は無いのに体面は気にしなくてはならないという、性に関しては極度に禁欲的な生活であったのかも知れません。その下級武士が政権を握ると、本格的に禁欲的な家父長制が始まります。
家父長婚
家父長制という意味では前代から継続しているのに、別項目にしたのは、下級武士の禁欲的な性生活が法律となって一般に適用され始めるのと、憲法が制定され、近代法治国家として性を管理する段階に入るからです。ではどのような状況だったのでしょう。明治民法の第四編に親族の規定があり、そこで婚姻についても定められています。
第七百五十条
家族カ婚姻又ハ養子縁組ヲ為スニハ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 家族カ前項ノ規定ニ違反シテ婚姻又ハ養子縁組ヲ為シタルトキハ戸主ハ其婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ一年内ニ離籍ヲ為シ又ハ復籍ヲ拒ムコトヲ得
3 家族カ養子ヲ為シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ従ヒ離籍セラレタルトキハ其養子ハ養親ニ随ヒテ其家ニ入ル第七百六十五条
男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百六十六条
配偶者アル者ハ重ネテ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百六十七条
女ハ前婚ノ解消又ハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ再婚ヲ為スコトヲ得ス
2 女カ前婚ノ解消又ハ取消ノ前ヨリ懐胎シタル場合ニ於テハ其分娩ノ日ヨリ前項ノ規定ヲ適用セス第七百六十八条
姦通ニ因リテ離婚又ハ刑ノ宣告ヲ受ケタル者ハ相姦者ト婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百六十九条
直系血族又ハ三親等内ノ傍系血族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス但養子ト養方ノ傍系血族トノ間ハ此限ニ在ラス第七百七十条
直系姻族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百二十九条ノ規定ニ依リ姻族関係カ止ミタル後亦同シ第七百七十一条
養子、其配偶者、直系卑属又ハ其配偶者ト養親又ハ其直系尊属トノ間ニ於テハ第七百三十条ノ規定ニ依リ親族関係カ止ミタル後ト雖モ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百七十二条
子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満三十年女カ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス
2 父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル
3 父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス第七百七十三条
継父母又ハ嫡母カ子ノ婚姻ニ同意セサルトキハ子ハ親族会ノ同意ヲ得テ婚姻ヲ為スコトヲ得まず第七百五十条で婚姻には戸主の同意が必要であることが明記されています。戸主とは明治民法において定められた「家」を代表する人間のことです。通常は父親もしくは祖父になります。しかも同意を経ないで婚姻した場合は1年以内なら取り消せるとあります。家族の認めない結婚は絶対できなかったことがわかります。
婚姻可能年齢が現行民法の規定より男女それぞれ一歳ずつ年下になっています。第七百六十六条と第七百六十七条、第七百六十九条、第七百七十条、第七百七十一条は現在も同じですが、第七百六十八条は現行の民法にない規定です。姦通(要するに浮気)した女性は離婚後も浮気相手とは結婚できないという規定です。戦前、浮気は犯罪だったのです。姦通罪は旧刑法(明治13年太政官布告第36号)に定められていました。
第三百五十三条
有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
2 此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ效ナシこの定めは明治40年に改訂されています。(明治40年法律第45号)
第百八十三条
有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
2 前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシいずれにせよ、妻が浮気したら二年以下の懲役にする。相手も同じ。という罰則です。男が独身の女性と浮気しても罪にならない点がポイントです。この自由を享受した有名人と言えば、与謝野鉄幹でしょう。山口県の徳山女学校に16歳から勤務していたのですが、女生徒と関係して子供を産ませています。ところがこの生徒とは別れて別の生徒と同棲し、また子供を産ませています。現代なら新聞の紙面に載って、2chで徹底的に叩かれますね(笑)。その女生徒とは結婚しているのですが、26歳の時離婚して、別の人と結婚しています。ところが後の与謝野晶子と不倫していてこれが27歳の時に問題化します。翌年夫人と離婚して晶子と結婚。その女性遍歴が祟ったのか、晶子と結婚してからは創作が不振に陥り、成功を続ける晶子の影で悶々とする日々を送る羽目になります。写真を見てもそこまでハンサムとは思えないのですが、やはり話術でしょうか。一方、姦通罪で告訴された有名人と言えば、北原白秋です。25歳の時に引っ越した家の隣に住む女性と恋に落ちたのですが、この女性が夫と別居中の身だったのです。これを夫が告発し、収監されたのですが、弟らの尽力で何とか釈放され、示談で解決しています。このスキャンダルで名声は地に墜ちましたが、活動は続け、後に歌壇でも独特の地位を占めるようになります。刑に服さなかったので、件の女性とその後結婚しています。実際の所、姦通罪は親告罪なのに加え、妻を寝取られるというのは恥でしかなかったため、姦通が本当はどれくらいあったかはわかっていないのです。恐らく夫は、江戸時代の武士同様、訴訟を起こすよりも、妻を離縁する方を選んだのでしょう。と思われるのは、明治時代の離婚率(人口千人当たりの離婚件数)が高いからです。特に、明治15年から31年は、2.27から3.39の間を上下しています。これは、上でみたように旧民法の第七百六十八条により、姦通した妻が離婚後に恋に落ちた男と思いを遂げることを抑えたからで、夫の側からすれば、離婚しただけでも、妻への意趣返しができると思ったからでしょう。
旧民法に戻ります。第七百七十二条は、現在未成年者に適用されています。男が三〇歳以上で女性が二五歳以上なら婚姻できそうに思いますが、戸主の同意は絶対に必要であることを思い起こして下さい。いくつになっていても実質的には家族の同意がないと結婚できなかったのです。また第3項において未成年者の婚姻で父母がいないときは後見人と親族の同意が必要となっています。第七百七十三条は父母といっても義理の父母が反対した場合、または血の繋がった母が反対した場合は、親族の同意があれば結婚してよしという条項です。これも現行民法にはありません。現代的感覚からすれば、異常にうざったい処置のように思えますが、民法制定当時の元下級武士の感覚からすると、それくらいは当たり前だったのではないでしょうか。とにかく「家」を守るが大事であり、戸主の権限も「家」を守るためですから、江戸時代末期下級武士の価値観がいかんなく反映されていることは確かなようです。
では実際はどうだったかというと、よく戦前は恋愛結婚なんてなかったとしたり顔で言う人がいますが、それは大きな勘違いです。だいたい好いたの惚れたのわんわん泣くわという娘を前にしたら、支障のない相手であれば結婚させたでしょうし、逆も又然り。だいたい好きになる相手も普段の交際範囲の中から選んで好きになるわけですから、親はそこを注意しておけば、とんでもないスカを引き当てることもないわけです。ただ、恋愛にうつつを抜かす暇があるのは金持ち連中くらいなもので、後は職業婦人が職場恋愛というところが相場でしょうか。もちろん、現在のような恋愛結婚全盛の時代とは異なり、見合い結婚が多いのは確かで、1930年代でも恋愛結婚は婚姻数全体の13.4%しかありません(『日本の「恋愛結婚」「見合い結婚」の推移をグラフ化してみる』から引用。
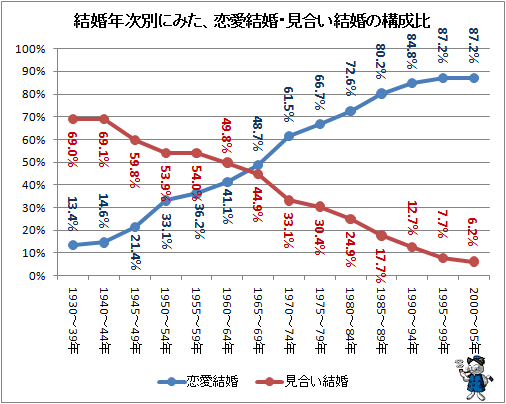
それを以て不自由というなら、現代出会いがなく結婚できないと嘆く男女も不自由です。国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料中、性別生涯未婚率および初婚年齢(SMAM):1920年〜2010年を見ますと、1995年頃を境に生涯未婚率が急上昇、女性で10.61%、男性ではなんと20.14%に達しています ([2022-11-03 追記] 2020 年国勢調査では、男性 28.3%、女性 17.8% に達しています)。「相手は知らない人だけど必ず結婚はできる」と「相手を好きになって結婚できる可能性もあるけどできない可能性も高い」のどちらが不自由さという点では勝っているでしょう?
何より、農村部では出会いなどほとんどあり得ませんし、口減らしで都会に奉公へ出されたりもしますが、遊びに行くわけではないので、出会いもそんなにありません。ですので適齢期になったり、できちゃった場合にちゃんとお世話してくれる人がいて結婚はできる。というのもそう悪くはないのかも知れません。よく言えばお節介な、悪く言えば無理強いで結婚させられるわけですが、恋愛感情はなくてもお互いいたわり合い大事にしあう夫婦はいたわけで、恋愛脳に毒されている現代人よりよほど幸せだったかも知れません。嫁と姑の折り合いが悪いと夫か妻のいずれかが地獄を見たのは確かですけどね。また、よく言われる戸主権も、例えば次の表を見てじっくり考えてみて下さい。当時、国民の大多数は農業に従事していました。
第1表 明治時代における自小作別農家戸数割合および小作地割合 (単位:%)自小作別農家戸数割合 総耕地のうち小作地割合 自作農 自小作農 小作農 明治6年 — — — 31.1 明治16,17年 37.3 41.8 20.9 35.9 明治21年 33.3 45.1 21.6 (20年) 39.3 明治25年 — — — 40.0 明治35年 35.4 38.4 26.2 — 明治41年 32.9 39.9 27.2 44.9 明治45年 32.1 40.8 27.1 45.2 総面積の半分近くの農地が小作によって耕作されており、自小作が小作をしないと食っていけない零細農民だと仮定すると(仮定しなくても実際零細農家なのですが)、明治末年で67.9%と、実に約七割の農民が無産者あるいはほとんど無産者に等しいことがわかります(上記の表は、綿谷赳夫氏「戦前戦後における農民層の変貌 (一)」より引用しています)。この傾向は大正、昭和にかけてさらに強くなり、例えば昭和4年の大阪府では、全耕地の60.8%が小作地となります(大場正巳氏『昭和初期、農業構造変動の「統計的」考察』第2表「山形県と大阪府における総小作地率および田小作地率の推移より引用)。つまり、国民の圧倒的大多数は資産など薬にしたくてもなく、戸主権があろうがなかろうが関係のない状態にあったのです。大正時代には小作争議が頻発し、米騒動が起きており、昭和初期に東北地方が大凶作に見舞われた際には農家が養育能力を喪失し、間引きが盛んに行われる一方で「娘の身売り」が大勢出て社会問題になったことからもこの状態は裏付けられます。二・二六事件もその困窮を政府も財閥も救おうとしないとする公憤が原因のひとつであったとされています。
では都市はというと、言うまでもなくほとんどが無産者です。財産など持っているのはほんの一握りの人たちで、あとは日給、月給で暮らさざるを得ない人々です。だいいち、家父長制が下々の隅々にまで浸透し権威を持っていたのなら、モボ・モガといった今風を満喫する若者が現れるはずがありません。職業婦人も急増し、家父長の威厳など形無しです。
でもまあ、「子なきは去る」で本人同士は嫌がってるのに無理矢理離婚させられたり、次々女をこさえて遊び回って女房を苦労させたりということもあったわけで、決して戦前がよかったと言っているわけではありません。しかし、現代的恋愛至上主義価値観で戦前はまるで封鎖されていたかのように考えることは間違いだと言っているわけです。戦前は、恋愛と結婚はまったく別の問題でした。もちろん不倫の挙げ句妻を捨て不倫相手と再婚する男性がいなかったわけではありません。が、それは今でも変わらないわけで、戦前だからという問題ではありません。ある程度の年齢になったら結婚して子供をもうけるのが当たり前で、そのために媒人を買って出る人が大勢いて見合い結婚が成り立っていました。おそらく多くの人が恋愛とは生涯関係なかったのではないでしょうか。いや、例えば初恋のたぐいを経験しない女性がいなかったとかではなく、それはそれ、結婚は結婚という価値観だったのです。そしてそれでも問題なかったわけですね。相手の人物は媒人が保証してくれますし、本当にロクデナシと結婚させられたら紹介者や媒人の体面問題になりましたから、見合い結婚でそんなにひどい結婚生活というのはまあなかったのです。戦前が抑圧された非人間的な時代であったというのは、文学者の書くことを真に受けすぎか、日教組の偏向教育で洗脳されているかどちらかです。どちらも極端な事例を普遍的な問題であったかのように作為しているので注意が必要です。そういう意味では、制度としての結婚という立場から見ると、現在の結婚には恋愛が必須という状況の方がむしろ異常に見えます。
そんな戦前の性事情はどうであったかというと、農村部やあるいは都会でも「夜這い」全盛で大人は総出で楽しんでいます。世間体を気にしなくてはならない層は、遊郭で遊んだり妾を囲ったり、もちろん一穴主義の人もいました。外に娯楽らしい娯楽もなかったといえば身も蓋もありませんが、農村では「夜這い」に加えて、年に一度の祭りやあるいは盆踊りなどに際して、村をあげて『群婚』を営んでいます。これはどんなに規制の緩いところでも、紹介者のいないよそ者はまず入れませんでした。では何歳から「夜這い」に加えるかですが、大正の頃は、15歳くらいになると、普段の仕事ぶりに加えて、村で通過儀礼を定めておいてそれに合格したら一人前として、性も解放となっていたところが多かったようです。
こうしてフンドシをしめると若衆になるわけで、どうも昔は若衆入りの前にフンドシマワシ初め、初フンドシなどいろいろいうが、ともかくフンドシ初めの祝いをやったようだ。(中略)ところでムラによると、フンドシ初めの日に若衆を迎える家では、女房の他の者は皆、家を出てしまい、残った女房は家の戸を全部閉めてしまう。それで他の村人は、あの家は今日、ハツフンドシがくると察した。まあ昼間のことだから、いくら戸を閉めてしまってもうす明るいわけであるが、それでもなにか秘儀らしい面影がある。ムラの人に聞いても、裸になって女の人にマワシをしめてもらのだから、いくら叔母さんでも恥かしいので暗くするのだということであった。しかし、あるムラでは、マワシをしめてもらってから、性の手ほどきを受けるのだということである。昔はかくすほどのことではなかったが、今はいってはならぬことになったし、だんだんそういう習慣はなくなり、よほど古風の家でないとしないようになっていた。つまり若衆になり、一人前の男となるためには叔母たちの手で、性についての実地教育を受けたのである。私は、この種の性教育は、農村では極めて普通であったと思っている。ただ地方によって、同じ地方でもムラによって大変違う。
『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版 「Ⅰ 村落社会の民俗と差別」「9 女の民俗」89頁〜90頁より
こうした若衆の元服と、その性教育についても、ムラの女頭目の関与が大きかった。初入りの若衆を、この地方では広く「日の出」若い衆という。ヒノデに夜這いを教えるのにもムラでいろいろと違って、まあ最初は兄貴分の後をついて行き、草履の番をさせられる。だいたい半年くらいお供をしているうちに、兄貴分が今夜はお前が入れと押し込んでくれた。また他のムラでは姉妹娘の居る家とか、母娘の居る家などを選んで、兄貴分が連れて行き、自分は妹とか、娘とかを相手にし、ヒノデには姉や母親などの経験者をあてがう。またオンナ仲間、カカ仲間、ムスメ仲間などのしっかりしているムラでは、仲間たちが双方の好みや性格を考えて相手を選んでやり、夜這いさせる。他にも、それぞれオンナ仲間で相手になる女を選別し、若い衆とクジできめるのもあった。
『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』 赤松啓介、明石書店、1986年7月20日初版 「Ⅱ 非常民の民俗文化」「16 若い衆の性教育」173頁〜174頁より
徴兵制度が敷かれたこともあって、この一人前になる年齢もだんだん年齢が上がっていき、遂には、徴兵検査のある年、つまり満二〇歳に引き上げられてしまいました。徴兵検査は一斉にあるので当然一斉に筆下ろしとなってわけで、とても村ではまかないきれません。結果、遊郭が混み合って大繁盛ということになりました。もちろん要領のよい男というのはいつの時代にもいるもので、徴兵検査までに親切な近所のお姉さんやおばさんに筆下ろししてもらった者もおりました。おばさんだって人間です。愛想のよい子がいればつばを付けたくなるのも人情でしょう。この元服、筆下ろしも当然、都市部では様相がまた異なります。
大阪あたりの商家になると、元服の階層性が極めて明確になった。船場、本町あたりの豪商になると、総領が一五歳になると宗右ヱ門町、新町などの一流の料亭へ親戚、別家、分家その他を集めて祝宴を開き、その夜、一流の芸妓がソイネをして性の手ほどきをする。もっとはっきりいえば豪商の後継者としての、公務としての「遊び」の初教育であった。それ以下の商家では別家、番頭などに案内させて料亭や遊郭で遊ばせ、芸妓や娼妓が性の手ほどきをしてやる。(中略)ところで最低層の丁稚・小僧はどうであろうか、かれらが一七,八歳になって一応、商売もわかってくると「手代」に昇格した。丁稚時代は○吉であったのが×助とか△七などと、その商店の慣例の呼名(通称)に変わり、足袋や羽織を許されるようになる。着物や帯も、上等な物をくれまして、その祝いの夜、初めて番頭などが遊郭などへ連れて行き、娼妓、芸妓などと遊ばせ、性の手ほどきをさせた。しかし、そういうことをしてくれる商家はまだ良い方で、だいたいは知らぬ顔で放任する。商家といってもピンからキリまであるわけで、女中部屋があるような店なら、たいてい夜這いで教えるし、女中頭に気のきいた女がいれば、適当なときに馴れた女中に夜這いさせた。まあ、そうして気をつけてくれる人がいるのは幸福で、殆どは悪友に誘われてチャブ屋や遊郭で酌婦、安女郎に童貞献上ということになる。
『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版 「Ⅰ 村落社会の民俗と差別」「9 女の民俗」97頁〜98頁より
女性の方は徴兵検査なんてありませんので、月のものが来るようになり、身体が出来上がってくる15、6歳くらいに「水揚げ」されるのが多かったそうです。別に風俗業に売られたわけではありませんよ。女子の初めての性交を「水揚げ」と呼んだのです。下手くそがやると痛いばかりなので、こればかりはベテランに頼む村もあったとか。「水揚げ」をした男性はその後も何くれとなく相談に乗ってやったりしたと言います。心底処女性などどうでもよかったことがよくわかります。ただし、これも村で生まれ育った自作農の娘の話で、子守などで年季奉公にきていた娘は娘仲間に入れて貰えず若衆に無理矢理されて回されたという話も残っていますし、そもそも最下層の家の娘は奉公や女工に出されるので、村に残れず、出先の待遇次第になってしまいます。得てしてそういう娘の行き先は配慮もへったくれもないものです。よい面ばかりなはずは決してなく、村の負の側面もいかんなく発揮されたのが「夜這い」という村の娯楽です。
同じようなことは(引用者註、夜這いの相手をさせること)ムラやマチの製糸、織布などの工場の幼女工たちもやらされ、七つ、八つから一二、一三ぐらいまでの幼女工たちが、工場主、番頭、男工たちの相手をさせられたが、殆ど強姦といってよい。大阪府下あたりの織布工場などでは年季明けで出替わりになると、その夜に新女工の歓迎会というので男工その他が祝宴を開いてやった。その前に希望で相手を定めるが、一人、二人に集中するとクジビキなどで決める。幼女工たちは殆ど酒など初めてで、しばらくは学校唱歌などうたって元気を出しているが、やがて酔いが廻ってくると笑い出したり、泣き出すのもあった。男たちが当てられた女を抱き寄せると、びっくりして逃げ出したり、泣いて暴れるものもあるが、ともかくおさえ込まれてオンナにさせられる。一〇歳以上の女の子になると、だいたいのことはわかっているみたいで、あまり手数をかけないようだ。こうして決まると自室へ連れて行き、朝は起床させて洗顔、食事をすませ工場へ出る。昼食になると手洗いの湯を運び、食事の世話をし、終業にはまた手洗いの湯を運んで自室に帰らせて、夕食の世話をし、ねる用意をしてやった。つまりその男工専属のオンナになり、身の廻りの世話をさせられるのである。男と夜番が合わぬと、それだけいろいろと苦労させられた。半季の場合は半年、年季の場合は一年間、男の世話をさせられるわけだが、だいたい三か月もすると馴れて女らしくなる。
『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版 「Ⅱ 非常民の性民俗(ムラとマチ)」「18 マチ工場の性民俗」322頁〜323頁より
今なら工場に一斉捜査が入って全員逮捕の上マスコミにさらされ、2chで実家まで特定されて男の人生は終わってしまいますが、ここまでいくと大らかなどとは言えません。現代はさも幼女趣味が氾濫し、変態が多いように印象操作されていますが、昔の方がひどかったわけで、いかに教師、マスコミの言うことが大嘘かがわかります。
では女性たちはなぐさみものになるばかりであったかというと、これも階層の差があって、たとえば赤松啓介氏の見聞談によれば、
だんだん丁稚奉公などする者がいなくなり、三食居間つき月給、つまり住み込み店員として給料をもらう、そのかわり将来の保証はしない、ということになり、いわゆる小店員制が生まれた。定着した家もあったが、移動の激しいワタリ奉公も激増する。その頃の同僚たち、友達は親切なところもあって、次から次へとお互いに有利な商店を紹介した。着替えの風呂敷一つあれば、食事と住居は先方もちであるから手軽に変われる。そうした見聞によると、商家の女房、娘というのはかなり尻軽が多く、丁稚小僧、小店員を性の遊びに誘うのが珍らしくなかった。またオイエハン、つまり後家さんが筆下しするというのも多いようである。
『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版 「Ⅰ 村落社会の民俗と差別」「9 女の民俗」99頁より
と、かなり楽しんでいた層もあったことがわかります。もっと下層はというと、
市中の小商店や廉売市場などの零細企業の渡り奉公をやっていると、いろいろの性生活がわかってくる。丁稚小僧といっても一人、せいぜい二人ぐらいで家族経営を主体にしており、他に女中一人でも雇うと精一ぱいであった。家も下が店舗なら奥が台所、女中や丁稚部屋、二階が家族というのが平均的で、風呂などあるのは殆どなく、銭湯通いであり、夏になると行水も多い。主人も豪商奉公で訓練されたというのはいないから、経営面でも家庭面でもシツケは殆どなかった。少し景気がよくて儲かると女遊びをするか、バクチ、競馬に手を出す。そうなると夫婦喧嘩が盛大となり、一年ぐらいの間に潰れた。丁稚の教育などできるはずもなし、売り上げの管理も粗雑になるから、勝手に持ち出して遊郭で遊ぶことになる。田舎から出てきた丁稚が初めから金をごまかすはずがないので、主人がそれだけの面倒を見なければ、隣近所の丁稚仲間に誘われてみるみるうちに悪化した。女房や娘、女中も似たような環境だから、丁稚の筆下ろしぐらいすぐ誘ってやってのける。とくに夏の行水は刺激的で、女房や娘のなかには背中を洗わせるのがあり、わざと挑発しているのだ。主人がいない夜は、夜這いを誘いにくる。今夜は暑くて寝られへんから外の障子開けておく、お前がねるときに閉めておくれなどうまいこと誘う。正直に遅くなって二階へ上がると、カヤの中では急所を見せて眠っているから、外の障子を閉めれば乗るのが当然となる。しかし主人にわかると、なんにも知らんと寝ていたのに、二階へ上がってきて強姦したということになった。こんなのはすぐ飛び出せばよいので、始末がつけやすい。隣近所との交際を見ていても、実質的には田舎の夜這いと同じで、お互いにかくれて遊びをしていた。
『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』赤松啓介、明石書店、1986年7月20日初版 「Ⅱ 非常民の民俗文化」「23 御用聞きと女の性」230頁〜231頁より
という次第でした。その一方で、悲惨な人々は悲惨そのものでした。赤松啓介氏が『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』明石書店、1986年7月20日初版や、『非常民の性民俗』明石書店、1991年4月20日初版で報告されているドヤの風景は、よおく考えなくても切実です。八歳の女の子が身体を買えと言ってくるというのですから窮乏の度合いが知れるというものでしょう。
ドヤの小窓から外の通りを見ていると、シトシトと降る小雨の中を、オバハンが背中にわずかな荷を負い、五つ、六つの男の子の手を引いていく。一目でドヤを追い出されたとわかるが、今晩どこでねられることやらと思うだけでもイヤになる。この雨で傘もなしにぬれて、歩いて、どこで、どうなることやら、という世界なのだ。それがわからないと、女の人や女の子までが、兄ちゃん、わたいとねえへんと誘いにくる社会がわかるまい。アホ、毛も生えとらんのにできるんか。できるぜえ、なんべんもしとる。なんぼや。二円や。アカン、もっと負けろ。二円も出すのなら、もっと大けえ、毛のある姉ちゃんが買えるわい。なんぼくれるんや。一円。ふーん、とふくれて見せるが、これが承知の意思表示になる。まだ八つのコドモが、こうした交渉を一人前にして見せた。実際として一円はまだ高いので、まず五〇銭が相場であろう。五〇銭から一円ぐらいまでの売春で、母親と二人がどうにか暮らせたのだ。この子は八月になると酌婦見習いに売られ、母親もどこかへ消える。
『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版 「Ⅱ 非常民の性民俗(ムラとマチ)」「28 性交の解放と自由」441頁より
ここでは性は商品であり、生活の方便です。楽しんでいたはずはありません。
長雨のとき、娘を五円で買えというので、一晩に五円は高いと断ったら、身体ごとやるということになる。買ったところで、後の食わせが大へんであるし、母親のように辻占の儲けを出させるのも不可能だから、断るほかない。
辻占や花売り娘たちが一群となって、ムラの娘仲間みたいのをつくっていたが、もう早いのでは十、遅くとも十二、三までに水揚げする。大阪ではデン公という不良少年が殆ど相手だが、客や長屋の大人たちもあった。もう七つ、八つになったら相当の性知識は、実見しているので持っている。私など独身だから、兄ちゃん、チャウス知っているか、などとからかわれた。しかし、もっとびっくりしたのは掻っ払いである。店内で万引きするのと違って、店頭の商品を持って逃げるのだ。(中略)助平みたいなオヤジに店内へ引き入れられたので、前を開けて見せたらいじくってから、金をくれたので、ときどき行っていじらして金をもらってくるものもあるそうだ。ほんとかと疑っていたら、他の娘もあるそうで、うそやいうのならついて見にくるかと誘われたが、さすがに思いとどまる。その店だけは教えてくれたが、どうも幼女姦、それも水揚げしたがるのが多いらしい。五円で買わなかったが、どうせ水揚げさせるから、あんたが水揚げしてやれ、という。初めからボスやデン公を通じて水揚げを交渉するのもあり、辻占や花売り姿を見てのことだ。しかし直接に店内や家内へ引き入れて強姦するものあり、これは後からあんちゃんなどが娘を連れて脅しに行く。
『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』赤松啓介、明石書店、1986年7月20日初版 「Ⅱ 非常民の民俗文化」「28 スラム街のバクチ」283頁〜284頁より
一方では性を謳歌し、一方では性を食に変えている現実が、明治、大正、昭和と続いた戦前の時代です。窮乏の極みにあった層の子供たちこそ憐れではありましたが、大人たちはそんな中でも性交渉のルールがあって、オトコを作ったりオンナを作ったりしていたそうです。
怒った姐さんに裏へ引き出されて、さあ、お前のもんも握らせろと責められた。他の女どももわいわいいうので観念していると、サルマタの中へ手を入れて握ったが、もうかんにんしてくれと頼んでも、なかなか離してくれいない。そのうちしごきだしたので、それは約束違反や、あんたのもんもしごかせろと股へ手を入れて押し合いになった。女どもが喜んで、あんたはすぐ離したのに、姐さんはいかん。姐さんが大きしたもんは、姐さんに小さしてもらい、とけしかける。そうなると逃げもできんので女を押し倒して上になると、なにをするんやと怒ってあばれ出したが、いつの間にかうまい具合に入っていた。押さえつけられて、どうしようもなかったというかっこにしただけで、本気で拒否しようとあばれたわけではない。しばらく見ていた女どもも、他人がええことしよんの、見ててもしようがないと居なくなった。すんでから、うち、この子、オトコにしたぜえと披露、もうサカゴウチのケイコなど女を追い回す必要もなくなる。それでも他の男たちに、遊郭や悪所遊びに誘わんようにと頼んでいた。
よく誤解されるがオトコにする、オンナになるは、夫婦になることではない。主人がありながらオトコをもつ女もあるし、妻がありながらオンナをもつ男もある。片方が独身で、他方が結婚というのもあるし、いろいろの型はあるが、いわゆる情夫とか、妾とかいう関係とは違う。双方とも独立的な生活をしながら、必要なときの性的交渉を保証し、他の者よりも優先的順位を与える。その限りで男が夜這い他の遊びをしようが、女が他の男と遊んでもよい。お互いに財政その他の援助をし合ってもよいが、所有財産をひとつにしないのである。そうした関係を認知し、保証する法的規制はないが、どちらかが合意の上でオトコあるいはオンナになったことを、その周辺の人たちに宣告する必要があり、それが暗黙に認められれば、夫婦とほぼ同じにみてくれるだろう。また、双方が同意すれば、いつでもその関係を解消できる。
『非常民の民俗文化 生活民俗と差別昔話』赤松啓介、明石書店、1986年7月20日初版 「Ⅱ 非常民の民俗文化」「25 サカゴ(逆碁)ウチ」253頁〜254頁より
さて、前代みられた男色はすっかり途絶えたのかと思いきや、
さて零細工場街のボウズ、小僧のうちお稚児さん型のかわいい男を、兄貴分の男工やオヤジたちのなかには水揚げしてオンナにするのも多いが、嬶やオバハンたちも稚児型に目をつけ、筆下ろしを楽しんでいた。(中略)小僧にしてみると前は嬶どもに責められ、後は兄貴たちに掘られるので大へんだろうと思うが、よくしたもので半年もすると一人前のオトコになっていた。なかには兄貴分が手離さないのもあり、これは工場をやめさせて下宿で同棲し、女装させていたが、これも半年もするとオンナになっている。あの娘、わかるかというので、なんやと問うと、オカマやと三人で同棲、妻妾同居というわけだが、オトコになったり、オンナになったりして双方に奉仕させられているらしい。それでもオヤジのとり合いで焼き餅したり、喧嘩しているそうだ。オヤジは若いオカマの方を好きだが、女房が離れんのだそうで、まあ三角関係としてなら珍らしいわけでもない。かわいいコドモであったから、すぐオヤジが手をつけてオンナにし、同居させたのである。尋小卒で十四、五だが、桃割れにしていると十七、八の娘盛りに見えた。ボンサンの水揚げをして、そのままオンナにして同棲するのも珍らしくないそうで、そういう男工に聞くと情が深くなると、女より女房らしくなって家事もするし、焼き餅もひどいらしい。オンナですまんなあ、とオバハンに思いきりひねられていたが、あんなにうまくいっているものばかりでないそうである。
『非常民の性民俗』赤松啓介、明石書店、1991年4月20日初版 「Ⅱ 非常民の性民俗(ムラとマチ)」「20 町工場の男色」348頁〜349頁より
と、やはり今ならお縄にかかって新聞紙面を賑わすようなことがよくあったみたいで、どちらもお盛んであったことがわかります。こういう様子を考えると、日本人は本当に芯から性を楽しんでいたんだなあと思います。しかし、そういう情景も日中戦争が始まり、大東亜戦争が始まり、戦況が厳しくなって空襲が始まるとそれどころではないと消え去っていきます。いや、軍隊の中は男ばかりなので男色は盛んだったと噂には聞いていますが。
この時代を、あるいは前代を含めて指して「実質的に一夫多妻だった」という人がいますが、妾を囲う余裕があるのは、上級華族か財閥系のオーナーや経営者連中、あるいは成金とよばれた新興企業のオーナー、地方の地主、あとは高級官僚くらいでした。そんなことを言う人は、実際に妾を囲えたのが、国民全体の何パーセントだと思ってらっしゃるんでしょう。例えば、第十三回衆議院議員選挙で選挙権を得た人は、直接国税(地租または所得税)を10円以上納めている満25歳以上の男性でしたが、全人口中25歳以上の男性は、大正7年推計値で、12,476,424人、うち選挙権を持っていたのは、1,422,126人ですから、全体の11.4%でしかありません。地価に直すと四百円で、田畑に直すとおよそ十二反以上ということで、まあ食べるのには困らないという広さでしかなく、妾を囲うとなると、その倍はいるでしょう。となると5%もいないわけで、全然一夫多妻ではありません。社会通念的には妻は一人(性的に関係を持つのは無制限)だったわけで、ごく一部の上流階級の有様をみて全体を歪めてみるという愚を犯しています。
敢えて言うなら、群婚的一夫一婦制でしょうか。もちろん「夜這い」のあり方は地方、村、町ごとに違いましたから、一概には言えませんが、最大公約数を取るとそんな言い方になると思います。
現代
現代は、一夫一婦制であると多くの人が疑いなく思い込んでいます。確かに同時には一夫一婦しか法律では認められませんから、そう言えなくもありません。ではその法律を見てみましょう。まずは日本国憲法第二十四条からです。
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
次に婚姻の具体的な要件を定めている民法を見ます。「第四編 親族」「第二章 婚姻」に規定があります。
第七百三十一条(婚姻適齢)
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。第七百三十二条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。第七百三十三条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止) 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止) 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意) 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。いやあ、今でも結構色々定めてあるものですねえ。離婚や相続に関する条文まで引用すると煩瑣になりすぎるので婚姻とその開始に限って抜き出しましたが、それでも6つあります。第七百三十三条は女性の婚姻の権利を侵害するものだとして無効を訴える人が少なからずおられますね。それはともかく、第七百三十二条、第七百三十四条〜第七百三十六条までは今や当然と認識して疑問を抱く人の方が少ないのではないでしょうか。直系はもとより兄弟姉妹、オジ、オバ、甥、姪と婚姻はもちろん、性交渉を持つことを忌避するのは一般的な感性でしょう。逆に養子であっても兄弟姉妹は結婚できないと誤解している人が多いことに驚きます。養子の場合兄弟姉妹と婚姻ができるとしているのは明治時代から続いています。でないと婿養子が取れません。案外見逃されているのが離婚した後、元夫または元妻の連れ子だった息子、娘とは結婚できないという点でしょうか。
常識と化して気付いている人が少ない点として、禁婚範囲が先進国の中では比較的狭い、つまりタブーが少ないという点です。いとことは結婚しないとするタブーはごく当たり前に見られる禁婚観ですが、日本はイスラム諸国と並んでそれを認めている数少ない国の一つです。禁婚が極端な例は韓国にあります。もともと韓国は同姓同本貫は禁婚です。あまりに厳しすぎるということで現在は改められていますが、避けられるものなら避けるのではないでしょうか。また、同姓不婚は中国が本家本元です。中国が夫婦別姓なのはそのタブーを犯していないことを明らかにするためであり、別段何か進んだ夫婦観念があるわけではありません。この同姓不婚というタブーは上古の族外婚から続いているものだと推定できます。族外婚の場合、他族から夫または妻を迎えなくてはならないので、必然的に同姓=同族は禁婚となるのです。春秋時代には既にこのタブーは確立していましたから、その淵源は相当に古いと見なさざるを得ません。
それはともかくとして、両性の合意だけで婚姻が成立するのですから、その点は『妻問婚』に回帰していると言えます。『妻問婚』だって貴族はともかくとして、誰も彼もが一夫多妻だったわけではありません。『魏志倭人伝』にもあるではないですか。「下戸或二三婦」「庶民でも二人、あるいは三人の妻を持つ者がいる」と。多数派は一夫一婦だったのですよ。それに『妻問婚』だって「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」という点では同じでした。その意味では、『妻問婚』回帰と言ってしまっても問題がないように見えます。
しかし単純にそう言い切ってしまえない側面もあります。それは「個人主義」の擡頭です。「個人主義」は欧米に端を発するのですが、日本にもその価値観がなかったわけではありません。しかしこれが普及したのは、戦後になってからです。日本国憲法は、既に個人主義が普及していたアメリカの意向が反映された憲法であり、もちろん「個人主義」をうたっています。憲法で保障されている「両性の合意に基づいた結婚」は「個人主義」を基本に据えたものなのです。氏族のバックアップのあった『妻問婚』とはそこが大きく異なります。
ところで日本では、互いの協議で離婚できる、あるいは裁判所の裁定によって離婚できるので、実は厳密には一夫一婦制とは言えません。本来の一夫一婦制は「二夫に見えず」ですから、死ぬまで離婚できません。カトリックは今でも離婚を認めていません。そのため、カトリック教国の多くは離婚の要件が厳しいものになっています。元来の一夫一婦制の場合、浮気したら妻は厳罰に処せられます(国によっては死刑)。婚前交渉など論外という制度です。婚前交渉、婚外交渉についてはイスラム教も厳禁しています。そのため、特にイスラム原理主義を掲げる国ではむち打ち刑(たいがい死にます)にしたりするところもあります。それに対して現状の日本は、何の罰則もないどころか、誰の同意も必要としない「個人的」密議で離婚が成立してしまいます。これを併せて考えると、日本は逐次的もしくは継次的多夫多妻です。厚生労働省の統計にある離婚件数の年次推移を見ると、2002年をピークに近頃は減少気味とは言え、離婚は増え続けています。また、各届出年に同居をやめ届け出た離婚件数の割合の年次推移を見るとこれも同じ傾向です。結婚してすぐ離婚する人が非常に多いことがわかります。これをもう少し正確に見るために同年同居の年齢別婚姻率の合計及び同年別居の年齢別離婚率の合計の年次推移を参照して下さい。男性、女性とも増加傾向にあることがわかります。同居期間別にみた離婚の年次推移を見ると、結婚20年以上の夫婦の離婚率が上昇しているのが何かもの悲しくなります。まあ、統計を見ても明らかな通り、現代は三組に一組が離婚するというご時世です。いずれアメリカのように二組のうち一組は離婚するような事態になるんでしょうか。
宗教も危機的状況を迎えています。統計数理研究所の「現代日本人にとっての信仰の有無と宗教的な心 —日本人の国民性調査と国際比較調査から—」によると、「信仰がある」と答える人は年々減少しています。20歳代はもともと低いのですが、それ以上の層が軒並み低下しています。「信仰はないが、宗教的な心が大切だ」とする人も減少しています。特に20歳代の減少が著しいです。「宗教に肯定的な人」も減ってます。オウム真理教などカルト団体が危険視されるようになったことも関係するのかも知れませんが、若者は宗教に救いを求めていないことがよくわかります。かつては祖霊を同じくする血族の紐帯が生きるために必要でした。その意味では生きやすい世の中になって宗教に注意を払う人が少なくなったとも言えます。従って宗教の戒律で婚姻を制御することも不可能になっています。
いずれにせよこの傾向は続き、将来は一生のうち二、三回は結婚するのが普通といった事態になるのかも知れません。先程は逐次的もしくは継次的多夫多妻と述べましたが、これに十代から二十代の恋愛期間を加味すると、実態は既にそうなっていると言っても過言ではありません。婚姻の意味は性交の相手を決定することにありますから(家族制度は後からついてくる)、二股をかけるのがモラルに欠ける行為と通念されているとはいえ、恋愛といいつつ、実態は通い婚と変わりありません。一部は乱婚といってもよいでしょうが、さすがにまだ一般的だと言えるほどではないと考えます。
今時「見合い結婚」をできる人はおらず(というか「お見合い」をセッティングしてくれる奇特な人がいない)、結婚に至るには恋愛が第一ステップになってしまった観があります。そうなると恋愛は誰にでもできることではないので、ドロップアウトしてしまう層が現れます。え? 恋愛って誰にでもできるでしょ? と思ったあなた。それは間違いです。人間のやることでなにがしか訓練を経ずに上手にこなせることなど皆無といっていいでしょう。誰でも喋っている言葉も赤ん坊の頃からインプットされ続けて、自分も喃語から片言の言葉を経て喋られるようになっているのです。従って、恋愛を上手に行う訓練を自分に課すことがあるいは両親から課されることがなかった人は、恋愛ができません。従って婚姻率は下がる一方ということになります。これも厚生労働省の人口動態統計からわかります。婚姻の推移を見ると、婚姻率はピーク時の半分にまで落ちているのがわかります。
これには婚姻を強制する社会圧力が非常に弱くなってしまったことも一因があります。その原因は「個人主義」にあります。昔は男性も女性も一定の年齢に達したら結婚するもので、逆にしないのは何らかの故障を抱えているためだとごく自然に思われていたのです。結婚適齢期という言葉は、この間に結婚しろという露骨な圧力でした。ところが「個人主義」の浸透が進むにつれ、結婚は「家」の行事ではなく「個人」の私事とされていったのです。「個人」の私事ですから他人の詮索するところではなくなり、その結果、今や親でさえ、結婚しろとは言っても、その相手を探してくるということがありません。それに加えて、恋愛至上主義価値観のせいで「お見合い」結婚がなくなってしまったのがその最大の原因です。婚活といって相手を探すのに血道を上げている人がいるではないかと思う人がいるかも知れませんが、紹介された人に不満がなければ結婚するという「お見合い結婚」と相手に不備がないか精査した上でおつきあいし、それで問題がなければ結婚する「婚活婚」では意味が全く違います。あれは恋愛感情を伴わない恋愛結婚のようなものなのです。
戦前の日本が結婚に恋愛など必要としていなかったことは既に述べました。いつからなぜこうなったのでしょう。『家父長婚』で示したグラフを見ればわかる通り、どこかに画期があったわけではありません。最初はお見合いも盛んだったのに、だんだん恋愛が前面に出てくるようになったのです。これは何かのイベントがあったためではなく、教育による「個人主義」と「恋愛至上主義」が浸透した結果です。戦前の事物の全否定から出発した戦後の日教組教育に「個人の自由と平等が至高の価値」「恋愛こそ至上であり婚姻に必須の過程である」というイデオロギーが組み込まれており、それをマスコミが盛んに煽ったためです。この気味の悪い恋愛イデオロギーはキリスト教の一夫一婦制価値観に基づいた近代「個人主義」最大の爆弾です。
学校では別に恋愛のことなんて習わなかったけど? と仰る方も多いでしょう。確かに直接的に恋愛を教えることはありません。では何が問題かというと、学校教育によって、元来日本では解放されていた性が封鎖されてしまったことに根本の原因があります。今時「夜這い」や『群婚』を営んでいる地域などありますまい。いやひょっとしたらどこかでは残っているかも知れませんが、暗黙の了解として国民皆が知っているというものではなくなっています。性を不潔なもの、子供が触れてはいけないものとして徹底的に排除し、性を教育するものがいなくなってしまったため、思春期になっても性衝動だけがぽつんと取り残されてしまう状況に陥ったのです。その一方で「個人の自由と平等」だけは高らかに教え込みます。これをどう解決すればよいでしょう。性衝動を個人的な感情に落とし込められ、しかしその「個人」は最高と教えられるのです。答えは「恋愛」です。「個人」の感情の発露としての愛情が最上級の位置づけを受け、日々教え込まれるのです。思春期の男女にとって愛とは「恋愛」です。その「恋愛」と「性愛」は不可分なのですから、「恋愛」が免罪符となって秘密の性交渉を可能としたのです。「個人主義」の極致である恋愛の素晴らしさを直接説き、広めたのはマスコミです。しかしその一方で婚姻を伴わない性交渉を「不純異性交遊」と呼び、不純で不潔なものと決めつけ、結婚するまでは処女でいることを日教組(と文部省)は教え込んだのです。それで悩まないのは悟りを開いたお坊さんか、仙人です。民法では十六歳から婚姻できることを保証している(2022-11-03 追記 現在、婚姻可能年齢は女性も 十八歳に引き上げられています) のに、現在の高等学校で生徒の婚姻を受け付けるところはありません。実態として婚姻できないのです。本来ならこれは人権侵害も甚だしい不法行為です。にも関わらずそれが認められているのは、教師自体が「恋愛こそ至上であり婚姻に必須の過程である」というイデオロギーに支配されており、「性を不潔なもの」として蔑視しているからです。かくして恋愛イデオロギーは再生産され、マスコミはそれが金になることに気付いて盛んに煽り、ますますその再生産を助けるというサイクルに陥ったのが、戦後の婚姻史の一面です。
この恋愛賞賛には文学者も多大な貢献をしています。戦前の白樺派でも特に谷崎潤一郎が有名ですが、別に彼に限らず戦前でもロマン主義文学者は恋愛を何か神聖なもの、あるいは無上の価値を持つものとして描いていました。そして家制度によってそれが挫折する様子まで。あるいは不倫の破綻という結果で。学校指定図書で感想文を書かされた人も多いはずです。これが戦後になると恋愛賛歌とでも言うしかない小説が量産されるようになります。マンガだって思春期以上の男女を対象としたものは大抵恋愛賛歌です。そんなものを読まされたらそりゃ洗脳されますよ。恋愛に至高の価値を認めるということは、これを以て全ての罪が贖われるということでもあります。好きなんだから身体を許しても仕方ない。好き合ってるんだから心も体もひとつ。それを邪魔する者は「個人主義」を侵すものであり、大罪人です。かくして秘密の性交渉で性衝動を発散させることになります。ばれたら「不純異性交遊」ですからこっそりと。ところが教師はおかまいなしです。好みの女生徒がいれば、ぱくっといってしまいます。教え子と結婚した教師がいかに多いかご存じでしょう。在学中に孕ませてしまって、女生徒は退学、ひっそりと式を挙げたなんて例もあります。生徒には「不純異性交遊」として禁じておきながら自分は立場を利用して女生徒で遊ぶ教師が最近よく紙面を賑わしますが、これ昔からずっと同じだったと言ったら驚きますか。別に今の教師だって大多数は真面目ですが、自分たちで作ったタブーを自分で破るというのは生徒がタブーを破るよりタチが悪いものです。このねじくれた特権意識(オマエは禁止だがオレはOKという俺様意識)はサヨクに特有の権力妄執が生みだしたものですが、それはさておき。
近代は封建制度から家父長制を生み出したわけですが、この「家」を基盤に据えた男系継承のための制度は、大体数の民衆が相続だの継承だのとは無関係であった時代にはよく機能しました(オーストリア・ハンガリー帝国や大英帝国では血脈の継承を尊重するあまり女性に帝位を継がせるまでになります)。しかし、「市民」と呼ばれる資本家が庶民の中で力をつけてくると、それまで事業主の血縁や従業員、居候、女中、下男下女といったメンバーで渾然となっていた家族から「家庭」という事業主の直接血縁者だけで構成された単位を分離する動きが表面化してきます。それは庶民の中でも自分たちを他の庶民から区別し、主権の担い手としてふさわしくあらんとした自尊の表れでもあり、庶民と資本家が異なるものであることを目で見て示す端的な方法であったからです。それと同時に近代資本主義が勃興し、機会の均等平等を要求する一大勢力になります。その要求の拠って立つ基盤こそ「自由主義」「平等主義」にありました。これにより、王侯貴族と自分たちを相対化したのです。この新しい勢力と旧来の王侯貴族の対立がやがて資本主義革命へ繋がり、資本家勢力が勝利するわけですが、それは直ちに「家庭」における家父長と他の血族の相対化をもたらしました。社会的な存在であったそれまでの大家族から切り離された「家庭」においては家父長も一個の人間でしかなく、その権限の及ぶ範囲が息子や娘たちからは見えなくなります。そうなると、家族から見た場合、家父長権は専ら消費、結婚にふるわれるようになりました。結婚の場合、子は当事者ですし、消費活動に家父長も家族も変わりなどありません。従って、家父長権の行使は家父長個人の行為と等しく見なされるようになり、そうすると家族個々がこれに対抗して、消費、結婚を自己の意思で行えるようになることを望むようになります。つまり「家の私有」ではなく「個人の私有」を主張し始めるわけです。そしてそこから「個人主義」が芽生えます。家父長が一個の人間なら「家庭」における家族もそれぞれがまた一個の人間なのですから、この二者の関係は相対的なものになり、家父長とその他家族をさらに「個人」に還元し、相対化した「個人主義」によって家父長権は打破されたのです。この「個人主義」を支えるイデオロギーは、元来資本主義に内包されているものでした。王侯貴族と自分たちの関係を相対化することにより、その特権を剥奪する権利があるとしてそれを行動に移したのが資本主義革命ですから、その縮小再生産が資本主義内部で起こることは必然だったのです。婚姻において「個人主義」を貫徹するということは、旧来の血縁や地縁、その他社会的動機に基づいた家父長の采配による婚姻を拒否することになりますから、これにかわり新たな婚姻倫理を作り出さねばなりません。ところがすべて「個人」として相対化されてしまったのですから、ある特定の男女を結びつける社会的な動機も失われてしまったのです。そこで、基本に立ち返り、キリスト教の基本規範であった「愛」がクローズアップされることになりました。そもそも恋愛は婚姻とは別個の男女間で営まれる社会的制約から無縁の行為でした。その意味では「自由」であり「対等」だったのであり、さればこそ宮廷や貴族のサロンで華やかな恋愛劇が繰り広げられたのです。ところが「個人」の社会的役割(父である、資本家である、王であるなど)を捨象して「個人」の営みとして婚姻を再定義するにあたり、それを「個人」に内在するものから生じたものの結果として婚姻もまた再定義する必要がありました。となると社会からの要請や制約に関係なく営まれた恋愛だけがその条件として残り、かくして男女間の間に生じる愛情こそ婚姻の契機であり、理由であり、婚姻に至らしめる過程であるとされたのです。これ以外の理由による婚姻は「個人主義」を侵す社会なり、親族なり、家父長なりという集団論理による奴隷的強制であると批判され、恋愛の崇高さ、純粋さを至高のものとする「恋愛主義」が花開いたのです。
しかし、社会過程を捨象したイデオロギーであるだけに、「家庭」も「恋愛」もその始まりから機能不全を起こし、多くの悲劇をもたらしました。それまで庶民の多くは、血縁なり、あるいは地縁なりに基づく紐帯で結ばれた集団によって生活が支えられていましたが、その社会過程を捨象するのですから必然的にその助けを得られないことになります。別段庶民が「個人主義」に染まったわけではありません。しかし、資本主義による収奪は激しく、そのために無産者が没落して都市にスラムが発生しても、「個人主義」的観念からすればそれは「個人」や「家庭」に内在する問題が引き起こした事態であり、社会に責任はないものとされる結果に結びついたのです。ただ憐れみから「個人的」な救恤対策が行われる場合もありましたが、それだけです。とても貧者の救いとなるものではありませんでした。「恋愛」を経ない婚姻は個人主義的でないがゆえに「不幸」であると再定義され、そしてまさにそのために「不幸」な夫婦が生まれたのでした。たとえ燃え上がるような「恋愛」を経て結婚したとしても、そもそも「恋愛」が終生続くことなど誰も保証していません。それどころか、かつて「恋愛」は一時期の戯れにすぎなかったのであり、時の経過と共に炎は鎮火し、焦がれるような思いは忘れ去られていきます。「恋愛」が結婚と結びつけられてもそれは変わりません。キリスト教は別段恋愛せよと教えているわけではなく「愛」を持てと言っているのですが、「恋愛」を経た人々は熱の引いたその状態を「愛が冷めた」と誤解し、やはり不幸になりました。また、「個人主義」が社会を捨象したからといって、社会そのものがなくなるわけではなく、「個人」は社会で期待された役割を果たさなくてはなりません。社会が発展し、規模を拡大するにつれ、それまでは互いに関与しなかった人々が関係を持つようになります。「恋愛」は「自由」「平等」ですからそれまではあり得なかった人たちの間にも起きるようになり、社会的要請が異なる人々(昔はこれを「身分違い」と言いました)を結びつけることもありました。うまくいった結婚もありますが、失敗に終わった結婚もまた数多くあったのです。
生殖と勤労、そして死という人生の主要過程は、古代の氏族共同体、中世から近世にかけての地縁共同体が丸抱えで面倒を見ていました。資本主義はそのイデオロギーの命じるまま、そのうちの「勤労」だけを取り上げ、他を捨象しました。「個人主義」はそのイデオロギーの命じるまま、そのうちの「生殖」だけを取り上げ、他を捨象しました。ヒトの人生は分割された挙げ句、誰もが避け得ない「死」を取り上げるものがなかったため、これを観念的に恐れ、病的なまでに遠ざけようとします。「死」は人生の終焉ではありましたが、それは決して最初から汚物にまみれ、苦痛にまみれた忌むべきものであったわけではありません。最も荘厳な、死者を以て生者の物語へと昇華するプロセスだったのです。しかし、社会から「家庭」と「仕事」を分離し、しかもそれぞれがまた分離している状態は人間が異なる役割を使い分けることを要求するだけでなく、それぞれが互いに不干渉であることを求めました。しかしひとりの人間の単なる別側面をそのように綺麗に分離することなどできるはずがありません。ヒトの生は常に不協和音に満ち、そこから逃れようとあらゆるものが流行しました。しかし社会基盤から生じる不協和音を小手先の教義や方法論で解決できるはずもありません。これも不幸な側面です。
かつて華やかな「自由恋愛」はお話の中だけのことで、現実ではありませんでした。しかし現代、それは「現実」であることを求められています。日本がまだ貧しい時代は、豊かになることが最優先目標でした。何も考えずがむしゃらに働いていればそれで充足されていたのです。「日帝」「米帝」「シホンシュギガー!」と戯言を垂れ流し左巻きの頭で最先端を気取ったフリをできたのは暇な学生連中だけです。しかしそれも豊かさが達成されてしまうと急速に萎んでしまいました。残ったのは豊かにはなったけど…という「現実」です。そんな中で性は放置され、個々人が好き勝手にしかしこっそり処理することが求められています。性を安易に得るためには性風俗のお世話になるのですが、これも性を封鎖したため価格が暴騰しており、ただでさえ世代間格差で賃金の少ない男にそう何度も手が出るものではありません。まして未成年であれば利用するだけで問題視されます。ところが現在になって「個人主義」のしっぺ返しが始まりました。性が高い価値を持つ=お金になることに気付いた少女たちがその売買を始めたのです。「自分の身体を自分の好きなように使って何が悪い」まさしく「個人主義」的主張であり、誰もこれに反論できません。若年期の性行為は身体に悪いからとか、性病が怖いからとか、いったい何の根拠があるのかわからない意見が新聞紙面を飾りましたが、当然の如く無視されました。「個人主義」を骨の髄までたたき込んでおいて今更慌てても手遅れというものです。同様に「個人主義」的観点から快楽の追求に走る女性も出てきます。高校生の童貞、処女率はどんどん低下しています。初体験が小学生の時だったという子も増えています。「個人」の勝手でしょ。と言われて説得力のある意見を出せますか? ところがややこしいことに、若年男性の処女信仰は年々強くなっています。性が貴重なものなら、手垢のついてない商品を選びたいという、これまた買い手としては当然の要求です。性に奔放な女性を「ふしだら」「淫乱」「ビッチ」「売女」と年寄りだけでなく若者自らも蔑視する風潮は、毒されきってて自浄不可能ではないかとの思いにすらさそわれます。なぜ自分のようなものを相手にしてくれてありがたい女性であると拝まないのでしょうか。不思議すぎて言葉もありません。そのせいで、生涯未婚率は女性で
10.61%17.8%、男性で20.14%28.3%にも達し、「現実」に適応できないでいる人が多数に上ることを示唆しているにも関わらず、最近の独身男性の処女信仰熱は衰えるどころかますます盛んになる一方です。本当のところは、性的な経験もそれほどなく、性に自尊ではあるが性の自信はない弱気の裏返しと私は見ているのですが、如何なものでしょう。性的にも鬱屈し、社会的にも世代間格差や労労搾取と呼ばれる収奪にあって鬱屈し、他方未来へ展望が開けているかというとそこも不透明極まりない。この閉塞感は若者が全体として共有している空気だと思います。この、現代日本に蔓延する閉塞感は、ヒトの人生が様々な局面にばらばらにされて放置されていることにその淵源があります。従って、近代「個人主義」に立脚している知識人はこれに回答することができません。ではどのように解決すべきでしょうか。企業が何とかしようと考えるなら、「生殖」「勤労」「死」というヒトのすべてを受け入れなくてはなりません。血縁でもない、地縁でもない新たな共同体の設立が求められているのです。今の企業は「勤労」だけ取り込んでなおかつこれの「正」の部分しか利用しかしていません。働いたら疲れるに決まっています。しかしその解消はすべて「家庭」に丸投げです。「生殖」ももちろん丸投げです。今の企業には、部下の結婚を世話するような熱心な御仁すらおりません。「死」となると、それが現実に近くなる前に「定年」と称して放り出してしまいます。少人数の「家庭」にそれを引き受ける余裕があるはずもなく、今度は公共機関に丸投げです。言葉でなんと取り繕うとも「生殖」「勤労」「死」のすべてを包含できない集団は歪でカタワの集団です。そんなものの存続を第一義とする理念—近代資本主義と「個人主義」—に私たちは支配されているのです。そんな歪な集団しかない社会はこれからどうなっていくのでしょうか。
今の時点で想定できる未来像は、婚姻できる層と婚姻できない(恋愛できない)層の二分化です。婚姻できる者は複数回経験し、事実上の多夫多妻制へ移行するでしょう。一方、婚姻できない層はどうするでしょうか。極論を言えば、そもそも恋愛の難易度が高いのは、性の価値が高すぎるからです。従って性の価値を日用品レベルまで落としてしまえば、結婚に焦る必要はなくなります。まあ別の意味で上手下手が問われるでしょうけど。つまり男女が出会えば挨拶代わりにセックス、ストレスがたまったら合意のとれた相手とセックス、めでたいことがあればご祝儀代わりにセックス。という状態になれば、誰も結婚を焦らなくなります。それでは乱交ではないかという意見もあるでしょうが、子の養育という大問題さえクリアできれば別段問題はありません。日本人のほとんどは無産階級ですので、相続にもごく一部が抵抗するだけで他はどうでもいいでしょうし。相手構わず股を開く女性をビッチだのヤリマンだの言う人は多いですが、自分にその機会が廻ってきたら嬉々として交わうんですから、意味のない処女信仰などさっさと捨てなさいと言っておきます。もともと日本には処女をありがたがる風潮はなかったんですから。しかしまあそれが極論であることは認めます。
ならば、恋愛に拠らない婚姻を模索するしかないでしょう。また、恋愛できない層が結婚できないのは、婚姻圧力が非常に弱まっているからでもあります。そこで、婚姻圧力を強力にかける、つまり法定年齢を指定して、それまでに結婚できなければ強制的に任意抽出した相手と結婚させる案もありますが、しかしそれでは形だけ整うだけで内実が破綻しますから意味がありません。おそらく彼らのうちから新たな婚姻形式が誕生し、それに伴い家族形態も一新されて社会が変わっていくと思われます。
企業はどうなるでしょう。利潤追求のみに特化した企業は、かつて戦闘に特化した掠奪集団そのものです。戦闘には強いのですが、社会生活全般は支配下に置いた部族の奉仕なしには成立しなくなっていました。現在、下請けと称する支配下の企業集団に支えられている大企業の姿そのものです。奴隷がいつまでも奴隷でいてくれれば安泰ですが、そうでないことは歴史が証明しています。奴隷の反乱が相次ぎ、遂には外部の集団に倒されてしまうでしょう。今ほど起業が楽な時代はありません。優れたアイデアひとつで会社を興すことができます。資本金すらいりません。第三次産業でも情報を取り扱う企業は経費がさほどかかりません。さらにはアイデア勝負で一旗揚げることができます。少しずつその動きは始まっており、やがて大きなうねりになるのではないでしょうか。その時、企業はどうやって優秀な人材を手元に留めておくのでしょう。
でも「生殖」と「勤労」だけでは不足です。ヒトはすべからく死ぬことが決まっています。「死」を包摂しないと充分ではありません。当然その「死」の前に訪れる「老い」はもっと重要です。老いて役立たずになったんだからすぐに死ねというのは簡単です。原始、ただ食っていくだけでも大変だった時代に「老い」は存在しませんでした。老いる前に死んでいたからです。ヒトが「老い」ることができるようになったのは、日本でいうと弥生時代、やっと農業生産が軌道に乗った頃です。『魏志倭人伝』に「其人壽考或百年或八九十年」「そこの人々は長生きで、中には百歳になるひともいる。八十、九十のひともまたいる」とあるので、少なくとも豪族=支配者層は現在とさほど変わらない寿命であったことがわかります。弥生時代の十五歳時平均余命は、出土骨から三十歳くらいあるいは四十歳くらいと推定されているはずだと仰る方もいらっしゃるでしょうが、社会上層部と一般庶民で寿命が大きく異なるのは別に日本に限らず、世界中で見られる現象です。お隣の中国も春秋時代、士大夫層(所謂支配者層)と庶民で倍近い寿命差があったことがわかっています。それはともかく、当時の日本は氏族共同体が社会の基盤になっていました。当然「死」も共同体の出来事として包摂されていたのです。それは、惣村制に移行しても同じでした。村八分から葬儀が除外されていたことからもわかるように、「死」は共同体の祭祀であったのです。新たな方向性を示すのであれば、当然現在は見失われている「死」をも包摂した集団が指向されねばなりません。「死」を以てヒトの生は完了するのですから。
では「生殖」「勤労」「死」を含む集団としてどのようなものが考えられるでしょうか。
ひとつ考えられるのは、太古にあった『族内婚』の変形としての「会社単位での婚姻」です。性の価値を低くすることが前提ですが、相手はローテーションまたは総当たり、あるいは任意で決定し、産まれた子は母子共々企業が面倒を見ていく制度です。企業や勤め先がその生命を長らえようと思ったら、構成員の意思を無視できません。現在「老い」や「死」といった不可避な課題から企業は逃げ回っていますが、その負債を抱え込まないと存続できない状況が到来します。若者の数は減っていますからね。経済規模を縮小したくなければ雇用関係を多少いじくった程度ではどうしようもなくなるのが目に見えています。むしろ、雇用の流動性が増せば増すほど組織を支える人材の確保が困難になっていきます。無限に給与の額を上げることはできませんから(ここ二〇年で見ればむしろ下がっています)、それ以外の点で若者を惹きつけないと組織は老化して死に絶えます。作れば売れた時代は完全に終焉しており、若者の消費性向は大幅に変わっています。もちろん消費を拡大しようにもお金がないこともその理由で、お金がないから結婚もできないと嘆いています。そんなことはないんですけどね。でも言い訳に使われるくらい世代間格差や労労搾取が激しいので、そのツケをいずれ払わされます。払いきれない企業は潰れるだけです。
もうひとつ考えられるのはさらに太古の『族長婚』に回帰することです。結局結婚できないんだから意味がないだろうと言われそうですが、勤め先のリーダーになれば恋愛がうまかろうが下手だろうが女の子が寄ってくるとなれば、恋愛の上手下手は関係なくなります。勤め先の選択もシビアになりますし、見込みがないとなればすっぱりやめられます。おそらく大幅な雇用流動性も確保できる(イイ女を求めて男が企業を点々とする一方で、イイ男を求めて女も企業を点々とする)ので、お勧めです。仮にやっぱりダメだったとしても同類がたくさんいるんですから諦めもつくでしょう。ダメ?
あるいは、現在では想像もつかない画期的な組織観念が誕生し、現在の国家や企業といった組織体に取って代わるかも知れません。さすがにそこまでは我々の生きている時代には到達できないでしょうけど。いずれにせよ、ヒトは不可能課題を前に懊悩し、試行錯誤を繰り返し、その果てにかすかな希望と可能性を見いだして生きてきたのであり、ここまで発展することができたのです。結婚できない層がどんどん増加し、このままでは国家の存続自体も怪しくなるでしょう。この、どう解決すればよいかわからない未明の課題に懊悩し狂おしいほどの錯乱の果てにかすかな希望の光を見いだす人は現れるでしょうか。かつての人類は不可能課題に挑戦し続けて種を生きながらえさせてきました。再びそのような時代がやってこようとしているのです。
現在に続く一夫一婦制は、ユダヤ教の教義にさかのぼれます。モーセの十戒には姦淫を戒める言葉があります。おそらくそれ以前から姦淫は禁じられていたのでしょう。イエスはもっと厳しく「姦淫の心をもって婦人を見ること」すら姦淫の罪を犯すことであり、戒めねばならないと説きました。モーセの十戒に姦淫の罪があることは、当時姦淫を行う風があったからで、そこから一夫一婦制であったことがわかります。おそらくこれが一夫一婦制の始まりでしょう。モーセの出エジプトは紀元前13世紀の頃ですから、少なくとも三千三百年の歴史と言うことになります。人類五百万年、あるいは八百万年の歴史においては須臾の間の出来事です。これが西欧に広がり、近代まで支配していた一夫一婦制観念に昇華するのは、キリスト教が覇権を握る中世のことです。婚前交渉を許さず、結婚までは処女であることが妻には求められ、生涯つれそうことを誓わせたのです(つまり死ぬまで離婚できない)。中世は一般的に五世紀から十五世紀を指しますから、今から1500年前のことになります。これはそれだけの時間があれば、一夫一婦制を覆せることを意味します。人類の太古の英知の前では一瞬のことではありませんか。
希望は常にあります。既に崩壊の兆しを見せている現在の婚姻制度に社会を支える力はなくなってきています。新たな展望はいずれ近く示されることになるでしょう。
–
- 2013年7月19日 初版
- 2013年7月26日 改訂
- 2022年11月3日 部分改訂
と平安貴族の場合を例にとって書きました。形式化が進むと共に、式次第も細かくなり、この他にも政所始やら行始やら色々あるのですが、きりがないので省略しました。肝は新婦の父が新郎に対して(もちろん遠回しに)求婚する点です。父親が積極的に関与してくる風は、婚姻は父が主催するものという世間の風が反映したものだと思われます。これに関連して、高群逸枝氏の主張する婿取婚を批判する一連の議論を見ていきたいと思います。
まず、『女性史研究 第1集』家族史研究会、1975年12月1日発行に掲載された「奈良時代の夫婦同居制をめぐって —洞富雄・高群逸枝の論争—」と題する論文(13頁〜22頁)です。著者は緒方和子氏です。この中で著者は洞氏の高群氏に対する批判として、以下のような点を挙げています。
1. 古代は既に嫁入婚だった
洞氏『(前略)中国正史である『隋書』のなかの文はつぎのとおりである。「男女相悦者即為婚 婦入夫家必先跨火乃与夫相見」洞氏は、「この一文はまことに貴重な資料である。(中略)それはともかくこの一資料によって、大化前代におけ娶嫁婚の存在は、いまやその確認をえたというも過言ではなかろう」』
高群氏『(前略)父系近親婚(異母兄妹婚等)は、当時のわが世俗としては周知のように禁忌されてみらず、記紀、万葉集に数多くみえている。(中略)母を基本としての家族観念であって、招婿婚が支配的野制として継続している期間中(南北朝頃まで)は、この俗もしだいに衰えながらも尾を引いて存続していることは、拙著の各章でみていると澄りである。(中略)あまり前段と後段の記事が矛盾するし実俗ともちがうので、資料の錯入かと疑ってとらなかったのである』
洞氏が『隋書』の記述により既に娶嫁婚に移行していたと結論するのは、当時の社会階層(身分)差や地域差を考慮しない暴論であり、高群氏の反論も「これを無視した」ということなので、両方ともいただけません。当時の俀國(倭國)の大夫(貴族)層では中国との交流が長く続き、嫁取りの習俗がが取り入れられていた。しかし、庶民やその他の地域(ヤマト王権の支配地域など)は『妻問婚』や一部『婿取婚』であった。と素直に解釈すべきでしょう。ただし、その習俗が他に全く影響を与えなかったというのも考えられません。嫁取りの観念は家父長制と不可分ですから、俀國(倭國)の大夫(貴族)層では家父長制へ移行していた可能性もあると思われます。
2. 夫婦別居婚から直接父処婚へ移行した
洞氏『婚制が夫婦別居婚から父処婚(嫁取婚)へと展開したことは明白な事実である。氏の云う「実験的過程」をたどったのでなく、父処婚への転換の時期も一概にはいえないが、けっして鎌倉初期というほど後期ではなかったことはすでにみた通りである。(中略)すでに父権時代にはいり、父系思想も滲透しつつあった平安朝農民に、労役婚の発生をみたというような時代錯誤が果してそのまま認められるであろうか。(中略)高群氏はこの貧窮問答歌に対して、父母同居的な同居(娶嫁婚)を示すものでなく、父母が息子夫婦の家(婿取婚か—洞記)に寄食しているのではなかろうかという解釈をされているかと思えば、一方では妻の父母でもありうるであろうという見方もたてている(『招婿婚の研究』二四五頁〜二四七頁)。このような持って廻った解釈は牽強付会といわざるを得ない』
高群氏『(前略)南北朝頃まで招婿婚と並存、もしくは招 婿婚を特殊視すべく圧倒的な他の支配的婚姻形態をみいだしえなかった。したがって洞氏がいわれるような招婿婚特殊視は私はできず、自己の婚姻史話段階の設定に錯誤があるものと思わない。(中略)ツマドヒの語は大化以前に盛行し、奈良頃まで行われ、ムコトリの語は大まかにいうと平安中期頃から南北朝頃にかけて、あらゆる文献にみえる、そして室町期からは代表的婚姻語として、ヨメイリの語が見えはじめるこれらの婚姻語は各時代ともに、上下層の別なく歌謡等にまで広汎にみられる。この語の変遷誇よび流通範囲からみても私の体系の妥当性が考えられてよかろう。』
平安時代を父系時代とするのは、やはり、歴史資料を無視した暴論でしかありません。ここは高群氏の主張が妥当であると思います。
さらに、洞氏は高群氏が『戸籍・計帳』について、「高群氏が夫婦別居であっても、夫が書方に同居しているのであっても、戸籍面では妻を夫籍に付し『さまで支障をきたすこともない』といわれる」とされることに対して、次の通りの批判を行いました。
これに対し、高群氏は次のように反論しています。
役人の辻褄合わせは今に始まったことではありません。両氏とも大化改新を画期としておられるようですが、その後の研究で大化改新は疑問視されるようになり、むしろ大宝律令施行がひとつの画期となっていることが明らかになっています。それはそうとして、律令施行時の官僚の苦心が偲ばれる話でもあります。律令は、唐の律令を参考に作られたので、当然家父長制を前提にしています。ところが日本は『通い婚(妻問婚)』でようやく『婿取婚』に移行が始まろうかという時期です。基礎となる社会制度が全く違うので、律令の作成者も苦心したでしょうが、施行者はより苦心を強いられたでしょう。それが、戸籍・計帳の不可思議な記載となって今に残っているのだと考えられます。従ってこれ単独ではいかようにも解釈できるという高群氏の主張は妥当な意見だと言えましょう。また決して婚姻の様式が一様であったわけではなく、原則は原則として存在しながらも前代の遺風が残っていたり、来たるべき時代の先取りが始まっていたり、混沌としていた状況を高群氏はよく理解されています。この批判の応酬も高群氏に軍配が上がります。
緒方氏は『女性史研究 第2集』家族史研究会、1976年6月10日発行「『今昔物語』における家族関係 ———高群逸枝氏の婿入婚をめぐって———」において、『今昔物語集』を題材に高群逸枝氏の平安時代を純婿入婚時代とする見解に異を唱えておられます。
ではその『今昔物語集』はいつ頃成立したのでしょう。ウィキペディアによると、
11世紀後半に起こった大規模な戦乱である前九年の役、後三年の役に関する説話を収録しようとした形跡が見られる(ただし後者については説話名のみ残されており、本文は伝わっていない)事から、1120年代以降の成立であることが推測されている。一方、『今昔物語集』が他の資料で見られるようになるのは1449年のことである。 成立時期はこの1120年代~1449年の間ということになるが、保元の乱、平治の乱、治承・寿永の内乱など、12世紀半ば以降の年代に生きた人ならば驚天動地の重大事だったはずの歴史的事件を背景とする説話がいっさい収録されていないことから、上限の1120年代からあまり遠くない白河法皇・鳥羽法皇による院政期に成立したものと見られている。 このため、『今昔物語集』は編纂後約300年間にわたって死蔵状態だったと考えられている。
ということで、もうすぐ鎌倉時代という時期に書かれたことがわかります。つまり、平安末期の風俗を反映した内容になっていることを念頭に置いておかないと批判は的外れになります。では『今昔物語集』で描かれた婚姻世相はどのようなものだったのでしょう。以下に婚姻が登場する話を数えてそれを分類した表を引用します。(『女性史研究 第2集』家族史研究会、1976年6月10日発行「『今昔物語』における家族関係 ———高群逸枝氏の婿入婚をめぐって———」7頁より引用)
第3表「洞富雄氏による改編の婚姻世帯のあり方」
| 婦家同居 | 訪婚 | 夫家同居 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|
| 二代以上の複式世帯 | 21 | 13 | 6 | 1 |
| 単式世帯 | 25 | 19 | 42 | 126 |
| 合計 | 46 | 32 | 48 | 127 |
夫家同居がかなりの数になっているのが見て取れますが、これは平安時代末期(十二世紀)の世相を反映したものだということに注意して下さい。その意味では時代を遡るほど婿取婚による婦家同居が多くなることがわかります。決して高群氏の議論を論破したことにならないのです。ですが、無視して良い数字でもありません。これは一体どのように考えるべきでしょうか。それには平安時代の様相、特に地方の様子を見てみる必要があります。
平安時代初期までは、中央政府も地方行政をおろそかにしませんでした。藤原保則のように良二千石と讃えられた良吏を輩出したのもこの時代です。しかし、わざわざそのように褒め称えるということは、その他はあまり出来が良くなかったことを示します。『万葉集』に納められている山上憶良作の「貧窮問答歌」に庶民の苦悶する姿がよく描かれています。ぜひ現代語訳だけではなく、原文とあわせてご覧になって下さい(探してみたら朗読までありました)。そのような困苦にいつまでも手をこまねいていると思う方がどうかしています。婿取婚により婿取られた男は同族と離れて生きていかなくてはなりません。もといた同族の里とて状況がそんなによいはずはなく、同じようなものだったでしょう。さすれば力をつけようとすると、血縁に頼らずに配下を集め、組織しなくてはなりません。自らが貴種である場合はともかく、そうでなければそれは実力、つまり暴力に基づいたものになるのは当然すぎるほど当たり前でしょう。自然、地縁による集団が地方で力を付け勢力を強めていくことになり、血縁による氏族共同体は徐々に解体させられていきます。そのように力をつけた農民を「殷富百姓」といいます。九世紀半ばの承和八年(西暦841年)に、そのような「殷富百姓」の一人、武蔵国男衾郡榎津郷の戸主壬生吉志福生(みぶのきしふくせい)が郡司に子供たちの庸調一生分を前納したいと嘆願し、それに対してこれを認める太政官符が発行されています。この人物は実はこれだけではなく、焼失した国分寺の仏塔の再建まで請け負っています。『続日本後紀』承和十二年(西暦845年)三月の条に、武蔵国から中央に提出された申請書のことが記載されています。内容は「承和二年に神火(神の祟りの火難)のために同国の国分寺の七層塔が一基焼失してしまった。それから十年も経つがまだ塔は再建に至らない。前男衾郡外従八位上壬生吉志福生が聖朝のために塔を造りたいと官に申し出た」もちろん政府はこの申請を許可しました。それだけでなく、官位を進めたでしょう。八世紀以来、定められた時期に調庸を納められない農民が激増していました。そのため、政府の督促は厳しくなり、郡司、土豪、「殷富百姓」らは進んで代納していたのです。政府もそれを奨励して特に外従五位下を与えたりしていました。延暦一三年(西暦794年)の平安遷都から半世紀しか経っていませんが、地方には既に彼らが隠然たる勢力が根を張っていたのです。彼らは先に述べたような方便以外にも様々な伝手を頼って官位を手に入れ、国司や郡司といった地方官に対抗していきます。しかし、普通、地方民と国司=中央派遣の官僚であれば、国司の方が官位は上です。そこで、中央貴族に手づるを求めて不輸の権、不入の権と言われている特権を獲得していきます。そうすると、国司、郡司の方も力で強行しようという動きが出てきます。対する「殷富百姓」の方も手数を集めます。こうして郎党(郎等)と呼ばれる者が組織されていきます。
九世紀を最期に班田収受が行われなくなり、地方の力は荘園に蓄えられるようになります。荘園は周辺の農民を雇って耕作させた場合もありますが、奈良時代以来増加していた浮浪人を定住させて耕作させることも多かったのです。そしてそのような血縁に頼れない人々を郡司はもとより、古来からの土豪も「殷富百姓」も積極的に取り込んで組織化していったでしょう。それは同時に、血縁による氏族集団が解体されていく過程でもあったのです。
それでは彼らは単に力を蓄えただけでしょうか。もちろん違います。平安時代の大きな騒乱と言えば、平将門と藤原純友が起こした承平天慶の乱が有名ですが、既に九世紀の天安元年(西暦857年)に対馬国で上県郡擬主帳(初期候補)卜部川知麻呂(うらべのかわちまろ)、下県郡擬大領(長官候補)直浦主(あたえのうらぬし、あるいは氏成とも)らが、党類三百人余りを引き連れ、国主の居館を包囲、放火し、対馬守立野正岑(たつののまさみね)、従者榎本成岑(えのもとのなりみね)以下十人、防人六人を殺害する事件が起きています。元慶八年(西暦884年)には、石見国で権守上毛野氏永(かみつけののうじなが)が百姓二百十七人を引き連れた邇摩郡大領外正八位上伊福部安道(いふくべのやすみち)、那賀郡大領外正六位下久米岑雄(くめのみねお)らに襲撃される事件が起きています。こうした大きい事件はそうそうなかったでしょうが、小競り合い程度なら既に日常的に発生していたのではないでしょうか。そもそも国司が地方へ下るとき郎党を組織して引き連れて行かざるを得ない状況というのがそれを証明しています。
こうした時期の土豪、「殷富百姓」たちはどのような婚姻観を持っていたでしょう。もちろん旧来からの習慣として娘には婿を取ったでしょう。それは族員が増えることを意味し、好ましいからです。では息子の場合はというと、血族の紐帯というものが意味を失っていませんから、信頼できる後継者または族員として手元に留めておきたかったに違いありません。つまり嫁を取ったと思われるのです。平安時代は、土豪、「殷富百姓」以下は婿取りと嫁取りが平行し、むしろ血脈と伝統によって支えられている貴族が古い婚姻を墨守した、つまり婿取りのみで過ごしたと考えられます。この嫁取りの傾向は地方が騒然となるにつれ、郎党という暴力装置を従えた実力者、土豪、「殷富百姓」たちの必要性と勢力を強くすることはあっても逆はありえなくなります。つまり、婚姻にせよ相続にせよ男性の発言力が強化される方向に進んでいきます。しかし、まだ完全ではありません。その過程にある状態が、上で引用した『今昔物語集』に登場する婚姻分類表に現れているとみるべきです。さらに本当の庶民は、新旧二つの勢力に挟まれ、通い(妻問婚)、婿取り、嫁取りが雑然と混在している状況だったのではないでしょうか。
では、平安時代は高群氏の主張する通り『婿取婚』と言ってしまってよいのでしょうか。あるいはそれを否定する洞氏や緒方氏に与すべきでしょうか。原則論で言った場合、前代から続いている伝統ある形式である『婿取婚』の時代であったと言い切ってしまって私はよいと思います。なぜなら、地方に「殷富百姓」が登場したり、あるいは国司が土着をするといった地方が中央から独立して試行錯誤を始めるのは平安時代に入ってからです。ですので『嫁取婚』はまだ新しい形式で主流となったとは言い難い状況にあります。地方では母系継承が困難になり男系による継承が始まっていたかも知れません。しかし、それが主流であるといえるほど普遍的に見られたとする根拠が脆弱です(『隋書』の記述だけでは不充分です)。何より伝統を墨守する貴族階級が『婿取婚』全盛で、母系による財産の継承=氏族による継承を行っています。そのような中で大勢を決したと言えるデータなしに、高群氏の論を否定することはできない、不充分であると結論します。
とはいうものの、時代は動いています。長き平安の世も終わりに近づき、武者の世が近づいてきます。『婿取婚』も変わっていくのです。平安時代も末期になると、「経営所婿取婚」という形式が貴族の間で主流になります。地方は、『今昔物語集』のデータで見た通り、『婿取婚』あるいは『妻問婚』が主流ではあるものの、確実に『嫁取婚』への移行が窺える状況になっていきます。経営所という言葉は「中右記」「長秋記」等に見え始めます。「中右記」は右大臣藤原宗忠がが記した日記で、寛治元年(1087年)から保延4年(1138年)まで記録されています。「長秋記」は、長治2年(1105年)から保延2年(1136年)までの期間が現存する源師時の日記です。
「経営所婿取婚」は、妻方の父(もしくは後見人)が、本居以外の所に経営所を特設し、そこで婿取りの式を行う方式です。この経営所は婚礼後若干期間の仮住まいとされ、その後新夫婦は永住の新居に移りますが、その新居も妻方が用意します。経営所と新居の両方を用意するのは大変であるため、後にはこれを同一の住まいとする形式に移行しました。しかしその一方で故実にうるさい貴族には冷笑されつつも、夫個人の家へ妻を迎える方式も流行し始め、時代ははっきりと嫁取りへ向かい出します。伝統に固執する貴族は「経営所婿取婚」といった形でその時流に妥協しつつもあくまで婿取りという形を崩しませんが、それも時間の問題となっています。
平安末期の院政期になると、お馴染みの平家と源氏の武士たちが登場します。彼らは在地では召上婚、進上婚といった形で『嫁取婚』を行いつつ、都の貴種やあるいは国司、郡司といった上司からは婿を取りました。平氏や源氏自体、元を正せば天皇の子孫ですから貴種ではあります。従って格下からは新たな男の血を入れるのを快く思わなかったのでしょう。こうした地方の勢いは中央に波及し、鎌倉時代に至って、「擬制婿取婚」というものを産み出します。しかし一方中央では美福門院を嚆矢として女院の勢力が全盛を迎えます。それは上皇の寵愛を基盤にしているとは言え、豊かな財政基盤を持った勢力であり、女系で譲られました。その意味で母系制もまたその余命を保っていたのです。
「擬制婿取婚」はだいたい承久の乱(西暦1221年)頃から南北朝(西暦1336年)頃まで見られる婚姻形式で、夫方の家から夫の親が一族を率いて避居し、その後に妻が移徒して婿取婚礼を行う形と、妻方で婿取婚礼を行い、夫の親および一族が死去、もしくは避居してから夫婦で移徒する形がありました。もちろんこれは貴族の例であり、武家は召上婚、進上婚と婿取婚を平行して行っていました。この頃巷ではいかに掠奪が多かったかは「私有婚」で述べた通りです。従来は女性も氏族の一員であり、また自族を動かないため、邸はもとより財産を親から伝領していたのですが、鎌倉時代以降、嫁取りの風が本格化していくにつれ、女は夫方に嫁取られるものという観念が生じ、そのため女性に財産を伝えるのは他族への流出となりかねない事態に直面したのです。このため、御成敗式目では女性の財産権について様々に制約を加えています。
この時期で注目すべき点として、「家」の確立があります。上級貴族階級では、摂家・清華・大臣・羽林・名家・半家といった家格が固定し、下級貴族階級では、例えば安倍氏と賀茂氏の天文と陰陽道のように家職が固定されるようになります。もはや氏族共同体は機能しておらず、血筋を明確にし、それぞれの職分を排他的に限定することで、既得権の獲得、存続をはかったのです。地方では、奈良時代の墾田開発から始まった土豪の動きが、平安時代を通じて徐々に支配地を守り、国司の苛政から身を守るために武装をすすめる結果となり、ついに武士として自立するに至ります。奈良時代から始まった律令制は、結果的に浮浪人や逃亡人を多数出すことになり、氏族共同体の破壊を推し進めることになりました。平安時代に入り律令制が崩壊過程に入ってもこの動きに歯止めがかからず、建前は律令制を維持しながら、実態は荘園制によって財政を維持する体制に移行します。氏族共同体を離れた人々は、領主、名主に家人、下人として再編され、地方は無秩序状態に陥ります。そのことも武士の自立の理由でした。地方領主はその支配地を明らかにする名字を名のり、支配地ともども代々これを受け継ぐ「家」を確立します。
奈良時代(八世紀)から続いた『婿取婚』も南北朝時代(十四世紀末)を過ぎるとすっかり途絶え、『嫁取婚』に取って代わられます。『嫁取婚』の時代にも婿取りは残りますが、それはもはや、跡を継ぐべき息子がいない「家」を存続させるための便宜としての婿取りであり、『婿取婚』と呼べるものではなくなります。
嫁取婚
室町時代に入ると様々な文献に「ヨメトリ」という言葉が見られるようになります。地方の擾乱が中央へ波及し、保元の乱、平治の乱を経て平氏政権を産み、源平の合戦を経て鎌倉時代に入っていったんは落ち着きますが、元寇の混乱から幕府が立ち直れず、これが建武中興の呼び水となって幕府滅亡から室町幕府設立までの戦乱に至ります。古い氏族共同体は完全に解体され、地縁に基づく集団を郎党として組織した武士団が全国に割拠します。既存の宗教はこの激変にまったく応えることができず、自ずと集団は占いや神託といった前時代的な意思決定方法を破棄して、暴力による統率に向かいます。鎌倉幕府滅亡はそれまで続いていた公家と武家の二重政治も終わらせ、武家一統の政治が指向されますが、まだそこまでの力をつけるに至っておらず、室町時代に入っても頻々と戦乱が起こっていたのは、歴史に詳しい方ならよくご存じのことでしょう。
『嫁取婚』の始まりが、掠奪婚であることは『私有婚』で既に述べました。召上婚、進上婚もその変形に過ぎません。それは既に平安時代から胚胎し、平安時代末期には公然と行われるようになり、鎌倉時代には式目をもって禁じる必要が生じるほど日常の出来事となっていました。この地方から中央への波はゆっくりとしかし着実に婚姻様式に変貌をもたらし、血脈と伝統の墨守を旨とする貴族は様々に工夫をこらしながら『婿取婚』を維持しようとしたのに対し、地方は土豪の都合によい場合は『婿取婚』で、通常は『嫁取婚』で対処し、庶民に至ってはその依存する集団によって『妻問婚』もあり、『婿取婚』もあり、『嫁取婚』もあるという(しかし『群婚』遺制は着実に守られながら)有様でした。
この流れが『嫁取婚』へと収束したのが南北朝時代以降です。暴力が支配する時代にあってそれを振るう男に全権が集中したことは論を俟ちません。血縁によらない集団を組織したとはいえ、跡取りは血縁が観念されました。しかしそれも男性に全権があるのですから、男性から男性への継承に限られます。こうして父系相続が正当化されます。その際、氏族ではなく、ある特定の男系による血脈を持つ長を頂いて同じくその血を引いている血縁集団と郎党という地縁集団を包含する組織として「家」が登場します。財産権はもちろん家父長が握り、それは婚姻にも及び、婚主が明確に家父長へ移行します。婚姻の主体が男性に固定され、女性は嫁に「取られる」ものとなります。継承が男系になるということは確実に家長の子であることが保証されなくてはなりません。そのため、姦通は厳罰を以て対処されることになります。この点も『私有婚』で言及した通りです。それでもまだ鎌倉時代初期でしたら母系観念が残っていましたので、北条政子や卿二位のように卓越した政治力を発揮する女性もいましたが、その後、女性が政治史に顔を出すことはほとんどなくなってしまいます。
新婦は「ヘヤ」と呼ばれる母屋に従属した小屋あるいは部屋そのものに住む新郎のもとへ嫁ぎ、そこで同居するか、「新造」といって新たに建物を建てそこの息子夫婦を住まわせました。前者が鎌倉時代から見られ、主として農村部に普及したのに対し、後者は応仁の乱の前後から見られ始め、主に都市部の町人の間で普及しました。婚姻の全権は家父長が握っており、両性の合意のもと営まれてきた「妻問婚」以来の伝統は失われ、家父長の承諾のない婚姻はすべて私通とされ罰の対象になりました。正式な婚姻はまず媒人を立て、婿側が婚資として結納を納め、嫁側が嫁入り支度をして、嫁行列を仕立てて嫁入りします。
しかし、『嫁取婚』が主流になったからといって家父長制が完全になって女性は無能力者に貶められたと見なす人がいますが、そんなわけはありません。変化は突然前触れなしに起こるのではなく、少しずつ生じていくのです。鎌倉時代は武士の所領は分割相続され、女子も相続の対象でした。これが所領の流出を防ぐため女子への相続は一期分といって女子一代に限られるようになり、やがて女子は惣領が扶持し、相続を行わないように変わっていくのです。男子においても鎌倉時代後期には分割相続の弊害が目立つようになり、惣領による単独相続へと変化していきます。庶子は家人化するようになり、後の戦国時代、江戸時代に続く「家」制度の基本が出来上がるのです。
そのような変化がまさに起こっている一方で、『長谷雄卿草紙(はせおきょうぞうし)』『直幹申文(なおもともうしぶみ)』『福富草紙』といった鎌倉時代に作成された絵巻物を見ると、市の店だなの売り手は皆女性であり、庶民の女性は自立して生きる人が多かったことを偲ばせます。狂言のひとつ『川原太郎』には酒売りの女のたくましい姿が描かれていますし、室町中期の事情を伝えると見なされている『七十一番職人歌合絵』には、様々な商業活動に従事する女性が描かれています。財産も確かに武士の所領の相続からは排除されていきますが、女性の財産権まで否定されていたわけではなく、現に数多くの土地寄進状、売券が残されています。少し時期が下りますが、戦国時代の日本の女性と婚姻について、ルイス・フロイス(永禄六年(西暦1563年)来日、慶長二年(西暦1597年)に長崎で死去。主著に『日本史』がある)が以下のように書き残しています。
『群婚』や「夜這い」の風俗がある日本で処女性が問題になるはずもなく、戦国期までは女性も気に入らない相手をとっとと離縁していたことがわかります。自分の財産は自分で管理し、好きなように処分する。その限りでは酒だって飲むし、行きたいところへ行く。必要とあらば文字も習う。自由すぎて堕胎も平気です。むしろ、今の女性の方が堕胎については敏感なのではないかとも考えます。この時期から徐々に女性の財産権を否定される方向に時代は進むのですが、それにしても、とてもヨーロッパと同じ家父長制とは思えないほど自由な女性の姿がそこにはあります。ただ一点腑に落ちないのは、親族の女が拐かされても見て見ぬ振りをするという点です。地主や領主の召上のことを言っているのでしょうか。あるいは借金のかたに取られていったのでしょうか。まさか本当にただの誘拐を見て見ぬふりをするとは思えません。親戚同士の情愛が薄いというのは、血縁より地縁を重視する惣村制に移行していたからでしょう。
さて、フロイスは、「嬰児殺しもたびたびで、育てることができなければ、嬰児の首筋に足をのせて殺す」「堺の町では朝、岸辺や堀端を歩いていると投げ捨てられた子供たちを見る。しかも誰一人憤りを感じないのが通例である」と零しており、ヨーロッパでは堕胎も間引きもなかったと言ってますが、実際はそんなことはなく、ヨーロッパでも堕胎や間引きが行われていたことがわかっています。近代はもとより中世はなおさら、子供がよく死んだ時代でした。日本人が子供を可愛がるようになるのはもっと後、商品経済が惣村にも浸透し、生産力が向上して生活水準全般が上向きになる江戸時代後期からです。生まれてきては何年もしないうちに死んでしまう子が多く、生命力が強くないと大人になるまで育たない時代で、可愛がるとかそうする以前にぽろぽろ死なれてしまうのですから、確かに聖職者からすると許しがたいほど薄情だったでしょう。それに、当時の惣村の生産力はまだまだ低く、生活水準を一定以上に保つためには人口制限が必要でした。コンドームや避妊薬などという便利なものなどなかったのですから、することすれば生まれてきます。堕胎するかどうかは女性の意思でも、産むと決めた女性の意思を無視してでも、産まれた子を生かすかどうかは惣村の総意で決定され、ダメだと決まったら間引きが行われたのでしょう。実際は生まれるときに始末することが多かったそうですが、母親は敏感にその空気を感じ取るらしく、どうしても産みたい場合は何だかんだと理屈を付けて実家で出産する場合もあったそうです。あるいはそれは無理でも実家から監視目的で実母が手伝いに来たりもしたとか。尤もそんなことができるのは中農クラス以上の農家だけで、下層になるとまず嫁の意思は無視されたとか。ずっと後の昭和初期、東北地方が極めて稀なほどの大凶作に襲われた際、盛んに間引きが行われたことが報告されています。昭和初期より生産力がずっと低かった中世からにかけてはもっと厳しく堕胎や間引きが行われたと考えるべきです。
女性が一般に想像されているよりも自由であったのはわかったが、それでも惣の寄合や村の宮座は男性のみで女性が排除されており、村の意思決定に参加できなかったのだから、既に男性とは同格と言い難い状況だったのではないかと言われると、まったくその通りと申し上げるしかありません。ですが、その主体性を否定されるようなところまでいっていたわけではないことも理解しておく必要があります。大人しく男の言いなりになっているような女性ばかりではなかったのです。では、その男たちは家父長制を謳歌していたのでしょうか。
鎌倉時代に出された御成敗式目の第四十二条に